中国の先端宇宙開発を読み解く
『宇宙の地政学』著者/倉澤治雄 評者/加藤千洋
2024年7月号
連載
[BOOK Review]
by
加藤千洋
(元朝日新聞編集委員)
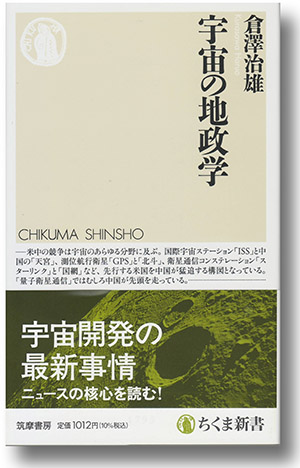
『『宇宙の地政学』』
著者/倉澤治雄
出版社/ちくま新書(本体920円(税別))
北京と東京に常駐記者を初めて送る日中記者交換協定が結ばれて今年は60周年。田中角栄政権で1972年に実現した国交正常化の重要な布石の一つだった。64年秋出発した日本側第一陣は新聞、放送、通信の9社9人。直行便が無い時代で、中継地の香港で中国側記者団と初顔合わせし、翌朝北京に向かった。
ホテルに荷を解いて間もない一夜、彼らは特大ニュースにたたき起こされる。10月16日の「中国、初の原爆実験に成功」だった。東京五輪で日本中が沸く最中に水を差す出来事でもあった。
倉澤さんによれば、この時の原爆実験は毛沢東の「両弾一星」政策に基づき、両弾は原子弾(原爆・水爆)とミサイル(導弾)、一星は人工衛星のこと。宇宙開発はここからスタートしたという。
それから30年後の90年代末、私は倉澤さんと北京特派員として一時期を共にしたが、当時から歴代特派員にない個性ありと認識し、その仕事ぶりを注目してきた。
北京特派員がまず取り組むのは、複雑怪奇な政治の内実に迫り、日々存在感を増す経済の実態を把握し、米日露などとの外交、台湾問題にも目を凝らす。まれに古代史や文化の世界に迷い込む記者もいた。
こうした規定問題をこなした上でのことだが、理系の資質に富む倉澤さんは、文革期の中断を経て再スタートした中国科学技術界をじっくりと観察していた。以後職場は変われど科学ジャーナリストとして取材を継続。その蓄積を米中対立の中で宇宙分野の競争が激化するいま、世に問おうとまとめたのが本書の狙いだろう。
1957年の「スプートニク・ショック」以来、宇宙開発は旧ソ連(現ロシア)と米国がけん引してきたが、「21世紀になって中国が独力で有人宇宙飛行に成功し、著しい躍進を遂げて米国の宇宙覇権を脅かすほどとなった」というのが倉澤さんの現状認識だ。
両大国のつばぜりあいはあらゆる分野に及ぶ。月探査では「アルテミス計画」と「嫦娥」プロジェクト、国際宇宙ステーション「ISS」と中国の「天宮」、測位航行衛星「GPS」と「北斗」、衛星通信コンステレーション「スターリンク」と「国網」……。
さらに一部の分野、例えば「量子衛星通信」など中国が先頭を走る局面も出現しているという。理系資質がいちじるしく欠如する私にはついていけない話題だが、詳しくはぜひ本書を手に取ってご確認いただきたい。
科学技術の進歩には「競争」と「協力」が不可欠だ。日本の宇宙開発は米中に比べて「周回遅れ」との厳しい見方もあるが、倉澤さんは50年に及ぶ日中科学技術協力の歴史を踏まえれば、「ライバルとして、またパートナーとして中国とどう向き合うか、本書が考えるきっかけとなれば本望だ」とも語る。
中国の発展と聞くと「脅威」と条件反射してしまうのが昨今の日本社会の空気だが、米国の科学技術やモノづくりを支えるのは中国人研究者であり、「デカップリングなど出来るはずがない」と指摘する倉澤さんのフラットな中国観察の視線は貴重だ。
BOOK Review バックナンバー
- 命を削る労作「調査報道150選」 (2026年03月号 )
- 私と母の秘密の思い出「砂川闘争」 (2026年02月号 )
- 真相解明のためなら何でもやる矜持! (2026年02月号 )
- 苦悩する「豊田章男」と紡ぐ言葉 (2025年12月号 )
- 政権中枢の「証言の数々」に刮目 (2025年08月号 )
- 申し訳ないが「読者を選びます!」 (2025年08月号 )
- 『なぜ倒産 運命の分かれ道』 (2025年03月号 )
- 超カリスマ池田大作の「黒い履歴書」 (2025年02月号 )
- 地方を元気に!「奇跡の酒蔵移転」の実録 (2024年12月号 )
- 「オバマ広島訪問へ」突き付けた切り札 (2024年12月号 )



