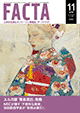『GHQ特命捜査ファイル 軍事機密費』
「空前の金満、金権」のからくりを暴く
2018年11月号
連載
[BOOK Review]
by
大鹿靖明
(朝日新聞記者)
関東軍が1931年に引き起こした満州事変は、世界恐慌と軍縮によって軍費が切りつめられた末の出来事だった。以来、戦費は膨れ上がり、それにつれ、使途が問われない軍事機密費も激増していった。機密費は、前線から日本に密かに還流し、やがて翼賛選挙の推薦候補の政治資金や宮中工作の資金に化けていく。本来の使途である戦地や敵国の秘密工作ではなく、日本国内の工作資金と軍高官の遊興費に使われたのである。
こんな軍事機密費のからくりが、主にGHQの捜査によって浮かび上がる。著者は、GHQ検事の尋問調書に依って、取り調べ模様を臨場感あふれる筆致で再現しており、読者は、まるで推理小説を読み進めるように、機密費の謎を探る旅に誘われる。十五年の戦争のうち軍事機密費は官邸に上納されるシステム化し、その仕組みは、小泉政権時に発覚した外務省の機密費と酷似する。こんなところにも、戦前と戦後の日本の連続性がうかがえるのだ。
著者が渉猟した資料は、既知のGHQ調書や160冊の文献だけでなく、国立公文書館や防衛研究所で発掘した資料も含まれる。陸軍省が秘かに作成した資料もその一つ。それには、東条英機が首相在任中、1600万円(今日価値約140億円)もの機密費を受領していたことや、2千億円に相当する機密費が沖縄戦終結後、軍高官の間で分配されていた、とある。「贅沢は敵だ」と国民に耐乏生活を強要した政権が、「空前の金満、金権だった」と著者。戦争長期化とともに高級軍人の余禄と言うべき機密費は累増するから、戦争をやめたくないわけである。本書は、こうした軍事機密費の成り立ちから使途、そしてGHQ捜査とその限界まで立体的に詳述しており、奥行きの深い調査報道型ノンフィクションとなっている。
一読後、改めて思うのは公文書の作成と保存に対する日米意識の差である。時を経て開示する米国に対し、我が国は敗戦時、責任追及を恐れて文書を焼却、さらに安倍政権下、同様の責任回避の意識から公文書改竄事件が起きた。日本の戦前と戦後は、やはり続いている。
著者は福島民友を経て朝日新聞社に入社し、事件取材に辣腕を振るう社会部型記者と思われたが、青森支局デスク時、三内丸山遺跡発掘に遭遇したのが転機となった。爾来、歴史学と周辺学問を取材領域とする学術ジャーナリストたらんと欲し、本作は二冊目。前作『虚妄の三国同盟』も良書だったが、本作は構成力と筆力が洗練さを増した。「50年後も読まれるものにしたい」と著者。刊行年しか売れないノンフィクションを書く小生には仰ぎ見る存在である。
BOOK Review バックナンバー
- 命を削る労作「調査報道150選」 (2026年03月号 )
- 私と母の秘密の思い出「砂川闘争」 (2026年02月号 )
- 真相解明のためなら何でもやる矜持! (2026年02月号 )
- 苦悩する「豊田章男」と紡ぐ言葉 (2025年12月号 )
- 政権中枢の「証言の数々」に刮目 (2025年08月号 )
- 申し訳ないが「読者を選びます!」 (2025年08月号 )
- 『なぜ倒産 運命の分かれ道』 (2025年03月号 )
- 超カリスマ池田大作の「黒い履歴書」 (2025年02月号 )
- 地方を元気に!「奇跡の酒蔵移転」の実録 (2024年12月号 )
- 「オバマ広島訪問へ」突き付けた切り札 (2024年12月号 )