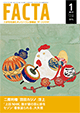『バブル 日本迷走の原点』
80年代バブルを生きた「語り部」
2017年1月号
連載
[BOOK Review]
by
掛谷建郎
(元日経新聞記者)
永野健二氏の『バブル』は1971年の三光汽船によるジャパンライン買収事件から始まる。国が主導した海運集約化に加わらなかった三光が第三者割当増資で得た資金でジライン株を買い占めた事件である。最終的に三光は所有株を手放すが、水面下で工作したのが日本興業銀行と児玉誉士夫だった。
不動産や株式の価格が暴騰し、日本中が熱狂したバブルの端緒は1985年9月のプラザ合意という見方が一般的。80年代前半のドル高を修正するため始まった日米協調の中で、過剰な内需拡大策と低金利政策が資産価格の暴騰を招いたからだ。
三光の話が冒頭にくるのは、同社に引導を渡したのが政府と二人三脚で戦後復興を主導してきた興銀だったためだ。他の銀行に債券を売って大企業に設備資金を供給した興銀は伝統的銀行体制の頂点に立ち、起債会を通じて企業の社債発行もコントロールしていた。
本書は永野氏が取材に関わった21の話を時系列で並べる。野村證券とJPモルガンの信託会社設立構想、興銀の投資銀行化を狙った大蔵省証券局長……など、一つひとつに読み応えがあるが、全体を通すとバブルの原因として、護送船団と呼ばれた銀行行政の失敗が浮かび上がる。
80年代半ばまでには、時価発行増資の拡大、国債の大量発行、金融の国際化と米国の自由化圧力……等々、護送船団が維持できなくなる条件は出揃っていた。制度疲労に対処できないところに大量のマネーが流れ込む。興銀もノンバンクへの貸し付けが全体の2割を超え、料亭の女将にまで貸すようになる。
著者が取材したバブル紳士たちが人間臭く書き込まれていることも、本書を面白くしている。小谷光浩、高橋治則、小林茂、渡辺喜太郎……バブルに踊った彼らに向ける著者の眼差しはやさしい。政策の誤りという大きな枠組みの中では、彼らも翻弄された小片にすぎなかった。
著者は日経新聞の記者時代を証券部一筋で過ごし「兜町の語り部」を自任した。当時から型通りの証券記事には収まらない取材をしていたが、今回の著作を読んで、兜町の中からかなり広い視角で外の世界を見ていたことに感心した。時の経過も過去の取材を熟成させ、今度は「バブルの語り部」になった。
印象深かったのは、引用されている中前忠氏の「(バブル経済の起点は)プラザ合意以降の円高過程で、日本の政策当局が日本経済の競争力を過小評価したこと」という言葉だ。市場経済の力で産業構造を転換する力があったのに、過度な金融緩和で構造転換のチャンスを逃してしまったという。これは異次元の金融緩和と財政支出拡大に頼るアベノミクスへの警告とも聞こえる。現状は80年代のバブル前と変わっていないように見える。
BOOK Review バックナンバー
- 命を削る労作「調査報道150選」 (2026年03月号 )
- 私と母の秘密の思い出「砂川闘争」 (2026年02月号 )
- 真相解明のためなら何でもやる矜持! (2026年02月号 )
- 苦悩する「豊田章男」と紡ぐ言葉 (2025年12月号 )
- 政権中枢の「証言の数々」に刮目 (2025年08月号 )
- 申し訳ないが「読者を選びます!」 (2025年08月号 )
- 『なぜ倒産 運命の分かれ道』 (2025年03月号 )
- 超カリスマ池田大作の「黒い履歴書」 (2025年02月号 )
- 地方を元気に!「奇跡の酒蔵移転」の実録 (2024年12月号 )
- 「オバマ広島訪問へ」突き付けた切り札 (2024年12月号 )