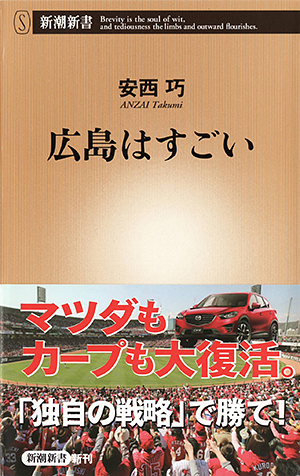『広島はすごい』
生かされてきた安芸人の「血と汗と涙」
2016年8月号
連載
[BOOK Review]
by
川本一之
(中国新聞社元社長)
読んだ後、あぜ道を歩きながら「ナンマンダブ。ありがたや」といつもつぶやいていた祖母から子どもの頃に聞かされた言葉を思い出した。「生かされている」。
手にした本から感謝の念に満ちた、不思議な感想を抱いた経験はあまりない。
「安芸門徒」と形容されるように、広島は浄土真宗の色濃い土地柄。本の中に紹介されている地域の人たちの言動から「こんなにも教えの元にある『他力』がこの地域の生き方に染み込んでいるのか」とあらためて感じさせられた。
著者が日経新聞広島支局長として赴任したのが昨年春。黒田博樹投手、新井貴浩選手のUターンに町が沸き返っていた。赤一色に染まったマツダスタジアム、カープに一喜一憂する市民。他の都市では見たことのない光景がこの広島にはあった。記者魂をくすぐられたに違いない。
「何で5倍もの年俸を蹴って」「10分の1の年俸に甘んじてどうして」。その疑問への答えは――。「今の自分があるのは広島のお陰」という二人の、自分を捨てて広島に戻ってきてくれた二人への市民の、この双方の感謝の渦がぶつかり合い、沸騰した広島国現象であった。
「広島」と言えば、マツダ、カープ、原爆・平和が定番だが、著者は魅入られたようにこの二人の歩みから広島東洋カープの誕生、そして被爆、軍都、維新、戦国時代へと広く、深く、広島のDNAを求めて筆を運ぶ。
特に印象に残ったのが「冷凍パン生地製造」の特許を開放したアンデルセンと「経営者の顔が見えない」カルビー。原爆の焼け跡で、飢えた市民を満たそうと「食づくり」に励んだ創業精神が今に息づく。その経営哲学にも「感謝」がにじみ出ている。
「群れない、媚びない、靡(なび)かない」。長い企業取材で育まれた幅広い視点からの広島論。国際化の流れの中で地方の生き方を説いた、説得力ある一冊だ。
今、JR広島駅周辺の開発が急ピッチで進んでいる。その裏で、あの『はだしのゲン』に描かれたような戦後の復興期の面影を残す町並みは次々に消えていく。駅前に被爆後に建てた筆者の妻の実家も地上げ屋に遭って、この度、取り壊されてしまった。
被爆70年の節目を過ぎ、広島は岐路に立たされているのかもしれない。「どんな町にしたらいいのか」。駅前の再開発の在り方の議論は行政からも建設会社からもなかった。灰の中から懸命に立ち上がり、生かされてきた両親の血と汗と涙が染み込んだ土地がただの普通のマンションに変わるのはいかにも寂しく、残念でならない。
「広島が国内中核都市の随所でお目にかかる『安っぽい近代化』とは無縁であってほしい」。著者のこの一節は被爆者の心情を代弁してくれている。しっかりと胸に刻んでおきたい。
BOOK Review バックナンバー
- 命を削る労作「調査報道150選」 (2026年03月号 )
- 私と母の秘密の思い出「砂川闘争」 (2026年02月号 )
- 真相解明のためなら何でもやる矜持! (2026年02月号 )
- 苦悩する「豊田章男」と紡ぐ言葉 (2025年12月号 )
- 政権中枢の「証言の数々」に刮目 (2025年08月号 )
- 申し訳ないが「読者を選びます!」 (2025年08月号 )
- 『なぜ倒産 運命の分かれ道』 (2025年03月号 )
- 超カリスマ池田大作の「黒い履歴書」 (2025年02月号 )
- 地方を元気に!「奇跡の酒蔵移転」の実録 (2024年12月号 )
- 「オバマ広島訪問へ」突き付けた切り札 (2024年12月号 )