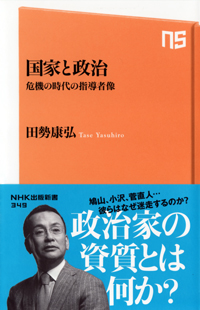「大きな政治」と「小さな政治」
『国家と政治 危機の時代の指導者像』
2011年6月号
連載
[BOOK Review]
by
坂本吉弘
(元通商産業審議官)
「政治ジャーナリストとして四〇年、『いい指導者』についていつも考えて来た」という述懐は、佐藤栄作総理から菅直人総理まで、国政の中枢を間近に見つめてきた著者の「大きな政治」に対する期待と、それがしばしば「小さな政治」に陥る失望とを深くかみしめた感慨として、読む者の胸にじわっとせまってくるものがある。
国の名誉と繁栄、国民の幸せを願い続けてきた心情は、本書の随処に現れる「愛しき日本」という言葉に凝縮されている。それは、戦争に翻弄される教え子たちへの村の分教場の先生の愛と涙であり、志半ばにして戦地に散った画学生の遺した「無言館」の未完の画作であり、「就活」に心身をすり減らす現在の大学生であり、東日本大震災の中で助け合う被災者に対する温かいまなざしから発せられている。この無辜の民の運命は、政治にかかってきたし、今もまたそうである。
眼を「国家」に転ずれば、日本は、危機的状況にある財政、普天間、尖閣に代表される外交、いずれをとっても深刻な危機感を以て臨まねばならない課題に直面している。「その国家をどのように運営し、この国をどうしようとするのかと国民は問うている」「日本の直面する危機は、政争に明け暮れる余裕などこの国にはない」と、痛切な指摘がある。
一方、政治が権力闘争の場である以上、そこに登場する政治家の人間像にせまって政治の力学と方向性を解明するのも、政治評論のプロのプロたる所以である。
自民党政権時代「“三角大福中”の激しい権力闘争の中にも、国を率いることへの使命感と情熱を感じさせた」。今日、政権政党の民主党においては、「徹底的な現実主義者」である菅総理が、小沢元代表との間に置く距離感と、これに対して「最大の政治生命の危機の中にあって小沢元代表がどう出るか」。「閉塞感が強まってゆく中で、強いリーダーシップを求めて小沢の辣腕に期待する人はまだかなり多い」とし、著者がこの20年、その分析に最も多くの時間を使ってきたという小沢元代表の去就に注目している。
震災対策で菅総理は自民党に入閣を求め、自民党はこれを断った。「連立」もまた、与野党をつうじて国の将来をかける「大きな政治」となる。
この著書の一言一句が、国の行く末に対する熱い思いと、その命運を握る政治家への冷静な目から紡ぎ出されている。
「この国の立ち居振る舞いに傲慢さがにじみ出るようになったころから政治は確実に劣化しているように見える。政治家達は国家目標について考えることを止め、『小さな政治』に狂奔するようになった」という分析は、この国の衰運がひとり政治家のみに帰するものではなく、その政治家を選ぶ有権者の知的劣化を反映しているという事の本質にせまっている。この社会を構成する私たち一人ひとりの教養が問われている。
それでも、著者は、東日本大震災を現地で目の当たりにして、「日本人は必ずやこの危機を乗り越えると思う。この三度目の危機にも『坂の上の雲』はあるに違いない」と結んでいる。
BOOK Review バックナンバー
- 命を削る労作「調査報道150選」 (2026年03月号 )
- 私と母の秘密の思い出「砂川闘争」 (2026年02月号 )
- 真相解明のためなら何でもやる矜持! (2026年02月号 )
- 苦悩する「豊田章男」と紡ぐ言葉 (2025年12月号 )
- 政権中枢の「証言の数々」に刮目 (2025年08月号 )
- 申し訳ないが「読者を選びます!」 (2025年08月号 )
- 『なぜ倒産 運命の分かれ道』 (2025年03月号 )
- 超カリスマ池田大作の「黒い履歴書」 (2025年02月号 )
- 地方を元気に!「奇跡の酒蔵移転」の実録 (2024年12月号 )
- 「オバマ広島訪問へ」突き付けた切り札 (2024年12月号 )