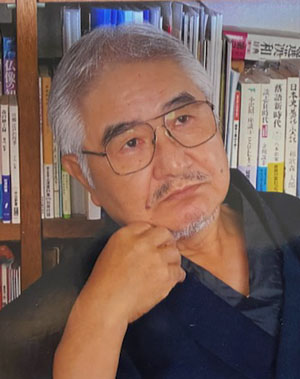追悼 「最後の噺家」柳家小三治さんとの日々/「タケちゃん、もう一度歌って……」/演芸評論家 太田博
2021年11月号
LIFE
by
太田博
(演芸評論家)

撮影:御堂義乘
噺家・柳家小三治の急死(10月7日、享年81)は意外なようでもあり、最近のテレビのドキュメンタリー番組での様子からは、やっぱりという気もする。
これまでも多くの噺家の死に接してきたが、これほどの衝撃波は感じなかった。というのも、戦後の落語界を担ってきた志ん生、文楽、小さん、さらにそれを引き継いだ志ん朝、談志、円楽といった名人・上手たちそれぞれの死は大きな引き潮のような動揺は与えた。
だが、小三治の死は落語の一切合財を根こそぎさらって行ってしまったような激震だった。落語という伝統話芸の形の崩壊という意味で、である。
「落語家」ではなくて「噺家」と呼べる落語芸の在り方を唱え続けてきた最後の師匠が小三治だった。
生来の「フラ」をどう活かすか

柳屋小三治監修の落語絵本『ねこのさら』
芸は日進月歩――。特に落語はそれぞれの時代の新鮮な空気を吸い、風圧に翻弄されつつ変化することで強靭な生命力を維持してきた融通無碍な話芸である。それを薄々感じて懸命に努力している若手もいることはいる。しかし、今の風潮は高校や大学の落研(落語研究会)を経て、ビデオテープ、DVD、ユーチューブなどの映像を主たる「師匠」として器用な落語をこなす若手が多い。これでは噺の「味わい」とか「深み」「可笑しみ」「哀しみ」、また、芸人が生来持っている滑稽味を意味する「フラ」をどう活かすか、といった目にも耳にも届き難い本質的な面は身に付かないことを感じ取っていた。「落語家」ではなく「噺家」として最も重要な精神の最後の体現者が小三治だったのでないか。
だが、決して口には出さない。意見をする、といったヤボはしない人だった。自身の師・小さんに倣ったのだろうか。
長い付き合いの間に人知れず見せた小三治の一面をたどってみると新聞やテレビの訃報に紹介された以上の小三治像が見えてくる。
新聞評とか解説を一切読まない師匠
私は朝日新聞の夕刊で20数年間、「寄席評」を担当したが、最後に取り上げたのが2010年3月26日付の柳家小三治だった。最初からそう決めていた。噺家としての腕力はすでに峠を越していたが、円熟味、巧みな話芸、風格とともに枯淡の境地にあった。人気も実力も他を寄せ付けなかった。今風に言えば「最もチケットの取り難い噺家」であった。
ところが、小三治がいつどこで高座に上がるのかを探すのにひと苦労した。なにしろ、この頃の小三治は定席にもホール落語にも滅多上がらなかった。気に入った席にしか上がらないからだ。で、やっと見付けたのが同月18日開催の東京・砂町文化センターだった。下町のホールに人気絶頂の芸人がどんな経緯で上がることになったかは不明だが、楽屋を訪ねると「ここで(高座に)上がるのがよく分かったねえ」と、ニヤッとしながらも歓迎してくれた。
「師匠の高座を私の(寄席評の)締めくくりにしたかった」と打ち明けると「ふっ、ふっ」と含み笑いしただけだった。すでに決定していた落語協会会長に就任する3カ月前のことである。
評にこう書いた。
「『受け狙い』の芸が蔓延している昨今の落語には見向きもせず、飄然とした孤高の芸境にいる」「心の赴くまま、自由闊達な落語を、他人(客)に聞かせるというより自身が楽しむために語る」「(かねてからもらしている)母親が子どもに寝物語を聞かせるような落語をやりたい、の境地にいる」と――。
ほどなくして小三治から葉書が届いた。長年の寄席評執筆への労いと、「おれの落語をそんな風に聞いててくれたの?」とあった。評に対する感想も苦情もなかった。最後の評と詠ったためのご祝儀だったろうが、感無量だった。
というのも、小三治は新聞評とか自身のカセット・テープ、CD、DVDに書かれた解説などを一切読まない師匠で通っていた。私も落語評や解説と称する紹介文を随分書かせていただいたが、その直後に楽屋で会っても何の反応もない。読んでいないのだ。
「タケちゃん、『山のけむり』、歌って」

「朝日名人会」の打ち合わせ(師匠と筆者)
東京・有楽町マリオンの朝日ホールで「朝日名人会」と称する落語会を始めたのが1999年2月だった。当時、寄席などを担当していた私に会社からの命があり、多くの関係者の協力で立ち上げることが出来た。小三治には開設初期から出演していただいた。
そんなある出番前、「ここは公(おおやけ)のホールじゃないから時間は気にしなくていいね」と聞くから「公立の施設は結構(終演時間)うるさいみたいですね。ここは朝日の持ち物ですからご自由にどうぞ」と答えるとにやりと笑って高座に向かった。結果は、なんと90分余にわたる「らくだ」だった。
自身が出演したテレビ番組のアラビア半島ロケの体験談から始まり、ラクダの特徴やら性質まで延々と約1時間、そして本題の「らくだ」を30分、という長丁場だった。しかし、帰る客は一人もいなかった。志ん朝の70分の「文七元結」を凌駕した。一席としては最長記録と、当時話題になった。
「朝日名人会」とは別に歌好きの小三治が朝日ホールを使って「小三治・歌だけの会」を開いたことがあった。知り合いの女性ピアニストを伴ってステージに上がり、彼らしく抒情歌ばかりを歌いまくった。歌唱力は知る人ぞ知る名手である。得意のおしゃべりで客を笑わせたのはもちろんである。
終盤で歌ったラジオ歌謡「山のけむり」(大倉芳郎作詞、八洲秀章作曲)にはこんな話が添えられた。
大学受験に失敗した郡山剛蔵(本名)少年は、一つ年上の初恋の女性と日比谷公園を訪れていた。5人姉弟の一人息子は小学校校長の父親に厳格に育てられていたから、受験失敗は重大な覚悟を意味していた。彼女と別れるつもりのデートだった。納得した彼女はひとこと「タケちゃん、もう一度『山のけむり』、歌って――」。
当時の流行り歌で剛蔵少年の好きな歌だった。歌い終わった時、小三治の目から涙がはらはらとこぼれるのを舞台の袖にいた私にも分かった。
引き上げてきた小三治とすれ違ったが、声は掛けられなかった。終演後、「プロのピアニストの伴奏で歌うなんて贅沢ですね」と挨拶するのがやっとだった。「一度やって見たかったんだよ」と素っ気なく場を離れていった。
オートバイが出せなくなる「駐車場物語」
小三治のこうした優しさは、落語より面白いと揶揄される「まくら」、というよりそれを拡大したトーク「ま・く・ら」により如実に表れる。
自宅近くに借りていたオートバイ(4台も所有)用の駐車場に住み着いてしまったホームレスとの滑稽で奇妙な交流を語った「駐車場物語」では、洗濯した下着をハンドルに掛けて物干し代わりに使われたり、どこかで貰って来た御飯を水道水で洗ったり、それでも駐車場が汚れると箒できれいに掃除してある。そうこうしているうちに彼が持ち込んだ段ボールが邪魔で肝心のオートバイが出せなくなってしまう。でも、出て行ってくれと言えない。帰宅すると「お帰りなさいませ」などと最敬礼の挨拶までされるようになってしまう。
ある時、大家の都合で駐車場が撤去されることが決まると、真から心配するようになっていた……。そんな日常を笑いのネタのしてしまう。その優しさがのどかな笑いを生むのである。
オートバイ、オーディオ、カメラ、ハチミツ、塩……と趣味といおうか、道楽というのか、とにかく好奇心の強い人だった。しかも、その入れ込み方は尋常ではなかった。
何かびっくりさせるような物がないだろうかと考え、福島県への旅行の土産に買ってきた温泉水を鍋で炊いて凝縮した温泉塩を差し上げると、しばしレッテルとにらめっこしていたが大事そうに鞄に仕舞い込んだ。世界中の食塩を収集していると聞いていたが、温泉塩がどういう位置にあったかは知る由もないが、趣味の部屋のどこかに残っているかどうか――。
「えっ、それを持ってるの? 困ったねェ」

撮影:御堂義乘
明治維新史が好きで、大佛次郎の『天皇の世紀』の古本を北海道で見付けて愛読している、と誰彼となく周囲の者に話していた。私が「大佛さんのサイン入りの初版本を持っていますよ」と口を滑らしたら、きっと顔を向けた。
鎌倉の大佛邸には「天皇の世紀」の原稿取りや雑用でよく伺った。そんな縁で初版本第10巻のうちの第1巻にサインをして頂戴したしろものものである。
「差し上げますが、一つ条件があります」――。
私は『柳家小三治の落語』という文庫本を持っている。実はその表紙の小三治の写真が裏焼きになった「希少本」なのだ。着物の胸の合わせが違っているので気が付いた。出版社名は敢えて伏せるが、どう検査をかいくぐって来たかは知らないが、数部が世間に出回ってしまったらしい。その一冊が私の手元にある。それに、小三治自身のサインをいただこうという少々意地悪な魂胆だった。
「えっ、それを持ってるの?困ったねェ」と言いながらも他日、「天皇の世紀」と交換に快くサインしてくれた。こんな一コマも懐かしく思い出す。
こうした気遣いは高座での演じ方にも表れる。
小三治の最後の高座は、今月10月2日の東京・府中の森芸術劇場での「猫の皿」だった。
諸国を巡って掘り出し物を捜して歩く道具屋が、江戸近郊の茶屋の脇でトウモロコシを目にする。古典落語の小道具としてどうかと思われるバタ臭い食物だが、海千山千の道具屋の上前をはねようという茶屋のおやじだけあって江戸後期に日本に渡って来たトウモロコシを栽培するくらいの才覚は持ち合わせていよう、とする繊細な演出なのだ。
もういいでしょう、小三治さん!
得意ネタの「鰻の幇間」で野だいこの一八が、金がありそうなパトロンを取り巻く「餌」にしようと持ち歩いている羊羹の存在も同様だ。失敗ばかり、エサの羊羹も効果を発揮しない。一日中飛び回っても格好の「獲物」にありつけない。しかし、羊羹だけはしっかり持ち続けている。お客さんは、なぜこの落語に小さな羊羹の包みが必要か、と思うだろう。小三治の狙いは、ケチで小心な野だいこの性根をこんな小道具で描きたかったのだ。
小三治は同じ噺を何度も高座に掛ける。ストイックに噺家としての自身と落語を磨き上げてきた。
でも、もういいでしょう小三治さん!