三耕探求③ 日本踏み潰すブラック・エレファント by 大塚耕平
世界は劇的に変化し、日本は取り残されつつある。大変であることを深層心理で認識しているが、見て見ぬ振りをしている。
2021年2月号
POLITICS
[三耕探求③]
by
大塚耕平
(参議院議員)
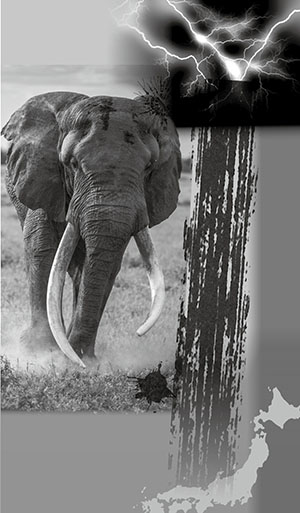
Elephant in the room
2028年に中国がGDP(国内総生産)で世界一となる。昨年12月公表の日本経済研究センターと英国経済ビジネス研究センターの予測が一致した。従来、中国が米国を上回るのは35年頃と予測されていたが、7年早まった。コロナ禍の経済への影響が中国より米国の方が大きいためである。
先入観、固定観念、思い込みは恐ろしい。この状況になっても「日本は貿易で挽回できる」と主張する有識者がいることには驚く。データを客観的に認識することが必要だ。
IMF(国際通貨基金)の最新データ(20年1~5月分)によると、米国の貿易相手のシェア最大はEU18・1%、続いてカナダ13・8%、メキシコ13・6%、中国12・4%。日本はASEAN8・2%にも及ばない5・3%である。
「中国貿易が伸びる」との声も聞くが、これも短絡的だ。中国の最大貿易相手は今やASEAN14・7%とEU13・9%。対立する米国は11・2%。日本は7・3%にとどまり、早晩韓国6・6%に抜かれる可能性が高い。
ASEANに期待する向きもあるが、地域共通経済圏は域内貿易が中心になる。ASEANは域内貿易が22・1%を占め、それに匹敵するのは中国18・8%。続いて米国11・1%、EU8・3%、日本は8・0%である。
EUは一層顕著だ。域内貿易が59・8%、続いて米国6・4%、中国6・0%が並び、日本は何と1・3%に過ぎない。
国際貿易における日本の存在感低下は否めない。根拠なく「たぶん大丈夫」「実はまだ凄い」と楽観することなく、事実を直視することが重要だ。それが日本再生の第一歩である。
技術力と競争力の危機

米国と宇宙覇権を争う中国(新型運搬ロケット「長征5号B」の打ち上げ、20年5月)
Photo:新華社/アフロ
GII(*1)はWIPO(世界知的所有権機関)が07年から公表している技術力ランキングだ。日本は4位からスタートし、12年に25位まで転落。若干回復して20年は16位だが、韓国は10位、中国は14位。既にアジアのトップではない。
スイスに本拠を置くビジネススクールIMD(*2)は1989年から各国の競争力ランキングを発表している。日本は89年から92年まで1位だったが、2019年は30位、20年は34位に下がった。
技術力や競争力は人材に影響される。英国THE(*3)ランキングは世界1500校超の大学の教育水準を評価している。21年版では1位から13位まで英米が独占。アジアトップはアジア勢過去最高20位の清華大。100位内の中国勢は6校(前年3校)、日本は東大(36位)、京大(54位)のみである。
教育水準は技術力や競争力のベースとなる科学論文数に顕著に現れる。科学技術・学術政策研究所が公表した科学技術指標2020によると、年平均の論文数で中国は30・6万と米国28・1万を抜いて首位となった。日本6・5万は前回調査(2010年)から順位を下げ、3位ドイツ6・7万に次ぐ4位である。日本の論文数は10年前の6・6万とほぼ同じだが、他国の論文数が急増しており、相対的存在感は低下。また、注目度の高い(引用率の高い)論文では9位にとどまっている。
技術力、競争力、教育水準、科学論文数は特許数に反映する。特許情報の調査企業(アスタミューゼ)公表のデータが参考になる。
AI、量子コンピュータ、再生医療、自動運転、ブロックチェーン、サイバーセキュリティ、VR(仮想現実)、ドローン、導電性高分子、リチウムイオン電池の先進10分野の特許出願数は、2000年から19年までの累計で約34万。
最新2017年では、10分野のうち中国が9分野で1位。量子コンピュータのみ米国が1位。日本は05年には自動運転など4分野で1位であったが、現在は全分野で2位以下。国別では中国が約13万と全体の4割。日米(いずれも約2割)の倍である。
15年、中国は国家戦略「中国製造2025」を打ち出すとともに、第13次5カ年計画で「知財強国」を目指す方針を顕示。研究開発費は17年で日本の3倍(約51兆円)、米国(約56兆円)に肉薄している。
こうした状況はユニコーン(企業価値10億ドル以上のスタートアップ企業)数にも反映される。米調査会社(CBインサイツ)によると、全体数は昨年11月に500社に到達。国別では米国242社、中国119社、日本はわずか4社である。
エレファント・イン・ザ・ルーム
コロナ禍で「ブラック・スワン」という言葉が注目を浴びた。「ありえないこと」を意味する英語の慣用句であったが、1697年に豪州で実際に黒鳥が発見され、以来「常識が覆ること」を意味する言葉となった。コロナ禍が世界の「ブラック・スワン」となった。
「エレファント・イン・ザ・ルーム」という慣用句も聞くようになった。部屋の中に象がいる光景を想像してほしい。誰の目にも危険である。部屋が破壊されることは予測できるにもかかわらず、それを放置していることから「見て見ぬふりをする」という意味で使われる。
ここにきて、両者を合成した「ブラック・エレファント」という言葉が使われている。つまり、「見て見ぬふりをしていた結果、これまでの常識が覆ること」を意味する。
日本の技術力、競争力は相対的に低下している。日本の企業や技術がガラパゴス化していると言われて久しい。「まだ大丈夫」と根拠のない楽観をしていると、ブラック・エレファントに遭遇して踏み潰される。
技術力も競争力も、それを生み出す源泉は人材である。そして、人材を育てるのは企業であり、国である。人材育成力に問題があれば、技術力も競争力も低下する。
日本企業は20世紀後半に一時は成功を収めた。しかし、90年代以降は変革への適応力を欠いている。
世界の産業やビジネスの変革の過半がシステムに関連していることから、日本企業のシステム観の変遷を知る必要がある。4つの局面に整理できるが、その中に日本再生のヒントがある。
第1は1980年代までのシステム黎明期。銀行システムが勘定系と情報系に分かれ始めた時代である。この頃は、競合する欧米企業と根本的な違いはなかった。
第2は90年代のBPR(*4)時代。欧米では生産性向上のために業務を抜本的に見直すことを意味し、急速に普及しつつあったPCやLANを有効活用することと表裏一体であった。
日本では業務に合わせてシステム構築する対応が主流であり、システムが有効活用できるように業務や事業を改革する動きは広がらなかった。
第3は2000年代に本格化したIT化時代。インターネットが劇的に普及し、中韓企業が台頭した時期と重なる。
この間、日本企業は人材とシステムをコストと考えてきた。そのため両者は代替的であり、人件費節減のためにシステムを使うという発想に終始した。
第4は2010年代半ば以降、現在に至るDX(デジタル・トランスフォーメーション)時代である。
DXは「デジタル技術による大変革」を意味する。「Transformation」が「X」と記される理由は、英語圏で「Trans」すなわち「横切る」「突き抜ける」という語意を「X」と表記するためである。
同時期、マクロ経済政策による景気浮揚に執心していた日本。世界の変化や人手不足にDXで対応することもなく、低賃金の派遣労働力や外国人労働者に依存。これは経営戦略とは言えない。
18年、経産省がDXレポートを公表し、企業ITシステムの複雑化、ブラックボックス化を改善しないと「2025年の崖」に遭遇すると強調したため、DXを表層的なシステム再構築と受け止めている経営者や企業も少なくない。
ブラックボックス化は、システムを単なるコストと考え、ベンダーに丸投げし、戦略ツールとして理解及び活用してこなかった結果である。
日本と欧米のシステム観の違い
さらにコロナ禍に見舞われ、人々の仕事や生活の変化に対応した国際的なコロナテック企業が続々登場。オンライン会議ツールに象徴されるようにITやインターネットの利活用が重みを増し、投資資金もコロナテック企業に集中している。
欧米、中韓でDXが進展する中、日本のデジタル化の遅れ、生産性低迷がクローズアップされた。後追いでは追い付けない時代である。客観的事実を認識し、次の変化を先取りするリープフロッグ(蛙飛び)を目指さなくてはならない。
情報処理推進機構の調査(19年)によれば、日本のIT人材の77%はSI(システムインテグレーター)等ベンダー側で働いており、ユーザー側の在籍者は2割にとどまる。7割がユーザー側に在籍し、新しいビジネスモデル創造や業務改革に取り組む欧米企業との構造的な違いである。
上述の第2期以降、世界で技術革新が加速する中、日本ではIT部署をコスト部門として切り離す動きが広がり、企業のベンダー依存が進んだ。
ビジネスモデル創造、業務改革がIT利活用の目的だが、ベンダーがそれをできるわけではない。むしろ、従来のビジネスや業務をそのまま複雑かつ代替不能のシステムとして提供することで顧客を囲い込んだ。ユーザーも従来のビジネスや業務を温存でき、双方もたれ合いの関係が構築された。
こうした実態だからこそ、日本企業はIT投資に消極的だ。OECD(経済協力開発機構)によると、17年の00年対比IT投資額は、日本は2割減、米国が6割増、フランスが2倍である。
システム観もガラパゴス化している日本の風景は、世界銀行によるビジネス環境ランキング29位、その構成要素である「事業の始めやすさ」106位という評価に繋がっている。
デジタル化の帰趨、国家の優勝劣敗を左右するいくつかの重要分野がある。
第1はもちろんAIだ。計算速度と論理回路の勝負である。計算速度ではスパコン富岳で世界一を奪還し、昨年は存在感を示した。しかし、早晩抜き返されるとともに、AIの本質は論理回路である。IBMがPC部門を中国レノボに売却し、その資金をAIワトソンの開発に投入したことが本質を象徴している。
第2は通信。日本は4Gまではアジアで最初に商用化してきたが、5Gでは中韓に先を越された。中国の5G基地局は昨年末で既に60万局。5G対応はASEAN諸国でも進み始めており、日本は後塵を拝するかもしれない。
ポスト5G競争も激化している。6Gは電波の届く範囲がさらに狭くなり、基地局は人口の10倍必要と言われる。
6G基地局のサイズは携帯電話程度だ。市街地構造物(電柱、街灯等)、移動体(自動車等)も設置場所として利用可能だ。発想の転換ができれば、日本にリープフロッグのチャンスはある。
第3は測位衛星。米国GPS(*5)は1959年に軍事技術として開発が始まったが、83年に民間開放された。中国北斗は94年に開発着手。驚異的スピードで構築が進み、2020年6月に完成。今や北斗(50基)の衛星数はGPS(30基)を上回る。日本の準天頂は4基である。
AI、通信、測位衛星が相乗効果を生み、ライフスタイルやビジネスモデルを大変革させる際のプラットフォームが第4のスマートシティだ。中国では新たな経済特区(雄安新区)に実験都市を建設する計画が進んでいる。
主戦場は半導体ICとプログラム
これら重要分野全てに関連し、生活に不可欠で身近なツールが完全自動運転電気自動車(AIEV)だ。21世紀前半はAIEVを制する者が世界を制する。
しかも、脱炭素の動きがそれを加速させている。米欧中各国は立て続けに2030年代に新車販売をEV等の環境車に限定する国策を決めている。
EV生産コストの半分を占める車載用電池も激戦だ。現在は日中韓の主要メーカーが競っているが、EUも欧州企業による生産を25年に現在の15倍にすることを目指すバッテリーアライアンスを発足させた。
日本の生命線は全固体電池の開発。固体で燃えにくく、エネルギー効率も高く、航続距離をガソリン車以上とすることが期待されている。
上記の全てに関わるのがH/W(*6)としての半導体IC、S/W(*7)としてのプログラムである。激戦地中の主戦場と言える。
半導体は、設計、素材、製造装置、生産の4分野で技術競争となっている。
生産においては、韓国サムスン、台湾TSMC、中国SMICが激しく争っている。日本のシェアは1988年の50%をピークに激減。現在は9%に過ぎず、技術者も減っている。
素材、製造装置では日本が優位だが、安閑とはできない。台湾グローバルウェーハズが独シルトロニックを買収し、ウェハー世界首位の信越化学に肉薄。同社は設計、生産に加えて、素材も手中に収める。中国も静観していない。シリコンに代わる半導体素材である窒化ガリウム等の開発を進めている。
設計は米インテル、英アームが主導権を握っているが、中国ファーウェイ傘下のハイシリコンも追撃している。だからこそ、米中対立が生じている。
昨年12月20日に亡くなった『ジャパン・アズ・ナンバーワン』(1979年)の著者エズラ・ヴォーゲル博士は2004年の同書復刻版で、日本人がハングリー精神を失ったこと、中国の産業的台頭で日本の優位は維持できなくなることに警鐘を鳴らしていた。
世界は劇的に変化し、日本は取り残されつつある。大変であることを深層心理で認識しているが、見て見ぬ振りをしている。
人材とシステムをコストと考えている限り、ブラック・エレファントに踏み潰される末路は避けられない。
(*1)GII=Global Innovation Index
(*2)IMD=International Institute for Management Development
(*3)THE=The Times Higher Education
(*4)BPR=Business Process Re-engineering
(*5)GPS=Global Positioning Satellite System
(*6)H/W=Hard Ware
(*7)S/W=Soft Ware
【「三耕探究」とは?】「学有り、論優れども、心貧すれば、任に能わず」という考えから、「耕学」「耕論」「耕心」すなわち「三耕」の「探究」の重要性を示す筆者の造語。




