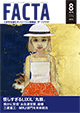新安保法制に違憲訴訟起こす
「平和的生存権侵害」の国家賠償請求!
2015年8月号
DEEP
[特別寄稿]
by
小林 節
(慶應義塾大学名誉教授・弁護士)

維新の党の安保法制独自案について意見を述べる小林節慶大名誉教授(7月2日、衆院第1議員会館)
Jiji Press
我が国の最高法である憲法が、9条の1項で(少なくとも「侵略」)戦争を放棄し、2項で軍隊(つまり戦争の道具)を不保持とし、さらに交戦権(つまり戦争の法的資格)も認めない……としている以上、我が国は、他国と「戦争」はできない。ただし、我が国も独立主権国家である以上、他国から侵略の対象にされた場合に無抵抗でその国の植民地になる謂れはない。国家としてどの国も本来的に有している自然権としての自衛権を行使して抵抗することは当然で、それ自体は憲法に違反しない。
しかし、上述のような憲法上の制約がある以上、我が国は自国の領域の外へ出て国際法上の戦争を行うことはできない。
そのような事情があって確立された我が国の防衛政策が「専守防衛」である。要するに、我が国に外敵が侵入して来た場合に限り、わが国の領域(つまり、領土と領海とそれらの上の領空)とその周辺のみを戦場として、警察予備隊として発足した(軍隊ではない第二警察としての)自衛隊を用いた抵抗しかできない。
だから、その専守防衛の意味として、「海外派兵の禁止」と「海外で他国の武力行使と一体化することの禁止」というふたつの原則も確立している。
ところが、今回の新法案の中心は(存立危機事態における)集団的自衛権の行使と(重要影響事態における)他国軍後方支援である。前者は、海外で戦争中の友好国軍と共に戦うために派兵することで、海外派兵そのものである。そして後者は、海外で戦争中の友好国軍をバックアップするために派兵することで、海外で他国の武力行使と一体化することである。
だから、今回の新安保法制は紛れもなく違憲立法である。
司法型違憲審査制の限界
このように明白に違憲な法案であっても、国会内で圧倒的な多数の議席を有している安倍政権は、批判には「馬耳東風」で、数の力で可決する構えでいる。
それに対して、多くの国民が、最高裁判所による違憲審査を定めた憲法81条を活用した抵抗はできないか? と模索している。同条は「最高裁判所は、一切の法令が憲法に適合するかしないかを決定する終審裁判所である」と定めている。だから、今回のような明白な違憲立法は、政治に自制が期待できない以上、最高裁によって止めてもらいたいと考えるのは自然である。
しかし、我が国の違憲審査制度についてはこの81条が司法の章の中にあることを無視してはならない。要するに、我が国の違憲審査制度は「司法裁判所型」(アメリカ型)であり「憲法裁判所型」(ドイツ型)ではない。だから、未だ法律が成立していない現段階で最高裁の判断を問えるドイツ型ではない。つまり、我が国では、その違憲の疑いのある法律が成立し施行された後に、その法律の下で、民事(行政事件を含む)訴訟か刑事訴訟が提起された後に、その事件の解決に必要な限度で憲法上の論点にも判断が及ぶという制度になっている。
だから、例えば、自衛隊の合憲性は、自衛隊法の立法過程の段階では問えなかったが、同法施行後に、ある基地周辺住民が、基地の施設を破損させて同法中の器物損壊罪に問われた事件(恵庭事件)になって、ようやく、前提問題としての自衛隊の合憲性が問われることとなった。
著名人1千人の原告団
私は今、新安保法制に対する違憲訴訟を準備している。
憲法前文第二段には「全世界の国民が……平和のうちに生存する権利を有する」と明記されている。そして、それを制度的に支えているのが上述の9条である。だから、私たちは、憲法によって平和的生存権という人権を保障されている。これは、「平和(つまり、戦争または戦争の危険のない状態)で暮らす状態を国家により邪魔されない」ことを保障する法的な力である。
ところが、新安保法制が成立した瞬間から、私たちは、それまでは制度上あり得なかった「海外で日本が自ら戦争に参加する」可能性の下に暮らし始めることになる。
つまり、国家によって、私たちは「戦争の危険がある状態」で暮らす生活に追い込まれ、それは平和的生存権の侵害そのもので、ここに具体的な事件(国家賠償請求訴訟を提起する根拠)が確認できる。
そこで、日本人ならば誰でも原告になり得ることになるが、だからといって何万人もの原告団を組織した集団訴訟だと費用と手間が大変になるので、むしろ、誰でも知っているような各界を代表する有名人百人とか千人に「代表」として原告団に加わっていただき、弁護団は、これまでに例のない千名を超える弁護士に名を連ねてもらおうと、今から話し合いを始めている。
もちろん、その前提となる理論武装のための研究会も立ち上げている。
これだけ広い国民的背景を持った集団訴訟であれば、それをまず担当・審理する地裁の裁判官たちも、司法官僚組織の中における将来の不利益などを意識せずに、己れの知性と良心のみに従って判断を下し易いのではあるまいか。
次なる段階は、海外への出動が命令された部隊の出発式など、公開の(報道のカメラが入っている)場面から隊員が「離脱」し、その行為に対する懲戒処分の前提(海外派兵命令)の違憲性も争うことができる。
そして、最後の不幸な段階として、このままなら必ず出ると思われる「戦死者」が出た場合に、その遺族が、その前提である命令とその根拠になっている法律の違憲性を理由に、損害賠償請求訴訟を提起することは可能である。
理不尽に対して諦める理由はない。