白川日銀「敗北」の末路
IMF・世銀の東京総会では「蚊帳の外」。世界の常識に背を向け、量的緩和を渋った咎で、景気は谷底へ。
2012年11月号
BUSINESS
[シャビー緩和の大罪]
by
高橋洋一 (嘉悦大学教授・政策工房会長)
10月9~14日、東京都内は至るところ交通規制で渋滞だらけだった。国際通貨基金(IMF)・世界銀行の年次総会が開かれたからだ。金融界のお歴々が一堂に会する年次総会のローテーションは、IMFと世銀の本部があるワシントンで2年連続開いた後、3年目は他の加盟国で開催することになっている。東京開催は1964年以来、48年ぶり2度目である。しかも、今年は日本がIMF・世銀に加盟して60年目という記念すべき年にあたっていた。
「素人」財務相と「場違い」総裁

左から白川総裁、城島財務相、ガイトナー米財務長官(11日、G7の会見で)
AFP=Jiji
日本がその経済政策を世界に発信する絶好のチャンスだった。なにしろ、世界各国から公式参加者が1万人、非公式を含めれば2万人という世界最大規模の国際会議だ。世界の財務相・中央銀行総裁らが集うため、主要会議のほかに数多くの2国間会談やG7、G20会議などが開かれた。
今回も187カ国の財務相と中央銀行総裁らが集まったのだが、日本は新任ほやほやの城島光力財務相。国対委員長あがりで大臣初体験、もちろん国際的な知名度はゼロにひとしい。かたや米国からティモシー・ガイトナー財務長官、ベン・バーナンキFRB(連邦準備理事会)議長、ユーロ圏からもドイツのウォルフガング・ショイブレら各国財務相、マリオ・ドラギECB(欧州中央銀行)総裁、英国からジョージ・オズボーン財務相、イングランド銀行のマービン・キング総裁が来日している。素人がワールドカップに参加するようなもので、「日本は財政再建を進めている」とお題目を唱えても世界は相手にしない。
それは悲しむべきことだが、もうひとり“場違い”な男がいた。こちらは英語が堪能で、知名度もあるのだが、任期も残り半年足らずでいよいよ意固地になるばかり。米欧からはまるで「蚊帳の外」で、これまた孤独な日銀の白川方明総裁である。
彼我の差はあまりに大きい。前号で報じたようにECBは9月6日、FRBは同13日、相次いで大胆な金融緩和を発表した。ECBはスペインなど1~3年物の南欧国債を無制限で買い入れ(ちょっとしたトリックで各国の支援が前提)、FRBは労働市場が改善するまで量的緩和を続けるQE3(量的緩和第三弾)に踏み切った。
ともに期限や買い入れ規模に限度を設けない「青天井」。ドラギ総裁が「ユーロ防衛にあらゆる措置」を行うとした決意は、利回り上昇で追い詰められていたスペイン国債相場をとりあえず沈静化させた。
FRBの決定に対しても、プリンストン大学のアラン・ブラインダー教授(元FRB副議長)が「素晴らしい」と称賛。コロンビア大学のマイケル・ウッドフォード教授も、QE3に具体的な時期を設けなかったことを評価し、過去の量的緩和より効果があるという見解を示した。
ウッドフォード教授は、プリンストン時代にバーナンキ教授と同僚で、辛口の理論家として有名だった。私も彼の講義を聴いたことがあるが、今回は手放しの褒めようだ。ところが、日銀はまたシャビーな(みすぼらしい)緩和でお茶を濁した。9月19日の政策決定会合で、10兆円の資産買い入れ基金の増額を柱とする金融緩和を決めただけ。ECBやFRBは政策目標達成のため「無制限」に緩和しているのに、白川日銀は相変わらず10兆円という量の制限をつけずにはいられなかったのである。
筆者は本誌で、外国為替相場は両国のマネタリーベースで決まると言ってきた(11年11月号など)が、将来のマネタリーベースの見通しで円相場はある程度読める。
ユーロもドルも一応「天井なし」の緩和をうたっているが、実際には無制限ではない。ユーロは金融不安が収まれば緩和をやめるだろうし、アメリカも失業率があと1%程度低下するまでと考えているだろう。それでも市場の現場感覚からすると、無限大を連想させる「無制限」と、数字は大きくても限定的な10兆円では、心理的インパクトが違う。円のほうが相対的な量が多くなるとは思い難く、結局、日銀の「シャビーな」緩和は円相場に影響しなかった。
IMF局長らの緩和擁護論
IMFというと、いつも日本に増税ばかり要求する国際機関という印象がある。IMFを取材する日本のマスコミが、日本人スタッフからコメントを求めるからだ。日本人スタッフは財務省の出向者ばかりなので、どうしても財務省に都合のいいコメントばかりになる。東京総会はそのフィルター抜きで本音が聞けた。
初日の9日、IMFは世界に「財政健全化を急ぎすぎるな」とのメッセージを送った。各国の財政状況を点検した「財政モニター」で、カルロ・コッタレッリ財政局長は「緩やかなペースでの財政調整がより望ましい」と発言している。特に問題なのは米国の「財政の崖」。年末以降に大型減税の失効や強制的な歳出削減が集中し、回避できないと米国の国内総生産(GDP)で4%マイナスの緊縮財政となる。コッタレッリ局長は「1947年以降、これほどの財政緊縮は例がない」と述べた。
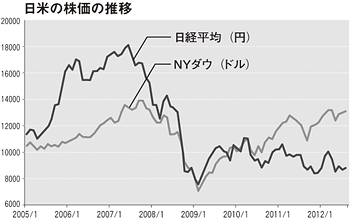
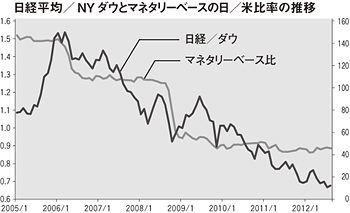
一方で、IMFは金融緩和を強調した。オリビエ・ブランシャール調査局長は「緩和的な金融政策の継続は経済成長にとって非常に強い力となる」と述べている。アジア開発銀行(ADB)の黒田東彦総裁もIMFが求める金融緩和に賛成だ。先進国・途上国を含め、日本だけがデフレに陥っていると指摘した上で、政策手段は「国債からインデックス債、株式など山のようにある」とし、デフレ脱却のためにいっそうの金融緩和を推進するよう求めた。
これが世界の常識なのだ。「お山の大将」白川日銀は何も発言できない。
総裁自身、景気の先行きに「下振れリスク」があると認めている。10月1日には9月の短観(全国企業短期経済観測調査)を公表したが、大企業製造業の業況判断指数(DI)はマイナス3と、前回の6月調査(マイナス1)より悪化している。DIの悪化は3四半期ぶり、DIのマイナスは4四半期連続だが、民間予測よりマイナス幅は小さかった。3カ月先は現状と変わらないという見通しだが、調査は反日デモと対中輸出の急減を考慮していない時期のもので「追い風参考記録」。今調査すれば、さらに悪い数字になるだろう。
業態別では、大企業非製造業のDIはプラス8だが、3カ月先は悪化見通し。中小企業では製造業が前回調査より2ポイント悪化のマイナス14で、非製造業は横ばいのマイナス9だが、3カ月先はいずれも悪化した。これでも白川総裁はアリバイづくりの小出し緩和で済ますつもりか。
思えば、日銀はこれまで「量的緩和は効かない」と言い続けてきた。その思い込みが白川総裁の手足を縛っている。本誌10年6月号などで書いてきたことだが、量的緩和のキモは「量的緩和をすると予想インフレ率が高くなる」ことに尽きる。
マネタリーベースと株価連動
これが成り立てば、予想インフレ率が高くなると実質金利(名目金利マイナス予想インフレ率)が下がるので、円相場を押し下げて輸出増加をもたらす。同時に株価を上げるので消費も増える。実質金利が下がるので、少しタイムラグを置いて設備投資が増加する。輸出、消費、設備投資が増えれば、有効需要が拡大して需給ギャップが埋まり、量的緩和は景気回復に寄与する――単純明快、これでおしまいだ。
各国のデータでも確認されている。リーマン危機以降、米国、英国、スウェーデン、スイス、最近はECBまで大胆な量的緩和に踏み切った。なんだかんだ言っても他に有効な手段がないから仕方がない。
日本だけ量的緩和を渋り、異質な金融政策をとり続けた弊害は、何といっても株価の低迷に現れている。ニューヨークのダウ工業株30種平均は、「リーマン」前の1万4千ドル近辺から7千ドルまで半分になったあと、リバウンドして9日現在で1万3470ドル前後だ。これに対し日経平均株価は1万8千円以上だったのが、いまだに8千円台で低迷している。
日経平均とNYダウの比は「リーマン」前は1を上回っていたのが、その後は1を下回る。この比率と日米のマネタリーベースの比率は驚くほど類似し、相関係数は0.8ほどになる。つまり、日米の株価の差の8割程度は、白川日銀の周回遅れの「シャビーな緩和」で説明できる。さあ、白川総裁、経済学部にいたのなら、最後は屁理屈でなく数字で反論したらどうか。



