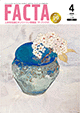某月風紋
2025年4月号 連載 [コラム:「某月風紋」]
相手企業の同意を得ない敵対的買収(TOB)が増えてきた。工作機械大手の牧野フライス製作所はニデックから、温度センサー大手の芝浦電子は台湾メーカーから、それぞれ公開買い付けを表明された。
両社に共通するのは、オンリーワンの技術を持ち業績も堅調なのに株価が低いまま“放置”されていた点だ。買収側はいずれも「企業価値の最大化」をうたい、経済産業省が2023年に公表した「企業買収における行動指針」を持ち出している。買収される側は株主利益と透明性を確保したうえで賛否を表明しなければならない。安易に拒否できない。
こうした動きは、東京証券取引所が「資本コストや株価を意識した経営」を求めていることも影響している。解散価値とされるPBR(株価純資産倍率)1倍割れに甘んじている企業を中心に、持ち合い株の売却が加速している。「物言わぬ」安定株主が減っているのだ。
それと並行して上場基準の厳格化が進んでいる。流通株式の時価総額や流通株式比率が基準を満たさず「経過措置適用」となっているところが昨年10月末時点で267社あった。LINEヤフーや三井海洋開発のような大企業も含まれる。改善しないと最悪、来年9月末で上場廃止という事態もあり得る。
東証の改革は上場企業のガバナンスを向上させ、株価上昇に寄与してきた。利益を貯め込んだまま有効活用しないことは許されなくなっている。野村証券によると、配当と自社株買いを合計した総還元額は23年度に29.4兆円と過去最高を更新。24年度はさらにそれを上回る勢いだという。
株主にとっては一見ハッピーだが、批判もある。投資会社のJPH代表取締役の青松英男さんは「キャッシュは将来の利益を出すための投資に使うべきなのに、企業はPBR1倍超えのような短期的目標を優先してしまう」と嘆く。
(ガルテナー)