「第3次世界大戦」に身構える世界/「ハイブリッド攻撃」が驚異的に増加/大塚耕平・コラムニスト
「戦争は始めたい時に始められるが、止めたい時には止められない」。日本丸は嵐の海を漂う小舟となるのか。
2025年2月号
POLITICS
[三耕探求 ⑭]
by
大塚耕平
(藤田医科大学教授)
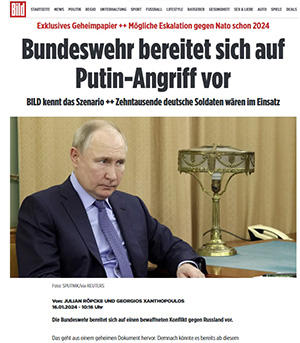
独大衆紙「Bild」のスクープ記事(24年1月16日)
2024年を時系列で振り返ると、後世「歴史の節目」と評される年であった。
1年前の24年1月16日、独大衆紙「ビルト」が驚くべきスクープを発表。独連邦軍が25年にもロシアとNATO(北大西洋条約機構)が武力紛争することを想定して準備を進めているとの独国防省機密文書のリーク記事だ。
同報道の反響は大きく、米紙等は「ロシアによる第3次世界大戦開始に備えるドイツ」という見出しを掲げた。
3日後の19日、独国防省は機密文書には言及しなかったものの「現状ではロシアによるNATOへの攻撃の可能性は低いものの、今後5~8年の間に起きる可能性がある。様々なシナリオを検討することは日常の軍事業務である」との公式見解を述べた。
同記事及び欧米メディアの追随報道によれば、独連邦軍の想定はロシアが隣国ベラルーシ及びロシア最西端の飛び地カリーニングラード(ポーランドとリトアニアの間)で兵力増強。これに対してNATOが東欧に派兵し、偶発的衝突があり得るということだ。カリーニングラードには既にロシアが核兵器搭載可能ミサイルを配備済みであり、欧州全域が射程圏内に入る。
「世界は第3次世界大戦の際にある」
ビルト紙の報道から1週間後、23日にロシアはウクライナの首都キーウをミサイル攻撃。さらに3月18日、プーチン大統領は記者会見で「NATO軍との交戦の可能性はあり得る。直接衝突すれば第3次世界大戦の一歩手前を意味する」と警告。
4月、ベラルーシのルカシェンコ大統領がロシアの戦術核兵器が同国に配備されたと発言。ウクライナを支援するNATOを威嚇した。
5月、米国はウクライナが米国提供武器を使用してロシア領を攻撃することを容認。6月、ウクライナが実際に米国製高機動ロケット砲「ハイマース」でロシア西部ミサイル基地を攻撃。同月、日本を含むG7は凍結ロシア資産によるウクライナ支援基金創設を合意。
欧米側の動きを受け、核ミサイル搭載可能なロシア海軍北方艦隊所属の原潜カザンがキューバ近海で作戦行動を開始し、6月12日にキューバに寄港した。
ロシアの核戦略原則には「通常兵器による侵略と国家存続の脅威に対し、核兵器による反撃を行う権利を有する」と明記。ロシア側の言い分は欧米諸国とウクライナの動きはこの要件を満たすものであり、1962年のキューバ危機を想起させる展開だった。

朝鮮中央テレビが報じた北朝鮮建国75年の軍事パレード
さらに6月19日、ロシアと北朝鮮が相互防衛協力を定めた「包括的戦略パートナーシップ条約」を締結。9月には北朝鮮がウクライナに派兵。実際に交戦するに至っている。
この間、中東情勢もエスカレート。4月1日、イスラエルがシリアにあるイラン外交施設を爆撃。これに対して4月13日、イランが自国領内からイスラエルを直接攻撃。これは歴史上初めてのことであり、ドローン185機、巡航ミサイル36発、弾道ミサイル110発という大規模な攻撃となった。
但し、イスラエルはこれらの99%を到達前に迎撃。イランのアブドラヒアン外相(当時)が本格的戦争になることを懸念し、攻撃計画の詳細を米国や周辺アラブ諸国に事前通告していたことが迎撃に寄与。5月19日、同外相は搭乗ヘリコプターが墜落して死亡。事故と見る向きは少ない。

「世界は第3次大戦の際にある!」
このような中、米国ではトランプが7月19日の共和党候補指名受諾演説で「世界は第3次世界大戦の際にある」と発言。「自分なら電話1本で事態を収束させることができる」と豪語し、現に大統領に復帰した。2025年、トランプの実力が試される。
バイデン政権の間にウクライナ戦争が始まり、日本は欧米に呼応してウクライナ支援を表明。中国と北朝鮮に加えて、ロシアと対峙することになった。トランプ政権の動向は日本の命運に直結する。
9月12日、プーチン大統領は西側諸国がウクライナに供与した長射程兵器でロシアに対する攻撃を認めれば西側諸国はロシアと直接戦うことになると警告した。
2024年のこうした苛烈な動きは各国に大きな影響を及ぼしている。英国では上記独紙の報道後、シャップス国防相(当時)が「今後5年間にロシア、中国、イラン、北朝鮮との紛争の危険が高まる」と発言し、各国に国防支出増大の必要性を訴えた。
NATOに加盟したスウェーデンでは、ボーリン民間防衛相が「210年間も平和を享受してきたスウェーデンでは、戦争やテロの脅威はどこか別の場所で起きていると考える『精神的防衛メカニズム』が働いている。現在、世界は第2次世界大戦以来最大の危機に瀕している。戦争に備えよ」と発言して国民に衝撃を与え、クリステション首相も「国民には国を守る義務がある」と明言した。
戦争の脅威を身近に感じているのは欧州だけではない。台湾総統選挙で独立派の民進党頼清徳が勝利したため、中国は台湾周辺で大規模軍事演習を続けている。台湾では民間防衛アカデミーで有事に備える基礎知識を学んだり、訓練に参加する市民が急増。このアカデミーに半導体メーカーUMC創業者の曹興誠(ロバート・ツァオ)氏が多額の資金を援助。曹氏はこのアカデミーやその他の組織を通じて民兵300万人を育成することを目指しており、既に資産10億台湾ドル以上を投じている。
「ハイブリッド攻撃」が驚異的に増加
1993年、米国政治学者サミュエル・ハンチントンが「文明の衝突」という概念を提唱した。ハンチントンは冷戦後の国際紛争は文明間の対立が原因となり、とくに文明と文明が接する断層線(フォルト・ライン)で紛争が激化しやすいと指摘。19世紀から20世紀に世界の中心であった西欧文明が、21世紀は中華文明、イスラム文明に対して守勢に立たされると予測した。
22年5月、フランスの人類歴史学者エマニュエル・トッドが「第3次世界大戦は既に始まっている。後から振り返れば2014年のロシアによるクリミア併合が始まりだったと言われるかもしれない」と述べた。
第3次世界大戦とは、常識的には米国及びNATOに対して、ロシア、中国、北朝鮮、イラン等が連合して複数の地域で直接武力衝突に至るイメージを抱くことだろう。既に北朝鮮はウクライナに派兵しており、中国はロシアが調達している軍需用先端電子部品等の7割以上を供給している。
とは言え、ロシアがNATOとの直接衝突、第3次世界大戦の入口に踏み込む可能性は現時点では高いとは思えない。ウクライナ1国を相手に勝利できないロシアが、米英独仏を含めた約30カ国を相手に正面から戦いを挑むとは考えにくい。
しかし、ウクライナ以外が発火点になる危険もある。北朝鮮は韓国を正式に敵国とみなし、ICBM級ミサイルを発射。しかも、ここにきての韓国の大統領弾劾と内政不安定化。中国も昨年は10回以上、台湾海峡や南シナ海、日本周辺海域で中露艦隊の軍事演習や示威航海を行っている。英仏独等の海軍も同海域に艦船を派遣しており、欧州とアジアで同時に緊張が高まっている。
加えて、ロシアとイランも協力関係にある。両国の軍事協力関係は一段と強まっている。そして、シリアのアサド政権崩壊。政権を握った反アサド勢力のシャーム解放機構(HTS)の背後にはロシアと中国が介在しているとの見方もある。中東は常に発火点となり得る。
他方、第1次、第2次世界大戦とは異なる状況が長期間続く予感もする。それは、大規模直接衝突には至らない「ハイブリッド攻撃」である。ロシアの常套手段は、テロ、暗殺、破壊工作、情報撹乱(こうらん)等のハイブリッド攻撃である。正規の武力行使ではなく、テロ等によって相手側の社会を破壊していく手段を指す。既にロシアは欧州に対し、毒殺事件等の数々のハイブリッド攻撃を仕掛けている。
欧州では、英国の安全保障機関MI5や独連邦情報局BNDが、ロシアの軍事情報機関GRUによる欧州域内でのハイブリッド攻撃が驚異的に増加していることを公表している。ロシアは、敵対国内における武器生産妨害、政治家威嚇、社会不安惹起等を企図している。
ハイブリッド攻撃の背景では、衛星通信やIT機器等の技術革新が影響している。宇宙物理学者スティーブン・ホーキング博士は2021年頃にシンギュラリティ(技術的特異点)が訪れると予測していた。それはChat GPTでブレークした生成AIかもしれない。ネット空間を含むハイブリッド攻撃において今やAIが活用されていることは周知の事実だ。
国際情勢の鍵を握る中国の動向
LAWS(自律的致死兵器)へのAI実装も加速している。韓国は昨年10月に開催した兵器展示会「KADEX」でAI軍事兵器開発を本格化させることを宣言。無人のAI戦闘機やAI戦車は実用段階に入っている。韓国では深刻な少子化も無人兵器実用化を後押ししている。
12月には、米OpenAIが防衛技術新興企業アンドゥリル・インダストリーズとの業務提携を発表。OpenAIは自社の技術を軍事転用しない社是を掲げていたが、昨年1月に利用規約を改定し、方針転換した。
これらの動きに先立ち、イスラエルとハマスとの戦闘においてもハイブリッド戦を思わせる実態(技術利用)が明るみに出ている。

イスラエル軍が公開したハマス最高幹部の最期を捉えたとする無人機の映像(ネット上で公開されているCNNニュース映像より)
それはイスラエル国防軍(IDF)がAI標的生成システム「ラベンダー」を使用しているという事実だ。ラベンダーはハマスとイスラム聖戦(PIJ)の軍事部門に所属している疑いのある全工作員を潜在的「人物標的」としてマークするように設計されており、ラベンダーでハマス要員3万7千人の識別を行い、IDFはラベンダーの指示に従って攻撃している。
さらにIDFは、標的対象者が家族と一緒にいる夜に攻撃している。「軍事拠点より自宅を爆撃する方が簡単」という理由からだ。標的が自宅に戻ったことを追跡する「WD(Where’s Daddy 、父さんはどこ?)」と呼ばれるAI追跡システムも使用している。
LAWS同士の戦闘、AIの指示に基づく攻撃やテロ、ネット空間内での情報撹乱、社会不安扇動等のハイブリッド攻撃が長く続き、第1次、第2次とは異なる様相の大戦となる可能性がある。
2025年国際情勢の鍵を握るのは中国の動向だろう。国内の安定のためには経済好転が不可欠であり、西側諸国との関係を重視せざるを得ないからだ。
不動産不況に伴う逆資産効果から耐久消費財を中心に物価低迷が続き、昨年11月の生産者物価指数(PPI)前年比は2.5%下落。2年2カ月連続でマイナスだ。昨年初から10月までの土地使用権売却収入は前年比33%減少で、ピーク時の21年比では55%も減っている。
不動産不況で行き場を失った資金は債券市場に流入。10年国債利回りは昨年11月に一時1.7%台まで低下。超長期30年国債利回りも2%程度まで低下し、一時日本の利回りを下回った。高成長を続けてきた中国の金利が日本の金利を下回るのは2005年3月以来。当時の中国超長期国債の流動性は極めて低く、実体経済を反映していなかった。日中金利逆転は実質的には初めてのことだ。
海外資金逃避の動きも活発化。2021年に過去最高を記録した中国への直接投資はその後急減し、24年は1990年以降で初めて流出超過になる見通しだ。
昨年12月9日、中国共産党政治局会議は25年の金融政策を「適切な緩和」に転換することを決定。中国の金融政策は「緊縮」「適切な緊縮」「安定」「適切な緩和」「緩和」の5段階に区分されており、11年以降、中立的な「安定」を旨としてきたが、これを「適度な緩和」に変更した。この表現が使われるのはリーマンショック後の09年以来14年振りである。
日本の経験からわかるように、不動産バブル崩壊で冷え込んだ経済を金融政策で回復させることは困難だ。さらなる金融緩和は銀行収益悪化や人民元安を招き、海外資金流出を加速させる。両刃であることがわかっていながらそうせざるを得ない。
安定した強固な政治経済基盤が必須
電気自動車(EV)最大手BYDを筆頭に躍進する自動車産業も、業界全体では巨額の開発費が重荷となり、収益悪化が進んでいる。中国車の輸出攻勢に対し、グローバルサウス各国も警戒を強めており、先行き不透明感が増している。
トランプ政権は関税引き上げを主張。中国政府は報復関税規定を設けた関税法を施行し、米国との貿易戦争の準備を進めている。トランプ関税に対処するため人民元安容認との見方もあるが、上述のとおり通貨安は海外資金流出(キャピタルフライト)のリスクがある。
IMF(国際通貨基金)や有力民間シンクタンクは、中国の2029年成長率は3.3%まで鈍化し、30年代半ばには2%を割り込むと予測。少子高齢化、労働人口減少等の構造問題も解決の糸口が見えず、上述の日中金利逆転を「中国高成長終焉の象徴的事例」と表現する向きもある。
経済不況下の中国では労働争議が頻発している。賃金未払いと人員削減が社会問題化している。
こうした状況の中国が、経済好転を目指して西側諸国と関係改善を目指すか、対外強硬姿勢で国民の目を逸らすのか。25年の国際情勢は中国の動向が鍵を握る。
世界の指導者は中世欧州の高名な政治思想家であり、『君主論』の著者として知られているマキアベリが遺した2つの言葉を肝に銘じなければならない。ひとつは「戦争は始めたい時に始められるが、止めたい時には止められない」。誰もが反芻すべき言葉である。
もうひとつは「フォルトゥーナを引き寄せるにはヴィルトゥが必要である」 。「フォルトゥーナ(Fortuna)」は「運」、「ヴィルトゥ(Virtu)」は「徳」「技量」などと訳される。平和という「運」を手繰り寄せるためには、「徳」「技量」、言い換えれば「政治的判断」「政治的手腕」が求められる。
経済力低下が著しい日本の国際政治における影響力は限定的だ。日本丸は嵐の海を漂う小舟となるのか。激動の2025年を乗り切るには、政争に明け暮れることなく、安定した強固な政治経済基盤が必要な局面だ。




