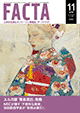裁判官「物言えば唇寒し」 岡口分限裁判と井垣懲戒
「裸の意見」をツイートする判事と、少年Aのための情報発信に腐心した元判事に「口封じ」。
2018年11月号 DEEP

岡口基一東京高裁判事
Photo:Jiji Press
9月11日、岡口基一(きいち)東京高裁判事は最高裁の「審問室」で大法廷判事15人全員に囲まれていた。追い込んだのは「犬の飼い主」。本誌2月号では彼がツイッターで判決文を紹介した殺人事件の遺族から抗議を受けて東京高裁が謝罪した顛末を報じたが、今回も全く同じ構図だ。
「え? あなた? この犬を捨てたんでしょ? 3カ月も放置しておきながら……」
岡口氏が訴えられた側の主張をこう要約したところ、訴えた側が東京高裁を訪れ、「傷つけられた」とクレームをつけた。岡口氏は林道晴東京高裁長官に呼ばれ、「ツイートをやめろ、でなければ分限裁判にかける」と言われて拒否した結果がこれだという。
実にバカバカしい話だが、もはや岡口氏排除の意図を隠そうともしない東京高裁の露骨さは何なのか。岡口氏は共同通信ヘの寄稿(9月5日配信)の中で「裁判官をベールに包むことで権威を守ろうとする、行き過ぎた裁判官統制」だと主張した。
法曹界の岡口氏をめぐる空気は「微妙」になっている。弁護士の間からも「裁判所の情報公開に悪影響が出るのは困る」などと辟易する声が出ている。だが、司法もまた他の専門家集団同様「みんなの意見」を無視できないなら、情報公開が必要ではないか。そんな節目の出来事が、20年前にもあった。

井垣康弘弁護士(元判事)はガンで声帯を失い、笛式人工声帯で発声している
1997年夏の神戸連続児童殺傷事件。残忍な犯行手口と「酒鬼薔薇聖斗」と名乗って声明を送りつけ、捜査当局を翻弄した「少年A」の大胆な行為は全国を震撼させた。Aは逮捕後、神戸家裁に送致され、少年審判で医療少年院送致の保護処分(刑事裁判でいう判決)が下された。
担当したのは井垣康弘元判事である。「少年法どおりに審判したまで」と淡々と回想するが、その経過は司法が初めて直面することばかりだった。
少年審判の場に被害者を
大がかりな精神鑑定も初めてなら、被害者遺族が少年審判傍聴と意見陳述を申し入れたのも初めてだった。少年審判は少年の更生可能性と保護のために非公開となっていたが、この「常識」が突かれたのである。
井垣氏はまず遺族に裁判官室に来てもらい、事件の概要と精神鑑定の内容を説明、質問も受けた。そして裁判官権限により遺族を審判に立ち会わせる道を探るが、家裁調査官らの猛反対で断念するに至った。
しかしメディアの「酒鬼薔薇聖斗」報道は過熱し、「自分の子もAのようになるのではないか」と、子育てへの不安が社会問題になっていた。
審判決定書の公表をメディアに求められ、全文公開を主張する井垣氏と、要旨でよいとする所長が対立した。双方譲らず、結局、所長が5千字ほどの要旨を書いて発表した。「そこからは、Aに、成育歴での問題点としての『愛着障害』と、普通の非行少年にも共通する『自己肯定感の低さ』があったという、重要なメッセージが伝わらなかった。それが残念」と井垣氏は振り返る。
もともと「工夫の人」だ。前任地で、離婚調停の際に夫婦同席でお互いの主張や意見を出し合うことで調停成立率を大幅に向上させる「岸和田方式」を編み出した。「今では全国で採用されている」(東京のベテラン裁判所書記官)
井垣氏の裁判官人生は栄達とは無縁だったが、「当事者の知恵を集めることが事件解決に役立つ」という考え方を固めていた。神戸事件に対応する裁判官としては最適だったのかもしれない。
2005年に判事を定年退官後、井垣氏は弁護士となり、少年院を仮退院して社会に出たAを気にかけつつ、少年事件と街場の事件を扱っていた。
懲戒3カ月、記者は逃亡
ところが15年。突如、月刊文藝春秋の5月号に審判書全文が掲載された。Aのプライバシーを暴いたとして井垣氏に非難が集中し、大阪弁護士会は業務停止3カ月の懲戒処分を決めた。
井垣氏はこの処分を淡々と受けた。民間人となった井垣氏に審判書を公開してAのプライバシーを明らかにする権利はない。しかし井垣氏は「Aの事件に関する事柄に限って、彼のプライバシーはないと思う。社会への影響を考えれば情報発信は必要。ルールにとらわれるのはおかしい」と持論を語った。
弁護士にとって業務停止3カ月の懲戒処分は「死刑宣告にひとしい」が、井垣氏の実害は国選弁護が2件できなくなっただけ。懲戒しないほうが、弁護士会のためになったのでは。
懲戒請求者はどうも事件関係者ではなかったようだ。最近、「余命三年時事日記」ブログ騒動のように、特定の弁護士を狙って弁護士会に大量の懲戒請求を送りつける事例が多発しているが、その先駆けであった可能性が高い。ネットを炎上させる“嫌がらせ”に似ている。
さらに、決定書を文藝春秋に持ち込んだのは井垣氏ではなく、共同通信の佐々木央(ひさし)編集委員であった。佐々木氏は自社での記事化が許されなかったため、自ら解題を書き、共同通信の肩書で発表したのである。
井垣氏の社会的発言力はこの件で大きく損なわれた。翌年、週刊文春が少年Aの写真を掲載、Aは自著『絶歌』を発表したものの、全否定の世論の前に姿を消した。
思い返せば神戸事件は、2年後の光市母子殺人事件とともに、裁判への参加や意見陳述など被害者の権利運動が法的に位置づけられる出発点だった。司法が未曾有の出来事に直面したとき、裁判官は井垣氏がしたように「市民的自由」の枠を超えて、世に発信すべきなのではないか。
だが意見表明には必ず摩擦がともなう。メディアを介する場合は調整が可能だが、佐々木氏は必要な対策を一切取らず、情報源を見殺しにした。文藝春秋掲載から3年、佐々木氏は井垣氏に一切連絡を取らず「逃亡」を続け、本誌の取材申し込みにも「既読」がついたのみだが、記事は悠々書き続け、大学でジャーナリズムまで教えている。一方でメディアに頼らず自ら発信する岡口判事もまた、大きなリスクにさらされている。得する者は司法官僚以外、誰もいない。