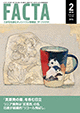知的財産の刑事罰規定範囲を明確化し濫用防止を
2018年2月号
DEEP
[特別寄稿]
by
壇 俊光
(弁護士)
復号された後のキャプチャであってもキャプチャ妨害プログラムに反する動作をするプログラムは電子書籍に付された暗号の効果を妨げるに該当する――。耳を疑うような判決がなされたのは、2017年12月19日、大阪高裁である。
あるIT会社が自分で購入した電子書籍をパソコンに保存して好きなときに視聴出来るようにしたソフトウェアを販売したところ、不正競争防止法の技術的制限手段の回避に該当するとして逮捕・起訴されたのである。
ただ、キャプチャ防止機能と電子書籍の暗号は異なる機能である。弁護側は、技術的制限手段である暗号によって実現されていない効果は「技術的制限手段の効果を妨げる」に該当しないとして無罪を主張したところ、裁判所からG難度を超える解釈が示されたのである。
「Winny」境に何でもあり
知的財産は、著作権法や特許法など個別法規で保護されているが、これらの権利を侵害する行為については刑事罰が規定されているのが通常である。しかし、ファービー人形の模倣品と疑われる人形を販売していた場合についても、刑罰規定を厳格に解釈して無罪とした(仙台高等裁判所02年7月9日)ように、抑制的に運用されてきた。
それが、大きく転換したのは、Winny事件である。これは、04年に、当時世界最先端のP2Pファイル共有ソフトの製作者を、著作権侵害を助長したとして著作権法違反幇助の罪で逮捕・起訴した事件である。この事件は、最高裁(11年12月19日)で無罪となり確定したのであるが、最初の捜査から最高裁まで8年もかかっている。さらに、残念なことに、製作者は、その後僅か1年半後に急逝した。この事件は、ファイル共有ソフトの提供の違法性が民事においても評価が定まらない状況で、刑事事件に問われるという点でも大きな衝撃が走った事件である。
09年には、インターネットを通じて漏えいした日本IBMのデータについて、流出したファイルにプログラム作成仕様書が含まれていたことから、著作権侵害に該当するとして、アップロードした者を逮捕した事件が起こった。情報漏えい対策のために著作権法違反で逮捕するというのはいかにも筋悪であるが、このころには知財の刑事処罰規定を利用する手法が広く知られるようになった。
17年には、アドビ社及び数社の販売するソフトウェアのプロダクトキーを取得するマニュアルをヤフーオークションで出品した者について、東京高裁(17年3月10日)は、商品説明欄にソフトウェアの名称を用いたことが広告としての使用であるとして商標を侵害するとした。しかし、何のためのマニュアルかを表示するだけで犯罪となれば、あまりに悪影響が大きい。
17年には、アップル社が公認していないアプリでも使えるようにしたいユーザー向けに、改造した「iPhone」を販売していた業者が商標法違反の罪で逮捕・起訴されたが、千葉地裁(17年5月18日)は、罪を構成しないとする商標法学者らの意見書が提出されているのに無視して、改造は品質を低下させている等の理由により有罪とした。しかし、改造したiPhoneは改造済みと表示されているし、購入者は通常より価値があると思って改造品を購入しているのであるから、裁判所の理由はあまりに説得力が無い。これらの判決は、日本の悪名高き刑事司法がベースとなっている。
「民事より刑事」選ぶ権利者
日本では、捜査では裁判所の発する令状によるという令状主義が採られているが、実際には「令状の自動販売機」と呼ばれており、請求すればほぼ令状が認められるのが現状である。
逮捕・勾留も、証拠隠滅の恐れありとされて容易に勾留され、最低でも23日間の身柄拘束は避けられない。しかも、起訴後の保釈でも口裏を合わせる可能性がある等の理由で認めないことが多い。無罪を争っていれば1年を超える勾留も珍しく無い。
そして、裁判所は、検察官が起訴さえすれば、事実認定や法律解釈を駆使し、最大限に有罪の可能性を追求する。自白があればほぼ有罪は確実である。テレビで見るような公平な裁判官はそこにはいない。争っていても有罪率99%以上なのは理由があるのである。
知的財産分野は、時代の移り変わりに適合する必要性があること等から、保護の範囲がある程度不明確であり、民事事件では、利益衡量に立った判断がなされる。しかし、罪刑法定主義や刑罰法規の明確性が求められるはずの刑事法の分野では、逆に、不明確さを逆手にとった、曖昧な処罰の拡大傾向がある。それだけではなく、現在では、厳格な定義規定が設けられている技術的制限手段ですら、上記のようなトンデモ解釈がなされている有り様である。そのため、知的財産の分野では、民事上違法とされる範囲よりも、刑事処罰の範囲の方が広いという逆転現象が起こっている。
知的財産の分野ではクリエーターが被疑者となる可能性がある。ハイスコアガール事件は、90年代のゲームセンターを舞台にした「ハイスコアガール」というコミックが無断でゲームのキャラを用いたとして、14年に作者らが著作権法違反容疑で大阪府警から家宅捜索を受けた事件である。捜索・差し押さえの恐怖は体験しないと分からないことであるが、捜索が創作に与える萎縮的効果は著しい。
近時、権利者は、民事と刑事の逆転現象を踏まえ、時間が掛かり、敗訴の危険のある民事事件より、刑事告訴を利用しようとする傾向が見られる。また、警察と懇意にし、刑事告訴の取次等で会員を増やしている特定の著作権団体がその傾向に拍車を掛けている。著作権では、民事を含め公平な利用について認める一般規定であるフェアユースを創設するべきという議論がなされているが、著作権者の強い反対に遭っている状況である。しかし、知的財産分野における刑事処罰の範囲の拡大は、公開された場での議論のある民事よりもずっと陰湿で危険である。
13年に国連の拷問禁止委員会の審査会で日本の刑事司法は中世レベルだと指摘されて、大使が「シャラップ!」と叫んだ非常識な事件があったが、日本は近代刑法の根幹である罪刑法定主義すら骨抜きにしようとしているのであるから中世そのものである。閉じるべきは大使の口で、速やかに刑事罰規定について処罰の範囲を明確にする見直しが必要である。