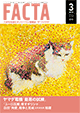南相馬「名もなき赤髭」物語
福島原発から北23キロ地点には、地元で語り継がれるお医者さんがいる。被災地から新しい医療が生まれる。
2015年3月号
LIFE
[特別寄稿]
by
上 昌広 (東京大学医科学研究所特任教授)

市立病院を守り抜いた金澤幸夫院長と及川友好副院長(右)

坪倉正治医師

小鷹昌明医師
東日本大震災から4年が経過しようとしている。縁あって筆者は、福島の医療支援を続けている。そこで出会った、名もなき「現代の赤髭」の物語を伝えたい。
南相馬市立総合病院(以下、市立病院)は、福島第一原発の北23キロに位置する中核病院(230床)だ。震災後、この病院は苦境に陥った。それは、南相馬市が、原発20キロ圏内の警戒区域、30キロ圏内の緊急時避難準備区域、30キロ圏外の無指定区域に3分割されたからだ。
市立病院が位置する原発30キロ圏には屋内退避の指示が出た。政府は「屋内にいれば問題がない」と言ったのだが、住民は「被曝の怖れがあるから、屋内にいなければならない」と受け取った。多くが自主的に避難し、高齢者と病人だけがとり残された。
避難したのは住民だけではない。医師も逃げ出した。震災前に14名いた市立病院の医師で、残ったのは金澤幸夫院長(62)、及川友好副院長(55)、鈴木史雄副院長(61)、根本剛医師(50)だけだった。この4人の医師は、地元に伝説を残した。なかでも、及川氏は、患者とスタッフから慕われる「現代の赤髭」の名に相応しい人物だ。彼は多くを語らず、腹の据わった金澤院長の存在や、共に残った医師・看護師の貢献を称え、「全員がヒーロー」と言い切る。
ライフワークは脳卒中をなくすこと
及川氏は、福島県いわき市出身で福島医大を卒業した脳外科医だ。2007年に市立病院に赴任した。事故当時、南相馬にとどまることは及川氏にとっても苦渋の決断だった。南相馬から福島に避難する妻子を送り出すとき、家族で撮った写真を渡し「もしものときは、これをお父さんだと思え」と言い残した。また、被曝も覚悟しなければならなかった。11年4月の検査で、約4千ベクレル程度の放射性セシウムによる内部被曝が確認されている。
この状況では避難するのもやむを得ない。事実、震災前239名いた病院スタッフは71名まで減った。清掃や事務などを担当する39名の派遣職員は全員がいなくなった。医療支援のために駆け付けた災害派遣医療チーム(DMAT)も帰ってしまった。さらに、地域の商業活動は停止し、3月16日に自衛隊がくるまで、ガソリン、食料品、医薬品は補充されなかった。この間、医師・看護師たちは、放射線防護服に身をくるみ、病院を守った。患者の治療から、普段はやらない事務作業や病院食の準備まで行った。そして、622名の外来患者、241名の入院患者を治療した。軽症患者には自主退院を依頼し、残った107名の患者を、福島市内などの病院に無事に搬送した。
患者を避難させた後、及川氏は避難所を回って、被災者のケアに力を注いだ。筆者が、初めて及川氏に会ったのはこの頃だ。当時の彼の口癖は「1日も早くうちの病院への入院を再開しなければならない」だった。それは、この地域は彼が専門とする脳卒中の多発地域だからだ。
脳卒中の治療は一刻を争う。市立病院に入院出来なければ、患者は70キロ以上も離れた仙台市や福島市まで搬送せざるを得ない。手遅れになる。及川氏は医療スタッフを確保するとともに、政府・福島県などと粘り強く調整し、5月9日、脳外科を中心に5床の入院治療を再開した。この5床は、すぐに満床となった。
あれから4年。及川氏は南相馬市で診療を続けている。ライフワークは、この地から脳卒中の患者をなくすことだ。及川氏は、診療を終えると8カ所の仮設住宅を回り、健康について説明して歩く。地元では「健康講話」と言われ、ファンが多い。この講話で、及川氏が強調するのは、塩分を控えることだ。東北地方は、以前から塩分摂取量が多く、市販されるカップラーメンの塩分は、西日本より高いなど、具体的な事例を挙げて分かりやすく説明する。
及川氏の努力にもかかわらず、この地域の脳卒中患者は増加傾向だ。震災のストレスが影響しているのだろう。及川氏は「少しでも被災者の健康維持に役立つなら、今後もこの活動を続けるつもりだ」と言う。ここに来て状況は変わりつつある。16年には市立病院内に「脳卒中センター(仮称)」が開設される。また、昨年5月、脳外科を希望する嶋田裕記医師(27)が、市立病院に就職した。彼は東京生まれで東大医学部出身。「この病院を選択したのは、被災地支援ではない。及川先生の下で働けば、多くの経験を積み実力がつくから」という。
ストレスで不整脈や顔面神経麻痺
2番目にご紹介したいのは、坪倉正治氏(33)だ。血液内科の専門医で、東大医科研の大学院生でもある。震災以降、月曜から木曜まで福島に赴き、金曜・土曜は東京で診療する日々を送っている。
坪倉氏は震災の時、都内の病院で勤務していた。揺れを感じたとき、「あの時と同じだ」と思ったという。坪倉氏は阪神・淡路大震災を経験している。神戸の私立灘中の1年生だった。崩壊した神戸の町、死体置き場となった母校のことを覚えている。「あのときの恩返し」と思ったそうだ。
南相馬市での坪倉氏の主たる活動は、内部被曝対策だ。南相馬は勿論、福島の被曝対策は、彼の存在抜きには語れない。内部被曝対策は苦難の連続だった。誰もノウハウがないからだ。国や福島県を頼っても、遅々として進まなかった。
坪倉氏は、11年7月より、市立病院の有志とともに内部被曝検査の準備を始めた。鳥取県より検査装置を入手したが、使い方がわからない。知人を介して自衛隊を紹介して貰い、操作法を学んだ。ただ、器械を動かし、検査結果が出ても、その解釈の仕方がわからない。早野龍五・東大理学系研究科教授にメールして、協力を仰いだ。
彼らの協力を得ながら準備を進めても、まともな結果が出てこない。体格の大きな人ほど、検査結果が低く出てしまうのだ。試行錯誤の末、原発から放出された放射性物質が周辺に存在するため、正確に測定できていないことが判明した。器械の周辺を高圧洗浄し、周囲を鉄板で遮蔽したが、上手くいかなかった。結局、11年9月にフランスのアレバ社製のFASTSCANという装置を購入し、検査は軌道に乗った。
以来、福島県内で約15万人の検査に従事した。大部分からは放射性セシウムが検出されていない。例えば、南相馬市在住の小中学生の98%が検査を受けたが、全員が正常値だった。坪倉氏は、一連の検査結果を国内外の専門誌で発表した。研究成果は、ワシントンポストなど海外メディアでも報じられ、福島の内部被曝は問題ないレベルであることが世界のコンセンサスとなった。
坪倉氏は、検査結果の地元への還元にも尽力している。行政や有志の協力のもと、住民や学校の生徒・父兄を対象に約250回の説明会を繰り返してきた。現地で活動する精神保健福祉士の吉田克彦氏(星槎大学)は「説明会を聞くと安心して帰る人が多い。カウンセラーより多くの人を救っている」と言う。とはいえ、坪倉氏の活動は順風満帆だった訳ではない。講演会の参加者から「人殺し」「東電の回し者」と非難され、ストレスから不整脈や顔面神経麻痺も発症した。坪倉氏は大学院の4年間を福島で過ごした。今春、卒業しても、活動を続けると言う。最近、彼の元には全国から若い医師が大勢集まり始めた。今春は滋賀医大出身の山本佳奈さんという女性が、初期研修医として市立病院に就職する。同院の医師は震災直後の4名から26名になる。
孤独な避難者に「男の木工」教室
坪倉氏とは対照的な生きかたで、この地域で汗をかく医師がいる。小鷹昌明氏(47)だ。小鷹氏は埼玉県出身。震災時、獨協医科大学神経内科の准教授を務めていた。当時、小鷹氏は「教授を目指して論文を書く大学での生活に魅力を感じなくなっていた」と言う。知人を介して、市立病院のことを知った小鷹氏は12年4月、獨協医大を辞職し、市立病院に就職した。それから3年、小鷹氏は地元に溶け込み、南相馬に欠かせない赤髭になった。
小鷹氏の活動は幅広い。神経内科の専門家としての診療の傍ら、患者支援に力を注いでいる。例えば「認知症の人と家族の会」、「全国パーキンソン病友の会」などの患者会に参加し、患者との交流に尽力している。小鷹氏は、看護師など病院スタッフを誘って、地元の飲み屋に行くことが多い。小鷹氏は「いつも顔見知りの患者さんと会う。よく飲まされる」と笑う。彼の関心は医療だけでない。南相馬を少しでもよくしたいと、心から願っている。小鷹氏の眼差しは、仮設住宅で暮らす孤独で不器用な避難者に向けられる。震災後、仕事を失い、引きこもりがちになった男性を対象に『男の木工』教室を始めた。彼らが趣味を持つと同時に、この講座で作った木製品は「復興お役立て木製品」として、様々な公共施設で利用されている。最近では全町避難の小高区(南相馬南部)で『男の料理』や『エッセイ講座』を催し、地元紙にも紹介された。
「除染で儲けている」などの悪口を言われると、言い返さずにはいられない。こんな熱いお医者さんを、地元が歓迎しないわけがない。彼も南相馬に住み続けるつもりだ。「被災によって壊れたものが再生するのを見届けたい」という。
南相馬はゆっくりだが、着実に復興している。そして、その一翼を担っているのが「現代の赤髭たち」だ。この地から、新しい医療が生まれつつある。