日銀確信犯の「鳩山デフレ」
実質失業率10%でなぜ円高。その底には実質金利高を放置する日銀がいる。蛮勇をふるえるのは誰か。
2009年11月号 BUSINESS [円高・雇用悪化・設備投資減]

9月24日、米ピッツバーグのG20サミットでガイトナー米財務長官と会談した藤井裕久財務相
AP Images
歴史的な政権交代から1カ月余りが過ぎた。最近、株価の動きが思わしくないことから、「鳩山不況」が市場ではささやかれはじめた。
9月の世界主要88株価指数の騰落状況を見ると、日本の東証株価指数(TOPIX)はマイナス2.3%で世界最悪。 日本を除くアジアや欧米の株式相場は、金融緩和政策などに支えられて上昇トレンドだが、日本株だけ取り残されている。
小選挙区比例代表並立制が導入・実施された1996年以降の総選挙では、株価は公示後に上げ、投票日以降に少し下げてから、その後は上昇トレンドに乗る――というパターンがほとんど。今回の鳩山政権の場合、支持率こそ70%台と高水準の滑り出しだが、選挙後の株価低迷は例を見ないことであり、政権交代のイメージダウンになりかねない。
実体経済にも不安材料がある。総選挙前には、政府の経済対策が効果をあげ、景気はドン底状態から脱したという声も聞こえていた。でも、それは“大本営発表”だったかもしれないし、一時的な小康状態にすぎなかった可能性もある。4~6月期の国内総生産(GDP)2次速報はかろうじて前期比0.6%増だったが、内需は1.0%減で、中国などの外需が1.6%増と完全な外需頼みの回復だった。
藤井・行天コンビの限界
それがここにきて円高で外需主導が崩れている。鳩山政権の重鎮、藤井裕久・財務相の円相場感は古きよき時代のもので、スタンスは「円高容認」といってもいいだろう。藤井財務相は、55年に大蔵省に入り、76年に退職した同省OBで、93~94年の細川政権で蔵相を経験している。当時はまだ円高基調であり、日本経済に高度成長の名残をとどめていたよき時代であった。この点は大蔵省の同期入省組で、藤井氏から財務相特別顧問に起用された行天豊雄・国際通貨研究所理事長も同じである。同じ時代の空気を吸っているから、円高には鷹揚だ。とりわけ行天氏は85年に円高誘導を決めたプラザ合意当時の国際金融局長であり、外需依存型の日本の産業構造を転換するため「円高阻止の為替介入はするな」という立場は今も同じである。
9月24日、G20金融サミットに出席した藤井財務相は、ティム・ガイトナー米財務長官との日米財務相会談で「為替市場は自由経済の牙城。安易に公が介入するのはどうか」と述べた。為替介入の手を自ら縛るような発言は異例のこと。鳩山政権は円高を容認すると市場に受け止められ、1ドル=90円を突破する円高を招いた。これが輸出企業を直撃する株安になり、藤井氏の“老いの一徹”に怨嗟の声があがっている。
鳩山政権は「内需中心の経済に切り替える」とも謳っているが、雇用や設備投資など内需の先行きも心もとない。8月の完全失業率は5.5%と7月に記録した過去最悪の5.7%よりは改善したが、年末にかけて6%台に乗せるのではないかと見るエコノミストも多い。
所得の伸びも芳しくない。夏のボーナスだけでなく冬のボーナスも厳しく、個人消費がどうなるか、不安の色が濃い。また設備投資でも、日銀短観の09年度設備投資計画は全産業全規模で前年度比17.3%減と過去最大の落ち込み幅だった。こうした状況では、「景気の二番底」が来ても不思議ではない。
円高、雇用悪化、設備投資減――これらは一見別々で無関係のようだが、実は複雑に絡み合っていて相互に関係している三重苦。そこにどんな対策を講じるか、必要なものはマクロ経済学の理解と、各経済変数間の具体的な相互関係のデータである。ところが、鳩山政権にはこのマクロ経済の司令塔がない。マクロ不在でミクロの対症療法だけという経済運営では体をなさない。
例えば、鳩山政権は雇用情勢の悪化に対応して緊急雇用対策本部を設置し、今年度内にも実施する短期的措置として「雇用調整助成金の要件緩和」などを検討し始めた。解雇せずに一時休業などで雇用を維持する企業に国が給付する雇用調整助成金は、統計上の完全失業率を押し下げる効果がある。8月の対象者は211万人で、これらは「隠れ失業者」といってよく、完全失業率は実態より3%強も低めの数字なのだ。つまり、日本の完全失業率は実質でみると10%近くに達している。
雇用調整助成金の原資は企業と従業員が分担してきた雇用保険料であるが、一部は税金も投入されている。もし雇用調整助成金の要件緩和で財源が足りなくなり、国債を増発することにでもなれば、金利を押し上げて設備投資を減少させるとともに円高要因にもなる。見かけの失業率を下げる代わりにいっそうの経済環境の悪化にはね返り、かえって雇用状況が悪化するかもしれない。
GDPギャップ80兆円に
マクロ経済学を使って適切かつ包括的な解を考えてみよう。まず内需要因から考えると、雇用減と設備投資減は、マクロ経済でのGDPギャップ(総供給と総需要の差額)が発生し、将来もあまり縮小しないことを意味している。足もとで40兆~50兆円の総需要不足であるが、もし「二番底」になれば、80兆円くらいに拡大するかもしれないのだ。
処方箋は二つある。一つは財政出動で有効需要を生みだすこと。麻生前政権はこの手段をとったが、明らかに規模が十分ではなかった。GDPが日本の2.4倍あるアメリカが78兆円、GDPが日本とほぼ同じ中国で4兆元(56兆円)の景気刺激策を打ったが、日本の第2次補正予算は14兆円と米中に遠く及ばない。鳩山政権が補正を削り込んでも、もともと水増しが多く目先のダメージが小さいのは皮肉だが、とにかく金融緩和が日本では不十分で、国債増発による金利先高もあって、景気対策としてうまくいったとは言い難い。
第二の処方箋は金融政策である。これは実質金利を下げ、設備投資を増やし、同時に円高対策にもなる。GDPギャップが大きく開くときは、財政政策とともに金融政策を実施すべきだというのが、マクロ経済学からの「正解」になる。
いずれにしても金融政策が鍵を握るのだが、日本では白川方明・日銀総裁にちっとも存在感がない。ベン・バーナンキ連邦準備理事会(FRB)議長がアメリカ経済を動かしているという評価と対照的である。
20世紀を代表するエコノミスト、故ミルトン・フリードマン教授の名言「インフレはいつもどこでも金融政策による現象だ」(Inflation is al- ways and everywhere a mone-tary phenomenon)を引くまでもなく、金融政策は物価に影響を与える。
ここでの物価はパソコンの価格がいくらといった個別の物価ではなく、経済全体の一般物価(消費者物価が典型例だが、個別物価の平均に一致)である。個別物価はそれぞれの競争状態によって決まるが、一般物価は金融政策で決まる。とりわけ金融政策は、一般物価の将来予想に大きく影響するのだ。
他方で金融政策は名目金利にも影響を与える。一般物価の将来予想と名目金利への影響を同時に考えてみよう。例えば、緩和的な金融政策を長く継続する場合――名目金利を低くしたり、ゼロ金利下で量的緩和を続けたりする場合、名目金利が低くなるとともに一般物価の将来予想は高くなる。つまり、実質金利(名目金利から一般物価の将来予想を引いたもの)は低くなる。この理解は、名目金利がゼロになると、もう引き下げられないので、金融緩和策はできないという、マスコミが信じる“俗説”(「流動性の罠」)が誤りであることを示す。
また「アメリカは日本より金利が高い」という通説も、名目ではそのとおりだが、物価連動国債の市場データ(流通利回り)を見れば、実質では逆であることが分かる。
日本の10年物国債は利回りが年1.2%だが、10年物価連動国債は同2.4%であり、一般物価の将来予想はマイナス1.2%である。一方、10年物米国債の利回りは3.2%、10年物価連動米国債は1.5%で、一般物価の将来予想はプラス1.7%になる。
これなら猿でもわかるだろう。つまり日本の名目金利1.2%、実質金利2.4%に対し、アメリカは名目3.2%、実質1.5%で、実質では日本のほうが高く、設備投資に懸念がでてくるのも当然なのだ。
亀井モラトリアムも使いよう
さらに、日本では一般物価の将来予想がマイナス1.2%なのでデフレ経済、アメリカはプラス1.7%なので正常。この状態だと、円・ドルレートには円高圧力がかかる。実質金利が日本のほうが高いことも円高圧力となる。不用意な藤井発言で簡単に円高になる地合いなのだ。
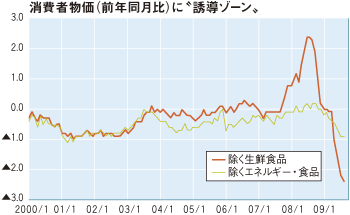
しかも、筆者の見るところ、日銀はデフレ経済の「確信犯」だ。日銀の福井俊彦前総裁は、消費者物価(除く生鮮食品)を0~2%にするよう金融政策を運営するとした(06年3月の「新たな金融政策運営の枠組み」)が、実際には消費者物価(除くエネルギー・食品)をマイナス1~0%になるようにしてきたことが2000年以降のグラフ(図参照)で一目瞭然なのだ。
欧米先進国では、消費者物価(除くエネルギー・食品)をプラス1~3%になるように金融政策を行っているので、明らかに日本は「デフレ」指向の金融政策である。この結果、名目成長率が先進国で最低という状態を十数年間も続けたり、常に円高圧力にさらされてきたのだ。
なぜこうなったかといえば、日銀法の欠陥である。先進国では中央銀行の独立性は「手段の独立性」であって「目標の独立性」ではない。つまり、消費者物価(除くエネルギー・食品)を1~3%にするという目標は政府が決め、それを達成するためにどうするかを中央銀行に任せる。ところが、日銀法では目標まで日銀が決め、デフレになっても日銀は責任を負わない。こんな強大な権限の中央銀行は世界でも珍しい。
では、国民は泣き寝入りなのか。ここでこそ民主党は「政治主導」を発揮できるのだ。日銀の意を受けた「ポチ」マスコミは日銀の肩を持って、中央銀行の独立性を侵すなと反論するだろう。そのときは、中央銀行の独立性は「手段の独立性」であって、「目標の独立性」はなく、中央銀行に目標を与えるのは政治の責任である、と堂々と言えばいい。
“蛮勇”をふるって「本石町お公家集団」に鉄槌を下すには格好の人材がいる。亀井静香・金融担当相である。民主党との連立で入閣した亀井国民新党代表は、目玉の金融対策として「中小・零細企業に対し3年間の借金返済免除」のモラトリアム(返済猶予)を主張し世を驚かせた。民主党も内心困っているだろう。
さすがに銀行と中小企業者間の貸出契約という私契約に国家が介入してモラトリアムを強制すれば、憲法29条「財産権は、これを侵してはならない」に抵触する。いくら関東大震災後に日本で行われたことがあり、海外では90年代に米ミネソタ州で農家を保護するため緊急避難的に短期間実施した例があるといっても、金融機関の中小企業向け貸付残高が300兆円ほどある日本でいきなり実行に移すのは無理筋だろう。
金利を返済猶予すれば、年利2%として年間6兆円、3年なら逸失利益は18兆円に達し、銀行は預金者に預金金利が払えなくなる。
しかしその損失分を銀行でなく、国が肩代わりするなら、景気対策として許容範囲かもしれない。GDPギャップが40兆~50兆円という深刻な状況では正当化できるだろう。国が肩代わりする方法は数多くあるが、簡単なものは銀行と中小企業者間の貸出契約に関する元利払いについて政府保証を付ければいいのだ。つまり政府保証の対象になっている中小企業で実際に元利払いの返済が滞った場合、政府保証が機能する。効果はモラトリアムを行った場合と同じになる。
これとほぼ同じだが、銀行の中小企業向け融資を政府の政策金融機関が買い取るなどして融資を入れ替える手もある。10月8日に金融庁作業部会がまとめた原案では信用保証協会による既存の損失補填制度を活用する方針で、これでモラトリアムに伴う銀行の損失は政府が負うことになる。
政策金融より日銀買い入れ
だが、霞が関官僚には、自らの権益拡大の絶好のチャンス。政府保証と政策金融機関の融資の組み合わせが亀井金融相の願望にかなうと述べたが、政府保証を少なく、政策金融機関の融資を多くすれば、官僚にとって好都合なのだ。政策金融機関は小泉改革で8機関が一本化されたが、この機会に政策金融機関の融資を拡大させれば、以前のように各省ごとに1機関が必要と言いだし、天下り先を確保できるから、「脱官僚」を掲げる鳩山政権の錦の御旗も下ろせる。
マクロ経済政策としても正しい別の方法はないか。それは銀行の中小企業向け融資を日銀が買い入れることだ(中小企業手形の日銀買い入れでもいい)。そうなれば、モラトリアムに伴う銀行の損失は日銀が負う。それでは日銀の経営が大変になると心配する人もいるだろうが、心配ご無用。日銀から政府への納付金が減るだけだ。この日銀買い入れのほうが、政策金融機関の融資拡大より優れている点がある。金融緩和の効果が大きいのだ。今はゼロ金利政策というが、貸出金利はゼロではない。だが、日銀買い入れによって金融緩和が進めば、貸出金利もゼロに近づき、この点からも中小企業の金利返済負担は減るだろう。
それだけではない。金融緩和になれば、今のデフレ経済からの脱却も同時に達成できる。すなわち、日銀買い入れは、中小企業対策とデフレ対策の一石二鳥になる。日銀は年末までに社債やCP(コマーシャルペーパー)の買い入れをやめて「出口政策」を探ろうとしているが、まったく逆だ。むしろ中小企業手形の買い入れを追加するのが、日本経済にとって正しい金融政策なのだ。
さて、「浪花節マルキスト」亀井金融相からそんなど真ん中直球が飛んできたら、日銀出身の大塚耕平副大臣はキャッチできるだろうか。



