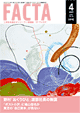「一般人」の体験が照射する『資本論』
演劇『カール・マルクス:資本論、 第一巻』
2009年4月号
連載
[IMAGE Review]
by
K

演劇『カール・マルクス:資本論、 第一巻』 (2月26日~3月1日にしすがも創造舎にて公演)
演出:ヘルガルド・ハウグ、ダニエル・ヴェツェル(リミニ・プロトコル)/出演:トーマス・クチンスキー、大谷禎之介ほか
マルクスの『資本論』が演劇化された。ドイツのアート・プロジェクトユニット「リミニ・プロトコル」が、今春開催された国際舞台芸術祭「フェスティバル/トーキョー」で上演した舞台『カール・マルクス:資本論、第一巻』のことだ。演劇教育を受けていない、その道の専門家や一般市民が表現者として舞台に立つ独得の手法が、演劇の常識を破っていて面白い。前衛志向の強いドイツ演劇の一端をかいま見させた。
2年前のドイツ公演は8人で、今回はマルクス経済学者ら日本人キャストが4人加わった東京版だ。テーマ自体は抽象的だが、出演者の個人的体験を通して語ることで具体性を帯びてくる。また、芸術祭事務局が演目を決定した時点では予想もしなかった国際的金融危機や派遣社員切りなど資本主義の矛盾露呈とも重なり、作品の現実性が増している。
上演場所は、西巣鴨にある廃校の体育館を劇場に改造した「にしすがも創造舎」。舞台装置が、客席に屹立するように迫る巨大な本棚で、その間仕切りの区画に演じ手が入っていたり、数百冊の文庫版『資本論』、ファイル、テレビモニター、胸像、インテリア雑貨などが収まっている。学校の教室のような黒板もある。
最初に登場するのがシュプレムベルク氏。ベルリンの電話局で電話交換手をしているが、全盲なので点字の『資本論』を読み始める。東京版のため、同じく全盲で東京のテレマーケティング会社に勤務する脇水哲郎氏が相手役として出て、一緒に『資本論』の「商品と貨幣」などの章を読む。福岡で生まれた脇水氏は、オーストリア、ドイツなどの盲学校に入学した経験を持ち、明治大学で政治学を学んだ後、ドイツにも留学している。
「私の人生で一度だけ、私は〈商品〉になった」とロシア語で話すラトヴィア人の映画監督の回顧に説得力がある。一家が無一文でドイツから避難する時、母親がポーランド人農婦に、パンや牛乳をやるかわりに赤ん坊を譲ってくれと言われ、売り渡されるところだったというのである。
ドイツで学生運動をした後、毛沢東主義者として中国に渡るが、実情に幻滅して現在、コンサルタント会社をベルリンで経営している者も登場する。マルクス主義が歴史的に具現した結果としてのソ連や中国の実態も、批判的に描き出しているのである。このように、このユニットの舞台は、演出家が出演者に事前に長い時間をかけて聞き取り調査を行い、その人の知識や経験を基に「人々が生きている真実の物語」を再現しようとしている。
途中、本棚から文庫版『資本論』が観客に配られる。「近代社会の経済的運動法則を明らかにすることがこの著作の最終目的である」などと蛍光ペンで印をつけた箇所がセリフに引用される。説明するのは法政大学名誉教授の大谷禎之介氏と大学院生の佐々木隆治氏。さらに、「労働者を使い捨てにするな」などという看板を出演者が体にかけて狭い舞台をデモ行進する。2時間ほどの上演だが、ゲーム的な遊びもあって飽きさせない。プロの役者の真似をしない一般人の表現力をプロが考えるいい機会になる舞台でもあった。