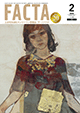最新!製薬マネー/「高額謝金」長者番付/医師20人の実名公開
トップは日大医学部の阿部雅紀医師。23年に約2334万円、155件の支払いを受けていた。
2026年2月号
BUSINESS
[製薬企業の「広告塔」]
by
尾崎章彦
(医療ガバナンス研究所理事)

受領額トップの日大医学部腎臓高血圧内分泌内科学分野主任教授・阿部雅紀医師(日大医学部HPより)
2025年11月19日、東京大学の整形外科准教授が、医療機器メーカーである日本エム・ディー・エム(Japan MDM)の関与する奨学寄附金をめぐり、贈収賄の疑いで逮捕された。
前号の記事では、医療機器業界におけるコンプライアンスの低さに加え、当該准教授の上司であり東京大学病院院長でもある田中栄医師が、講演会などを通じて製薬企業等から繰り返し謝金を受け取っていた事例を取り上げた。その上で、指導的立場にある医師ほど企業との関係が強まりやすいという医療界の構造と、それが事件の遠因となった可能性を指摘した。では、最新データである2023年時点において、指導層にある医師は実際にどの程度の謝金を受け取っていたか。
医療ガバナンス研究所が集計し、オンラインで公開している製薬マネーデータベース(https://yenfordocs.jp/)より、2023年に製薬企業から金銭を受け取った医師の金額上位20人を分析する。

まず注目すべきは、トップ層が極めて多額の謝金を受け取っている点である。上位20人の受領額は約1670万円から2330万円に分布し、各人の受け取り案件数は120~190件前後と非常に多い。単発の高額報酬ではなく、講演会への謝金を始めとして、反復的・継続的な金銭授受によって受領額が積み上がっている点が特徴だ。
上位に名を連ねるのは、診療・教育・学会活動において強い影響力を持つ医師が大半であり、企業側が、医療現場の「方向性」を形づくる立場にある指導層を重視している構図が、改めてデータから浮かび上がる。
奨学寄付金と対をなす「製薬マネー」増大
試みに、医療ガバナンス研究所が保有する最も古い2016年のデータと比較すると、当時のトップの受領額は2900万円、20位は1633万円であり、約10年が経過した現在も、金額水準は若干の低下にとどまる。
総額で見ても、製薬企業から医師への金銭支払いは、2016年の264億円から2023年には286億円へと、むしろ増加している。これは、前回も報告したように、同期間に同業界からの奨学寄附金が224億円から51億円へと大幅に減少したことと、対照的だ。
ある製薬業界OBはこの状況を、「奨学寄附金の不正利用は、30キロオーバーのスピード違反に相当する重大な違反である。一方、講演謝礼は、仮に多額でも、赤信号の横断歩道を渡る程度の軽微な違反あるいは道徳的な問題にすぎない」と比喩的に説明していた。実際、講師謝金は、1回あたりの支払額が社会通念上著しく高額でない限り、違法性が問われる可能性は低い。
さらに彼は、「製薬企業から講演依頼があっても、受け手である医師が断ればよい。特定の医師に支払いが集中するのは、企業にとって“扱いやすい”からだ」とも述べていた。
確かに、奨学寄附金の問題は一定程度整理されてきた一方で、多額の講演謝礼をどのように位置づけるべきかについては、いまだ明確な結論が出ていない。新薬開発や情報共有に医師の関与が重要であることは事実だが、謝金の受け取りについては、医師側が主体となって適切なルールを定める必要があることは間違いない。
次に診療科ごとの金銭授受であるが、まず多いのが、慢性疾患に関わる受け取りだ。
受領額トップは、日本大学医学部腎臓高血圧内分泌内科学分野の主任教授である阿部雅紀医師であり、2023年に約2334万円、155件の支払いを受けていた。阿部医師が専門とする腎臓・透析領域では、透析導入前後を通じて、降圧、腎保護、貧血、ミネラル管理などを目的とした長期継続の薬物療法が必要となる。
例えば、阿部医師への支払い額が最も多かった田辺三菱製薬(現・田辺ファーマ)(約327万円)は、腎保護薬であるSGLT2阻害薬のカナグル(2022年に慢性腎臓病への適応追加)や、腎性貧血治療薬であるHIF-PH阻害薬のバフセオ(2020年上市)など、腎臓・透析領域における主要薬剤を有している。こうした背景から、同社による阿部医師への業務依頼が相対的に増加したのだろう。
また、阿部医師については、「どの薬についても前向きに評価し、分かりやすく話してくれる。その能力は現役医師の中でも際立っている」との業界内の評価があるようだ。言い換えれば、阿部医師は、企業にとっての「扱いやすさ」を体現する存在である。
次に、糖尿病の専門家である自治医科大学附属さいたま医療センターの原一雄教授は、約2059万円・183件と、全体でも5位の受領額だ。糖尿病治療薬は、作用機序が限られ、効能や安全性も類似する上、対象患者数も多いことから、伝統的に、製薬企業間のプロモーション競争が熾烈になりやすい。
原医師への支払いが特に多かったのはアストラゼネカで、約303万円であった。同社はSGLT2阻害薬フォシーガを有する。同薬の2024年度売上高は896億円と、医薬品全体でも9位を記録している。
ただし、糖尿病内科や腎臓内科、循環器内科など、いわゆる生活習慣病を主に扱う診療科への製薬企業からの支払いは、全体としては大きく減少している印象を受けた。
具体的には、2016年から19年にかけて連続して1千万円以上の支払いを受けていた医師55人を分析した際には(2022年4月号掲載)、うち32人がこれら慢性疾患領域に関連する医師であった。しかし今回の分析では、上位20人のうち、当該領域の医師はわずか3人にとどまった。
支払い増加の際立つ自己免疫性疾患領域
他方、支払い増加が際立ったのが、超高額な生物学的製剤が多数販売されている自己免疫性疾患領域である。皮膚科を中心として、上位20人のうち14人が、この領域に従事する医師であった。
例えば、皮膚科領域における主要な自己免疫性疾患である乾癬の治療では、10剤以上の生物学的製剤が使用されている。これらの薬剤は、皮疹や関節症状の重症度、併存疾患、感染リスク、投与間隔、患者の生活背景などを踏まえて主治医の裁量で選択される。その状況下で、複数の薬剤がいずれも高い有効性を示し、明確な優劣が定まりにくいとなれば、製薬企業による情報提供やプロモーションの影響は推して知るべしだ。
さて、より重要な論点は、こうしたプロモーション活動の対象となっている薬剤が、果たしてその価格に見合う治療上の価値を提供しているのか、という点である。筆者らが国内売上上位51品目について欧州およびカナダの公的評価を参照したところ、約半数ないし8割の薬剤が「治療における追加的価値が低い」と判定されており、「高売上」が必ずしも「高い治療価値」を意味しない実態が明らかとなった。しかし日本では、新薬承認や薬価算定において追加的治療価値の提示が必須とされておらず、国際的に低評価を受けた薬剤が、国内では高売上を維持する構造が温存されている。
こうした中、米トランプ政権の薬価引き下げ政策を受け、イーライ・リリーのリックスCEOは、日本経済新聞の取材に対し「薬価が低いままでは日本で新薬は確実に減る」と発言し、日本に対して「公平な薬価」を求めた(2025年11月16日付)。もっとも、彼らが想定する「公平な薬価」とは、日本で設定されている薬価を大きく上回る水準だ。確かに「ドラッグロス」の問題は深刻であり、無視はできない。しかし、新薬であることや高売上であること自体を過度に評価するのではなく、個々の薬剤が実際にどの程度の治療効果をもたらしているのか、より慎重で批判的な視点を持つ必要がある。そして、本来、医師は、薬剤評価におけるゲートキーパーであるべき存在だ。
だが現実はほど遠いようだ。医師自身が経済的関係に深く組み込まれることで、その独立性と批判的な視点が損なわれている。
25年12月28日付の日本経済新聞では、医師の約3割が過去1年に「不要な入院」を経験したと回答し、そのうち4割が病床稼働率を高める目的で病院側から指示を受けていたと報じられた。医療費膨張の要因を一概に現場の医師に帰すことには慎重な議論が必要だが、医師自身が企業の広告塔と受け取られかねない行動を取り続けていれば、社会に対する説得力は自ずと弱まる。
医師の独立性と倫理の危機
なお、先述の自治医大内分泌代謝科・原医師は、筆者と同じ東京大学医学部の出身で、医療ガバナンス研究所理事長の上昌広とは同級生の関係にある。会食で同席した際には、終始気さくで、こちらが恐縮するほど控えめな印象を受けた。評価の是非は別として、こうした“良き人物像”が、結果として製薬企業からの“扱いやすさ”や業務依頼につながっている可能性は否定できない。
この原医師の上司にあたるのが、日本医学会会長を務める医学会の大物、門脇孝医師である。東京大学元教授(~2018年)、同大学元病院長(2011~15年)を歴任し、現在は虎ノ門病院院長も兼務している。門脇医師も製薬企業からの金銭受取額が多い医師として知られ、2016年には1164万円、すでに70歳を超えた23年にも708万円を受け取っていた。
田中栄医師の事例といい、製薬企業との密接な関係は、東京大学病院長経験者、さらには同大学糖尿病内科において、一定の歴史的文脈を持って形成されてきた側面が見え隠れする。ただ、製薬企業の「広告塔」として振る舞うことを、社会が東京大学の医師に期待、もっと言えば許容しているだろうか。疑問を抱かざるを得ない。
本来、大学病院に勤務する医師は、指導的立場にある専門職として、個人の利害を超え、医師全体に対する社会的信頼を俯瞰的に考慮しながら、若手医師や医学生を導くことが期待されている。しかし、病院経営の厳しさや奨学寄附金の減額といった構造的要因を背景に、こうした理念は次第に後景に退きつつある。代わって、自己最適化の論理のもと、講演謝礼などを通じて個人収入の確保を優先する姿勢が半ば常態化する。
このような状況は世界共通だが、海外ではすでに対応策が講じられている。例えば、2018年に米国ニュージャージー州で施行されたN.J.A.C.13:45Jは、処方医の独立性を守るため、製薬企業からの講演や助言業務に対する報酬を年1万ドルまでに制限し、贈答品の提供も広く禁止している。日本で同様の法規制は難しいとしても、大学病院や学会が主導し、所属に関わらず、医師による企業からの金銭受領を、せめて本給の半額に制限するなどの自主規制は必要だ。国に経営難を訴える一方で、多額の企業マネーを受け取り続ける姿勢は、社会的理解を得にくい。
医療の持続可能性が強く問われる現在、短期的な自己利益に目を向けることなく、専門職としての責任と社会的信頼をいかに守れるか。医師、とりわけ指導的立場にある医師の生き方が今まさに問われている。