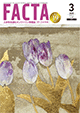連載「シン鳥獣戯画」/『吾輩はカラスである』/神経衰弱でいざ勝負!/松田裕之・日本生態学会元会長
2025年3月号
LIFE
[シン鳥獣戯画]
by
松田裕之
(日本生態学会元会長)

石神井公園のカラス(撮影/宮嶋巌)
吾輩は嘴太(はしぶと)烏である。嘴細(はしぼそ)烏(がらす)とともに都市部にも棲み、ゴミをあさり、数を増やしてきた。ゴッホが「カラスのいる麦畑」に描いた時代以前から、人を恐れず、人間社会のそばに棲みついてきた。
吾輩の近縁種に嘴細烏がいる。よく見ると嘴の太さが違い、一回り小さく、声は吾輩のほうが澄んだ美声である。分布域は嘴細の方が広く、ユーラシア各所にいる。彼らは農村などの開けた場所に住み、吾輩は比較的山林など高さのある環境に多い。かの地に我々嘴太はいないから、ゴッホの絵は嘴細だろう。北海道教育大学の三上修教授らの研究チームも、函館近辺の調査をした際に「秋冬の農耕地帯では、比較的広い範囲でハシボソガラスだけ数十羽がともに採食していた」などと書いている。きっとゴッホを思い出していたに違いない。
都市には嘴細はあまりいないとも言われていたが、場所や景観によるようだ。特に、東京の上野公園から東大本郷キャンパスにかけての1977年の樋口広芳博士らの調査では、嘴細は1羽もいなかったらしい。2000年の都心部に位置する文京区の別の調査でも0である。ただし1990年の帯広の市街地や98年の京都大学と京都の下鴨神社では逆に嘴細が多数派だったという。近くに農地など彼らの本来の棲み場所があり、平坦な市街地で河川も公園もある都市部なら嘴細も暮らしていけるようだ。
吾輩と違い、嘴細はゴミにそれほど執着しないようだ。吾輩が高所から見下ろして餌を探すのに対し、嘴細は地面を這いずり回り,河川や草地の中の餌を探す。吾輩はよく群れを成し、声を出し合って餌をあさる。烏合の衆という失礼な表現もあるが、認知神経科学者によると、烏は姿と声を対応付けた「個体認知に基づく社会」を築いているという。

水浴びをするハシブトガラス(相模原市立博物館HPより)
烏の行水ともいうが、我々は水浴びや砂浴び後に羽繕いをし、寄生虫を取り除く。行水だけで短いと言ってほしくはない。
ほかに、深山(みやま)烏(がらす)や鵲(かささぎ)も我々の近縁である。深山烏は冬に中国やロシアから九州に越冬に来る渡り鳥だ。嘴細と姿や大きさが似ている。1980年頃までは西日本だけに越冬に来ていたが、最近では全国に越冬地を広げている。人間たちは鶴の越冬地が拡大することを期待しているようだが、鶴は九州の出水という越冬地にこだわりがあるようだ。
鵲は韓国語でカッチ、佐賀県ではカチガラスともよばれる。もともと日本にはいなかったようで、万葉集にカササギは登場しないらしい。ただし、日本書紀には聖徳太子の時代に「鵲」を新羅から持ち帰った記録があるという。
佐賀県の鵲は豊臣秀吉の朝鮮侵略時代に日本に輸入されたらしい。江戸時代を経て1923年に佐賀県から福岡県にかけて「カササギ生息地」が天然記念物として保護され、筑紫平野に広く分布している。北海道でも見られるようになりつつある。
烏(からす)という漢字は鳥(とり)に似ている。ある漢和辞典によると、鳥という漢字にあって烏にない横棒は目を表し、吾輩は全身黒くて目がどこにあるかわからないので、烏は横棒が1つ足りないのだという。ただし、甲骨文字や西周時代の字体では鳥にも目がなく、烏とは別の字体だった。秦の時代の小篆という漢字から、鳥と烏は横棒一つの差になったようだ。ちなみに「嗚(お)」咽(えつ)は「鳴」と字が違い、前者の旁は烏である。
一、 烏の記憶力は類人猿並み
吾輩の記憶力には定評がある。木の実などの餌を100か所近くに分けて土に隠し、必要に応じて後から食べる。他の烏の隠した餌を盗む不届きな烏もいるが、見つからぬようカラの隠し場所を偽装するなど工夫も凝らす。動物学者は、我々の記憶力を類人猿並みと評価している。
日本語で記憶力の弱い人のことを「鳥頭(とりあたま)」というらしいが、見当違いも甚だしい。韓国語でも似たような意味で鶏頭(닭대가리)(たくてがり)というらしい。鶏の脳は確かに小さいが、吾輩の脳は体重当たり鶏の約5倍である。「脳重」と「体重の2/3乗」の比を脳化指数という。鶏は確かに「猫の額」の四半分と指数が小さいが、烏は犬より指数がやや高いという。そもそも、脳重は必ずしも知能を反映しない。むしろ脳細胞数のほうが重要だろう。鶏も決して記憶力が低いわけではない。
吾輩に言わせれば、餌の隠し場の記憶力に関しては、人より秀でていると思う。動物学者は、かたくなに人自身と烏との記憶力の比較実験から逃げている。人間どもの「神経衰弱」というカードゲームを見ていると、吾輩は自分の記憶力に自信を持ち、人間どもを見下す勇気が湧いてくる。
深山烏が1、2、3、4までの数の概念を答えられたとする研究成果がある。しかし、それ以上の数の概念を持っているわけではないし、たくさんの餌の隠し場所を「数えて」いるわけではない。それに対して、人間はそれぞれの鳥や人の姿かたちは忘れても、はるかに多くの数を数えることができる。

人を襲うカラス(FNNプライムオンラインより)
餌の隠し場だけでなく、吾輩は人間を「個体識別」する。その記憶は半年間持続すると動物学者は言う。我々に悪さをする悪人の姿を記憶し、反撃する同志もいる。吾輩の嘴と爪は、丸腰の人間よりは遥かに強力だ。吾輩は空を飛び、滑空しながら人の頭を襲うことができる。人間どもは、昨日と今日の烏が同じ個体かどうか知る由もないだろう。
都市の家庭ゴミの回収場所は、都市に進出した吾輩の主要な餌場である。朝ゴミが出されてから、吾輩とゴミ回収車の早い者勝ちだ。しかし、人間は知恵がなく、回収車が来る直前にゴミを出すとは限らない。夜のうちにゴミを出すのはご法度である。中には吾輩が傍で待っているのを知りながら、ゴミを杜撰に出す「味方」もいる。

(生ごみをあさるカラス/東京都内)
昔から、人間たちは家庭ゴミ対策に悩んできた。福岡市では、ゴミを夜中に回収している。我々は昼行性なので、かの地ではゴミをあされない。代わりに夜も行動できる猫がゴミをあさるかもしれない。ただし、夜間回収のきっかけは烏対策ではないらしい。北海道では頑丈な金属製の檻の中にゴミを入れるところがある。ポリバケツでも、単に蓋を被せただけならば、吾輩はたやすく蓋を開けることができる。
我々は雑食である。鳶も含む猛禽はタカ目に属するが我々はスズメ目である。隼(はやぶさ)も猛禽だが、ハヤブサ目はどちらかといえば鷹(たか)より我々に近い。いずれにしても、系統分類が異なるものの、我々は猛禽に近い生態を進化させてきた。我々のライバルはタカ目の鳶である。我々は群れを成す点で彼らに勝り、鳶を蹴散らす戦果を各地で挙げている。日本の諺では「鳶に油揚げをさらわれる」というが、吾輩も油断している人間の手からサンドイッチを頂いたことがある。背後から滑空し、人間にけがをさせずに食い物だけをかすめ取る技術は鳶に負けない。これも我々の人間への温情である。
鵜と同様に、多くの日本人は我々を食料とはみなしていない。もっとも、長野県ではカラス田楽という伝統食があったらしい。今でも食べようとする試みはいくつかあるが、それほど普及しないだろう。けしからぬことだが、中国や韓国では我々を漢方薬として利用しているという。
二、 我々も絶滅危惧種か
意外と、簡単な折り畳み式の網のケージに入れることで、ゴミあさりはかなり阻まれてしまった。結果として、巣落とし、捕獲小屋を使った捕獲、餌の減少、鳥インフルエンザの感染などにより、都市部では我々の数が目に見えて減ってきた。ただし、絶滅危惧種になったわけではない。
我々は、もともと人間社会に依存せず、野生で生きていた。今でも郊外や山間部にも住んでいる。都市部では減ったかもしれないが、全体として絶滅の危機にはない。
意外なことに、蒼鷹(オオタカ)も我々の後を追うように都市部に参入してきた。一時期、オオタカは絶滅が危惧され、「種の保存法」で保護されてきたが、近年個体数が回復し、2017年に種の保存法の指定を外れた、日本では今のところ唯一の例となった。今でも準絶滅危惧種として、環境影響評価ではオオタカへの影響に配慮しているが、我々への影響も配慮してもらいたい。人間たちは不公平である。
米国の国鳥である白頭鷲(はくとうわし)は1997年までに米国本土全州で危急種に格下げされた。日本のオオタカより一足早い措置だったが、日本のオオタカが種の保存法から外れるときはかなりの反対運動があったらしい。米国では、いつまでも絶滅危惧種のままにしておく方が危うい。成果の出ない保護運動をしていると思われる方が、篤志家の寄付が得られにくいようである。
鹿や川鵜と同様、我々烏も人間に大量に駆除されてきた。特に、コロナ禍の時代に餌としていたゴミが減ったという。吾輩はゴミだけでなく鼠も食べる。しかし、都会に鼠が増えているのは我々のせいではなかろう。
数を減らしているという点では、雀(スズメ)の方が心配だ。かつての1~2割程度しかいないという推定もある。彼らの主要な餌場である水田、空地、草原などが減り、巣場所としての樹洞や木造建築が減ったこと、そして彼らを襲う猛禽や我々が増えたことも減らした原因の一つかもしれないという。我々のためにも、雀の餌場や棲み処を減らさないでいただきたい。
かように、我々は依然として元気である。我々の絶滅の心配や駆除を望む前に、まず、吾輩の記憶力を見習うことを勧める。この前ゴミ回収場で吾輩を追い払おうとした輩のことを、吾輩はしっかり憶えている。
[謝辞]原稿執筆にあたり、東京大学の樋口広芳名誉教授、北海道教育大学の三上修教授、北海道立総合研究機構の玉田克巳博士、酪農学園大学の森さやか准教授の助言を参考にしました。
また、原稿執筆にあたり、参考とした情報を以下の個人サイト
https://ecorisk.web.fc2.com/FACTA-Froricking-Animals.html
に掲載しています。
【編集部より】本連載は不定期に掲載します。