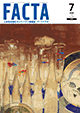「書かざる記者」は沈黙の共犯者だ!
「文春にはタレコミがあったからできる」という人たちに裏付ける手間と熱意がわかるか。
2020年7月号
DEEP
[特別寄稿]
by
清武英利
(ノンフィクション作家)

不屈の記者魂がスクープを生む(『週刊文春』5月28日号より)
後輩が読売新聞記者を辞めて、新しい名刺を作った。肩書に「独立記者」と印字されている。これからはどこにも身を売らずに、自由に物を書いていくというのだろう。そんなに肩ひじ張らなくても、と思ったが、ただフリー記者と記さないところに、彼の矜持があるような気がした。
いつまでもその気持ちで書き続けてほしい、と私は願った。
数年前の名刺のことを思い出したのは、東京高検の黒川弘務検事長の賭けマージャン問題で、 「書かざる記者」の存在を突き付けられたからである。黒川検事長と雀卓を囲んでいた産経新聞の二人の司法クラブ記者と、朝日新聞の元司法記者のことだけを言っているのではない。大組織の中に居て、読者が求めている時に、求められていることを書かない、記者の群れのことを記している。
記者は書いた記事が全て
週刊文春の報道で驚いたことはたくさんあるが、その一つは出版社を含む、意外に多くの記者たちが黒川検事長と交遊していて、「秘密主義の権化みたいな検察庁」(検察記者だった魚住昭氏)の世界を描かなかったことである。
法務・検察という最強の権力組織は絶えずチェックされ続けなければならない聖域である。その№2だった黒川検事長は、以前から安倍政権に近いと言われてきた。それは具体的にどういうことなのか。対する検事総長や検事たちは何を考えているのか。そもそも検察はなぜ近年、疑獄事件を摘発できなくなったのか――。
検察庁という組織の全体像と検察人脈を伝える長期連載やルポルタージュが、これほど求められた時期はなかったのではないか。だが、今年1月に黒川検事長の定年延長が閣議決定されても、検察官の定年を延長する「検察庁法改正案」が強い批判を浴びても、SNS上に「#検察庁法改正案に抗議します」という投稿があふれても、なお断片情報以外は書かれなかった。
書くことは、検察幹部や検事たちと日常的に接しているクラブ記者には、(気概さえあれば)可能なことである。文春報道の後、「実は俺も黒川を知っていた」というマスコミ人が次々に現れて、(なあんだ)と私は呆れてしまった。聖域の実態を伝えるのが仕事なのに、同化して「沈黙の共犯関係」に陥った人が実に多い。政治記者もその誹りを免れない。
警視庁記者クラブに、「それ、書いちゃいなよ」と口癖のように言うキャップがいた。捜査途上で書いたり内幕に触れたりすると、圧力をかけられるだけでなく、取材源をつぶされかねない。私はこの先輩が苦手だったが、熱意に引っ張られて記事の量は格段に増えた。対照的に司法記者クラブには「引き付けて書け」と一瞬の特ダネに賭けるキャップがいた。こちらは当然のように記事の総量は減る。取材源にも上司にも配慮する人だったが、読者の「知りたい」という欲求に応えたのは、書きにくいことでもこねくり回して書いた前者だった。
記者は掲載された記事が全てだ。そして、その記者がいなければ明らかにならなかっただろう記事のために存在している。明日になれば当局や企業が発表するような記事は本当の特ダネではない。当局との信頼関係や幹部と秘密を共有したことよりも、現れた記事によって記者は評価されなければならないはずだ。今回、袋叩きにあっている3人も口を拭ったりせずに、ぜひ再びペンを執ってほしい。痛みや反省とともに、黒川問題と検察の裏面を書けるのは彼らだし、産経新聞社によると、記者たちの行為は仕事らしいから、いつか活字になるのだろう。
私はかつて、ルポルタージュ『ベトナム戦記』(朝日文庫)を読んで、口拭う記者だけにはなるまいと誓った。ベトナムには、太平洋戦争終結の後も様々な事情から現地に残留して戦った元日本人兵士たちがいた。作家の開高健は彼ら日本人残留兵士の悲運と怒りを、こんな言葉で代弁している。
<“欧米列強の桎梏よりアジア同胞を解放する”という日本のスローガンは当間(元俊)氏ら無名の日本兵士によってのみ真に信じられ、遂行された。(中略)スローガンを美しく壮大な言葉で書きまくり、しゃべりまくった将軍たちや、高級将校や、新聞記者、従軍文士どもはいちはやく日本へ逃げ帰って、ちゃっと口ぬぐい、知らん顔して新しい言葉、昨日白いといったことを今日黒いといってふたたび書きまくり、しゃべりまくって暮しはじめたのである>
現場に12人を動員
それにしても、文春の記者たちには、新聞記者が失いつつある調査報道への情熱を感じる。この1年の政界絡みのスクープだけをとっても次のようになる。
▽<厚労政務官(上野宏史衆院議員)口利き&暴言音声を公開する>昨年8月29日号の発売当日に政務官辞任▽<菅原一秀経産相「秘書給与ピンハネ」「有権者買収」を告発する>同10月17日号から三連発で経産相辞任▽<法務大臣夫婦のウグイス嬢「違法買収」>同11月7日号の発売日朝に河井法相が辞任▽<森友自殺財務省職員遺書全文公開「すべて佐川局長の指示です」>今年3月26日号▽<黒川検事長は接待賭けマージャン常習犯>5月28日号――。
新聞社でこれだけ抜かれれば編集局長はクビだ。これ以外にも<森田健作 台風被害の最中に「公用車で別荘」疑惑>や、<安倍首相補佐官と美人官僚が山中教授を「恫喝」した京都不倫出張>もあった。
甘利明経済再生相を金銭授受疑惑で辞任に追い込んだのも文春である。その時は文春よりも先に新聞社に情報提供が行われていたというのだから、長い間、新聞社で調査報道に携わった身としては歯ぎしりする思いだ。
文春は河井事件や黒川問題を報じるとき、現場に12人の記者、カメラマンを動員したという。「文春にはタレコミがあったからできる」という人たちがいるが、ここまで立て続けにスクープされると、そうではないことがわかってくる。つまり、タレコミや断片情報を五つのチーム(計三十数人)が手間をかけて裏付け、写真を撮り、一つ成功させることによって、「あそこなら受け止めてくれる」という信頼感につなげているように見える。それが新たな情報を呼び寄せている。それだけの手間と熱意を新聞社も投じてほしい。
ここまで書くと、「じゃあ、お前やってみろよ」という新聞社幹部や検察記者もいるかもしれないが、私はこう答えます。「いいですよ。仕事を棚上げしてでも、お手伝いしましょう」――。