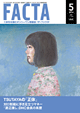検証・「石巻・大川小」津波悲劇
「最終報告書」が浮き彫りにしたハザードマップの過小評価と経験科学の域を出ぬ地震の科学の限界。
2014年5月号
DEEP
[特別寄稿]
by
纐纈一起
(東京大学地震研究所・教授)
2011年3月の東日本大震災の津波は数多くの悲劇を生み出してしまったが、北上川の河口にほど近い石巻市立大川小学校で起こったことはその中でも格別の悲劇と言わざるを得ない。当時の全校児童108名のうち、欠席・早退や家族に引き取られた等の約3割を除く76名が、教職員11名による学校管理下にあったにもかかわらず津波に巻き込まれ、72名が死亡・行方不明(教職員も10名が死亡)となった惨事である。
最終報告書は妥当なものか?
石巻市教育委員会が適切な事後対応できないでいる中、児童の遺族を中心に惨事の真相解明が強く叫ばれるようになり、文部科学省の主導・斡旋に基づいて事故検証委員会が12年12月に発足した。一年強の審議を経て、その最終報告書が去る3月1日に石巻市長に提出されている。なお、死亡・行方不明の児童を74名とする報道が多いが、報告書によればそのうち2名は欠席・早退の児童で学校管理下になかったと考えられるので、ここでは72名とした。
すでにいろいろな問題点が報道されている中で、この最終報告書は妥当なものなのかどうかを考えてみたい。筆者が問題点と指摘できるのは次の2点である。第一に、被災地の貴重な財源から多額の経費を使いながら、遺族が独自に調べられたこと以上の検証、特に地震発生から津波襲来までの51分間の検証がなかったこと。第二に、審議の過程で委員会を迷走させる発言や調査を行った委員・調査委員がいたことである。
第二の問題点はほとんど報道されることがなかったが、遺族との意見交換会や記者会見の議事録に垣間見える。実は、筆者が13年12月の第8回と翌1月の第9回検証委員会を傍聴するきっかけになったのは、この問題点を友人の研究者やジャーナリストから聞いたことであった。しかし、遺族からの厳しい指摘を受けて検証委員会は第7回において軌道修正を行っており、8・9回委員会には委員会を迷走させた者のうち調査委員はもう出席していなかったし、審議内容に強い違和感を抱くこともなかった。

最終報告書はこうした軌道修正を経てまとめられたものであるので、やはり強い違和感を抱かせるものにはなっていない。第一の問題点、検証結果に遺族による調査を超えるものがなかった点を別の見方をすれば、最終報告書は大筋で遺族が調べられたことに沿っており、一応の妥当性を持っているように見える。また、検証委員会が立ち上がった際の文科省の斡旋案は「検証委員会の目的は、事故の原因究明及び再発防止であることから、事故前後における関係当局や関係者の対応に関する法律上・行政上の責任追及は目的としない」(宮城県教育委員会第836回定例会会議録より)というものであったから、最終報告書が提言を重視し、責任の所在を明確にしなかったのは斡旋案に沿った結果と言える。
逆に言えば、遺族の当然の感情として責任の所在は明らかにしてほしいという気持ちがあったにもかかわらず、斡旋案を受け入れた遺族の建設的な対応は高く評価すべきであろう。その意味で、第1回委員会で「遺族の方の気持ち、亡くなられた方の気持ちに寄り添っていく」と所信表明して遺族の対応を評価した室委員長(神戸大名誉教授)には忸怩たる思いがあると想像される。
この惨事で多数の児童・教職員が死亡・行方不明となった要因に関して最終報告書は「避難開始に関する意思決定の時期が遅かったこと、及びその時期の避難であるにもかかわらず避難先として同校より標高は高いものの河川堤防に近い三角地帯を選択したことが、最大の直接的な要因である」と結論づけた。そして、その遅れの分析結果のひとつとして「過去に津波が来襲した記録がないことに加え、大川小学校がハザードマップの予想浸水域外になっており、津波災害時の指定避難所になっている」点が影響したと推定した。
背後にある科学の問題
石巻市の当時の津波ハザードマップは、宮城県防災会議地震対策等専門部会が04年に連動型宮城県沖地震を想定して作成したものをほぼそのまま踏襲していた。図の中でいろいろな色で塗りつぶされた部分が、想定地震による津波浸水が予想されている領域である。こげ茶色の5m以上から緑色の1m未満まで6段階で表されており、左下の大川小学校はこの領域から外れているだけでなく、それをもって津波災害時の避難所に指定されてしまっていることが見て取れる。
また、1933年の昭和三陸津波の浸水域も大川小学校には及んでいない。この大津波を上回るものとして知られている1896年の明治三陸津波では図面は残っていないものの、宮城県海嘯誌という公文書に「大川村は追波の河口に臨み又其湾に面し居るも沿海民家少なかりしを以て流失家屋僅かに一戸死亡亦一人に止まれり」(大川村は当時の河岸南側の名称)と書かれている。これだけでは大川小学校に明治三陸津波が及ばなかったとは言い切れないが、「大川村大字長面は海岸には凡十町餘の距離あるを以て市街地付近に於ては何等の被害なかりし」(十町は約1㎞)の記述と併せると、最終報告書の通り「過去に津波が来襲した記録がない」となろう。
図で示した東日本大震災時の津波の浸水高と比較すると、ハザードマップの推定がいかに過小評価かよくわかるが、ここに科学に関わる問題が潜んでいる。ハザードマップが作られた、前述の地震対策等専門部会による第三次地震被害想定では、国の地震調査委員会が発生確率の長期評価を発表していた地震のうち、もっとも確率が高く規模が大きい、マグニチュード(M)8連動型宮城県沖地震が想定地震として採用された。採用にあたっては、専門部会に参加していた数名の科学者も、科学的に妥当だと判断して同意したはずである。
ところが実際に地震が起こってみればM9の超巨大地震で、予想を絶する巨大津波となってしまったのである。直後に当時の阿部勝征・地震調査委員長が「4つの想定域が連動するとは想定できなかった。地震研究の限界だ」(正しくは4つではなく6つ)と述べたように、過小評価のハザードマップの背後には科学の想定外があった。地震の科学は依然として経験科学の域を出ず、東日本大地震災のような未経験の事象を事前に想定することは困難な状況にある。
ではどうしたらいいのか? 検証委員会の最終報告書は前述のように提言が重視され、24件もの提言が含まれているが、そのうち2件がこの問題に割かれている。
まず提言16では「市町村は、これまで作成した、又は今後作成するハザードマップについて、その作成過程を見直すとともに、地域の地勢や地形などに即して具体的に検証すること」と述べられている。しかし、これは少々ピント外れであり、問題の本質は地域の地勢や地形などといったローカルなところにあるのではない。おおもとの地震の想定という、もっと根源的な科学の問題がからんでいる。提言16はさらに「ハザードマップの内容が『安心情報』にならないよう、その正しい理解のための啓発と広報に努めること」と続くが、的確な地震の想定に基づいて津波を正しく予測できなければ、ハザードマップの内容が「安心情報」とならないようにはできない。
次の提言17では「専門家は、災害の危険性について住民が正しく理解できるよう、積極的な情報発信やコミュニケーションに努めること」と述べられている。しかし、専門家(科学者)が住民全体とコミュニケーションをとるなどあまりに非現実的であるから、これもピント外れと言わざるを得ない。コミュニケーションの問題は行政に任せ、ハザードマップの問題の解決や、行政が的確に動けるような情報提供に科学者は専念すべきであろう。
科学者はどうすべきなのか
未経験の地震を事前に想定してハザードマップを作成するという課題は、科学の「限界」への挑戦とも言える重い課題であり、その解決には長い道のりが必要である。しかし、地震国日本は、それでも地震災害の軽減のためにハザードマップを作らなければならないという状況にある。
そうした状況の中で科学者はどうすべきなのか。たとえば、科学者の常識的な感覚から導かれる平均的な想定地震だけでなく、情報・知見などを総動員して最大規模の地震を想定し、それを提示する必要があるだろう。東日本大震災以前のM8連動型宮城県沖地震は規模が大きなものとして選ばれたのであろうが、結果的に「平均的」な想定地震に過ぎなかった。今後必要となるのは、未経験な状態で東日本大震災のような「最大規模」の地震を想定することである。
そして、「平均的」や「最大規模」など、複数の想定地震ごとに提示されるハザードマップの中からどれを選ぶか、あるいはどう組み合わせるかなど、減災に向けた活用の仕方は科学者が決めるべきことではない。行政あるいは住民が直接、科学以外の要素(経済的・社会的状況など)も勘案して決めるべきことである。特に、避難所や避難場所の選定はそれ自体が重大であるだけでなく、大川小や、ここでは触れなかったが東松島・野蒜小の場合のように人々の避難行動に大きな心理的影響を与えるから、最大規模の想定地震に対するハザードマップに基づくべきである。