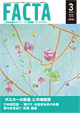「デフレ特効薬」は日銀法改正
テイラー・ルールを都合よく「厚化粧」する手前ミソ。その鉄面皮を剥ぐには独立性を限定すべし。
2010年3月号 BUSINESS [テイラー・ルール改竄]

カナダで開かれたG7で肩を並べる資格はあるか――(前列左から菅財務相、トレモンティ伊経済相、後列左からゼーリック世銀総裁、ストロスカーンIMF専任理事、白川日銀総裁、伊中央銀行ドラギ総裁)
AFP=Jiji
「いのちを、守りたい」
1月29日、鳩山由紀夫首相は施政方針演説で「いのち」という言葉を24回も口にした。国会中の答弁はたいがい官僚の作文の棒読みだが、施政方針演説は冒頭で行われ、首相の個性を一番出すことができる。
官邸ホームページの演説原稿では、見出しも含めると「いのち」が31カ所もある。この演説は、劇作家の平田オリザ氏が助言したものに鳩山首相が手を入れたようだ。官僚の筆でないことは一目で分かる。
ただ、皮肉にも「いのち」演説の3日前、警察庁は2009年の自殺者(暫定値)が3万2753人(08年比504人増)となり、12年連続で3万人を超えたと発表した。施政方針演説ではさすがに「いのちを守る社会の基盤として、自殺対策を強化するとともに……」と一言だけ触れている。
鳩山政権が本気で「いのち」を救おうとするなら、35兆円ともいわれるGDP(国内総生産)ギャップ(総需要と総供給の落差、「需給ギャップ」または「デフレギャップ」とも呼ぶ)を放置してはいけない。自殺は景気と密接な関係がある(37ページのグラフⅠ参照)。景気が悪くなると自殺者が増えるのだ。適切な財政・金融政策でGDPギャップを埋めれば、自殺者を5千人は救え、失業者も100万人救えるだろう。しかし政府も日銀もGDPギャップを放置している。これでは「いのち」は守れない。
日銀論文が使った「手品」
本誌2月号の記事(「日銀は『テイラーの公式』逸脱」)では、スタンフォード大学のジョン・テイラー教授が提唱した金融政策の「テイラー・ルール」を使って日銀の無策ぶりを論じたが、批判もあるようなので今号で反論しておきたい。
第一の批判は「テイラー・ルールは米国産なので日本に適用できない」というナイーブなものだ。
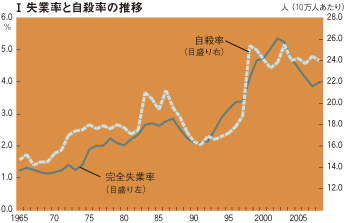
しかし、今よりは比較的ましな経済運営だった1990年代後半までは、日本にもテイラー・ルールがあてはまっていたのだ。また、現在の経済学は、動学的確率的一般均衡(Dynamic Stochastic General Equilibrium)というモデルを使っているが、一定の条件のもとで、最適金融政策としてテイラー・ルールと同種のものが導かれている。つまりテイラー・ルールは米国産だが、もう少し普遍的なのだ。
第二の批判は「テイラー・ルールでみても、日銀はそれなりに頑張っている」というものだ。これはちょっと手が込んでいて、根拠のひとつには日銀企画局が05年8月に公表した小田信之・永幡崇連名の共同論文「金融政策ルールと中央銀行の政策運営」(日銀レビュー)がある。
金融政策は日銀政策決定会合で決まるが、その事務局は企画局だ。実際の決定会合の議事録を読むと分かるが、企画局もかなり議論に加わって方向性を左右している。企画局が発行したテイラー・ルールに関するペーパーがこの論文である。彼らがどんな“手品”を使ったか、ここで暴いてさしあげよう。
論文に載っている「オリジナルのテイラー・ルールが示す日本の政策金利の例」(次ページのグラフⅢ)と「推定されたテイラー・ルールが示す日本の政策金利の例」(同グラフⅣ)を見てほしい。「現実のコールレート」と「テイラー・ルールから算出される政策金利」が、いかに乖離しているかが一目で分かる仕掛けだが、ここにマジックが隠れている。
グラフⅢは本誌1月号(「白川日銀は『デフレ誘導』」)に付けたグラフⅡとよく似ているが、「現実のコールレート」と「テイラー・ルールから算出される政策金利」の差が本誌より明らかに小さい。なぜか。
本誌を「オリジナル・テイラー・ルール」、日銀論文を「日銀流オリジナル・テイラー・ルール」と呼ぼう。「日銀流」は、本来のデータ(もちろん本誌は同じデータ)にかなり「お化粧」を施しているのに、オリジナルと称しているのが笑える。
「可変ルール」の予定調和
二つの「オリジナル」には違いが2点ある。第一点は、GDPギャップを算出するためには潜在GDPが必要だが、その計算方法が違う。本誌は内閣府のデータである。経済協力開発機構(OECD)など国際機関と同じ方法であり、資本・労働などから生産関数を推計し、失業がない状態という観点から潜在GDPを計算する(生産関数アプローチ)。
これに対し「日銀流」はHPフィルター(Hodrick-Prescott filter)という手法で潜在GDPを計算している(フィルター・アプローチ)。HPフィルターは、「現実のGDPは平均して一定の期間でみれば潜在GDPになる」という前提があり、簡単に計算できるので、学者の論文で多く用いられているが、現実的に妥当かどうかという議論がある。
またHPフィルターによる潜在GDPは、内閣府やOECDなどに比べてGDPギャップが小さくなる傾向がある。このためHPフィルターでみると、GDPギャップがないのになぜ失業が多いのか、なぜデフレになるのか――という素朴な疑問も湧く。ちなみに日銀は公式見解としては、潜在GDPを見るときには内閣府やOECDなどと同じ生産関数アプローチなのだが、この論文でそれを伏せているのは意図を感じる。
第二点は、均衡実質金利について、本誌は固定、「日銀流」は可変にしている。これは大きな「お化粧」だ。可変的な均衡実質金利を入れて「日銀流」による金融政策を行うのは、中央銀行が全知全能の神さながらに完璧に経済運営できると考えていることと同じだ。つまり、日銀が誘導している金利はほとんど均衡実質金利と変わらないと宣言しているようなものだ。日銀が誘導した金利は経済実態からみて適正だ、と主張するにひとしい“予定調和説”なのだ。
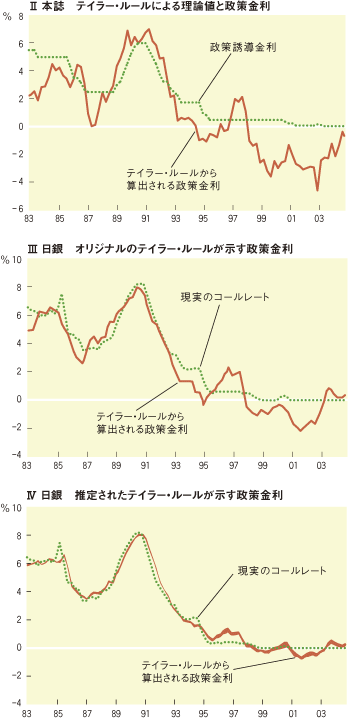
この二つの操作で、「日銀流」と現実金利の乖離は本誌より小さくなった。ただ、これだけお化粧を施しても、90年代後半以降はまだ乖離が残っているのだから笑える。
その上で日銀論文はさらに厚化粧して「オリジナル・テイラー・ルール」とは似ても似つかない「推定されたテイラー・ルール」という応用形を用意する。グラフⅣでは、実際の金利はこの応用形とほとんど一致する。これだけみれば、日銀はテイラー・ルールどおりに政策運営してきたと早合点する人も多いだろう。
「応用形」は、「日銀流オリジナル」に金利スムージングと可変のインフレ目標を加えている。実は可変的な均衡実質金利を導入した「日銀流オリジナル」でも、もうルールとはいえない。誰でも分かるのがルール。これは「その場その場でルールが変更になる」というルールなのだ。
さらに前期の金利を正しいと肯定的に考える「金利スムージング」や、可変のインフレ目標を入れるのだ。「ルール」自体がいかようにも変わり、現実の金利をほぼ100%説明できるに決まっている。「日銀流オリジナル」で第1次粉飾し、「応用形」で第2次粉飾するなど、芸が凝っているのには驚かされる。
なぜここまで厚化粧して日銀の行動を正当化したいのか。外部からその心理は窺いしれないが、企画局エリートにとっては組織防衛のために当然なのだろう。きっと本誌の「オリジナル・テイラー・ルール」に基づくデータも算出しているはずだが、出さないのはあまりにせこい。
大蔵省解体のすり替えで
日銀の歴史を振り返ると、さもありなんと思えてくる。今の日銀法は98年4月の施行だが、旧日銀法は「第一条 日本銀行ハ国家経済総力ノ適切ナル発揮ヲ図ル為……」とあるように、第2次大戦の国家総動員体制のもとで1942年に公布されたものだったため、98年の改正まで日銀の独立性はなかった。それが改正新法によって、たちどころに史上最強の独立性を手にしたのだ。
中央銀行の独立性とは「目標の独立性ではなく手段の独立性」というのが当時から世界の常識である。つまり、中央銀行の目標は、政府または政府と中央銀行が共同して設定するが、その目標をどのような手段で達成するかは中央銀行に委ねる――というものだ。ところが今の日銀法では、目標の独立性まで日銀に与えている。これが「史上最強の独立性」という意味だ。新日銀法とほぼ同時期に制定されたイングランド銀行法第12条には、目標は政府が設定すると明記してあり、新日銀法の異様さが際だっている。
なぜ日銀法に目標の独立性まで与えたのか。ひとつには新日銀法制定の際、独立性の意味はほとんど議論されなかったことがある。
新日銀法の議論は、96年7月、首相官邸に中央銀行研究会(座長は鳥居泰彦慶応大学塾長)が設けられて正式にスタートし、同年11月に研究会は当時の橋本龍太郎首相に答申を提出した。それを受けて大蔵省の金融制度調査会の小委員会が実務的な議論を行い、97年2月、調査会は答申を出した。その翌3月に政府が新日銀法案を国会に提出し、6月に成立した。長い時間をかけたようだが、実はただ漠然と日銀には独立性が必要という浅い議論しかされなかったのである。
その根本的な原因は、立案関係者に中央銀行論の専門家がいなかったことにある。政府内で新日銀法の議論が始まるきっかけも不幸であった。橋本政権発足早々の96年3月ごろ、急に与党3党(自民党、社民党、新党さきがけ)による「大蔵省改革問題プロジェクトチーム」で、日銀法の議論が盛り上がったのだ。このチームは、名称からわかるが、95年春以降相次いで起きた大蔵省幹部の接待事件、大和銀行ニューヨーク支店の巨額損失事件、住宅金融専門会社(住専)問題など、大蔵省の不祥事・不手際の火消しを狙って、与党3党が発足させたものだ。
ところが、議論は紆余曲折を経る。財政政策と金融行政の両方を一役所で担当するのは権限が集中しすぎでよくないとされ、大蔵省の金融行政担当部分(銀行局と証券局)を切り離すことになった。一口に「財金分離」というが、財政と金融の分離という場合、金融は「金融行政」ではなく「金融政策」というのが一般的だった。だから「財金分離」という言葉を逆手にとって、大蔵省解体を回避し、組織維持を図るために新日銀法に議論がすり替えられた公算が大きい。しかし大蔵省の不祥事問題は延々と火の手が収まらず、「財金分離」も、財政政策と金融政策の分離や新日銀法制定ではとどまらなくなり、財政と金融行政を分離して金融監督庁を設置することになった。
こうした経緯があるので、新日銀法の制定の議論では、日銀の独立性は所与のものとして議論の対象にならなかった。議論のスタートで「財金分離」と言う以上、財政と金融政策を分離するのは、日銀の独立性と表裏一体になるからだ。そこでは「中央銀行の独立性には目標の独立性と手段の独立性があって、目標の独立性を日銀に与えるべきではない」という精緻な議論をすべきだった。それが世界の流れと関係者には分かっていたとしても、マスコミを恐れて議論できなかったのかもしれない。
日銀は黙っていた。かくて新日銀法第4条は「日本銀行は(中略)常に政府と連絡を密にし、十分な意思疎通を図らなければならない」と規定しているだけで、日銀が目標を設定することを前提に、政府と連絡すればいいという条文になっている。
勝利した日銀内の高揚感は、10年後に公開された日銀政策決定会合の議事録でわかる。それまで大蔵省からの事実上の指示で金利が決まっていたのが、日銀政策決定会合で名実ともに決められるのだから当然だ。財務省副大臣などがオブザーバー出席しても、評決の票がない。
レベルの低い床屋談義
ただ議論のレベルはあきれるほど低い。「金利が低いのは困る」とだけ主張する審議委員もいた。スーパーな独立性を与えられたのに、明確な政策目標を設定せずに、漫然と景気状況を述べるだけになっている。
典型は99年9月21日。金融政策と為替政策で議論しているが、「日銀は物価を安定させることが目標だと明確にしていないので、為替のために金融政策を使うべきでないが、世論が心配だ」とか、「いや、世論に屈するのは問題だ」とか、混乱した議論になる。「デフレ時でも日銀は長期国債の買いオペは一切ダメ」という“日銀DNA”丸出しの意見を平気で言う審議委員も出てくる。ある報道で日銀は10年前も同じように悩んでいたというが、10年たっても相変わらず明確な物価目標を明かさず、床屋談議しているだけだ。
テイラー・ルールの改竄もこの“独善”が苗床なのだ。白川方明総裁のもとで独善度は強まるばかり。どれだけ金融政策を誤っても、総裁の責任を問うことはおろか、更迭することもできないのだ。今の白川総裁に日銀内で異を唱える声はない。財務相は素人同然の菅直人副総理であり、国民は投票で選ばれたわけでもない「デフレターゲティング」総裁にあと3年も我慢しなければならない。
打開するには、日銀法をもう一度改正するしかない。日銀は激しく抵抗するだろうが、その独立性を制限すべきだ。政府が日銀に対し物価目標を設定できる代わりに、政府は目標を与えたら、何も言わず日銀の手段の独立性を確保すべきだ。それが世界標準の中央銀行だ。でないと「デフレターゲティング」日銀から、国民の「いのち」は守れない。