出版界真っ青「ブック検索」の黒船
あのグーグルが「デジタル版権」を牛耳ろうと全文スキャン。米国の訴訟和解で日本も踏み絵。
2009年5月号 BUSINESS
米グーグルの言動に世界中の著者と出版界が困惑している。発端となったのは、日本では2月24日に読売新聞や朝日新聞などに掲載された「グーグルブック検索和解」に関する告知広告。グーグルと著作権者の訴訟による争いが和解に至ったことを告げていたが、迷路のように入り組んだ文章は翻訳調の悪文もあって一読しただけでは理解できない。
だが、ここに至る経緯とその背景を知れば、「日本の書籍がグーグルのサイトで全文読めるようになる可能性」に誰もが驚くだろう。出版物のデジタル版権を牛耳りたいという、グーグルの見え隠れする野心を知り、青くなるかもしれない。
告知を要約するとこうなる。「米国の著作権に関する集団訴訟で権利者代表とグーグルが和解をした。その影響は著作権条約を締結しているすべての国の権利者にも及ぶので、この和解に賛成か反対か態度を決めろ」。なぜ米国での訴訟の和解が他国の書籍の権利者にまで影響するのか。それを理解するには、一連の動きを知る必要がある。
アマゾンともリンク
グーグルは2005年、提携する図書館や出版社から提供を受けた本をスキャンし、ネットで検索・全文または一部閲覧を可能にするブック検索プロジェクトを開始した。これに反発したのが米作家団体。図書館の蔵書とはいえ著作権が現存する本も多数ある。それをデジタル化して一部分とはいえネットで閲覧可能にするなどもってのほか、というわけだ。作家団体は、グーグルを著作権侵害で提訴した。しかし、グーグルは「フェアユース(公正利用)」を主張し対立。フェアユースとは、原作品の市場を奪わないなど権利に配慮した利用であれば、権利者の許諾を得ずに著作物を利用できるという米国の著作権法に定められたルールである。ブック検索を利用するとわかるが、著作権の発生する書籍の場合、中身の全文検索は可能でも、ネットで閲覧できるのは、検索キーワードに関係したページとその周辺ページだけ。グーグルが言うフェアユースの根拠だ。おまけに、ブック検索には、アマゾンなどネット書店の該当ページへの直リンクも張ってある。「売り上げに貢献している」とアピールする意味もあるのだろう。
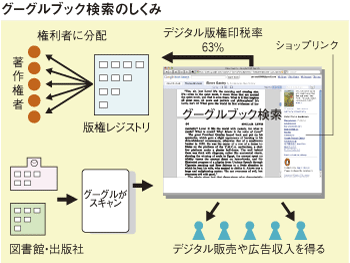
実際、“死に筋”本がブック検索で発掘され、ベストセラーになった例もある。ただ、旧来メディアの権利者からすると「グーグルの好きにはさせないぞ」という感情的な反発もあり、訴訟騒ぎに発展していた。
今回の和解により、グーグルは権利の発生する刊行物(新聞や雑誌は除く)であっても個別に許諾を得ることなく、その全文をブック検索に収録することが合法化される。デジタル情報の販売や検索結果に表示する広告掲載など、ネットビジネスへの利用も正当化され、収入の63%を後述する「版権レジストリ」という管理団体を通じて権利者に還元するとしている。ただし、現段階では、米国のブック検索に限定され、日本からは利用できない。
それにしても、米国での訴訟の和解内容がなぜ日本を含めた他国の書籍やその権利者にまで及ぶのか。これには、米国流の集団訴訟の仕組みと著作権の国際協定「ベルヌ条約」が大きく関係する。今回、米作家団体は、「クラスアクション」と呼ばれる方式で提訴した。多数被害者の利害を代弁し個別の委任を必要としないこの方式により、作家団体が権利者の声を代表して和解する形になった(離脱は自由)。
それだけなら米国内の話だが、ベルヌ条約の規定により、米国の和解が他国の権利者にまで影響する。ベルヌ条約は加盟国の著作権を相互に保護しているため、日本の作家でも自著が米国内で流通していれば、米国における自著の権利は今回の和解の対象になる。つまり、スキャンされてグーグルのネットビジネスに利用されても和解から離脱しない限り文句は言えないわけだ。
もうひとつ大きな問題がある。米国内で「市販されていない」または「絶版」と判断された刊行物については、米国での権利が発生しないものとして、グーグルが自由に利用できる。つまりネットに全文公開される可能性がある。おそらく日本のほとんどの著作物が米国では「権利なし」の扱いになると見られ、「米国でのことだが、自著がネットで公開可能な状況に置かれるのは、気持ち悪い」という声も多い。
デジタル印税率は63%
権利者には期限つきで大きく三つの選択肢が与えられている。
①何もアクションを起こさない。この場合、09年5月5日時点で自動的に和解に参加したことになり、自著がスキャンされる可能性がある。
②和解専用サイトにユーザー登録(和解への参加を意味する)し自著をスキャン対象から除外する。
③和解からの離脱を意思表明する。あるいはグーグルを訴える。この場合、スキャンの除外やデジタル化報酬等の受け取りなどができなくなる。
なんと狡猾なやり方か。黙っていればグーグルの思うつぼ。権利行使のために書籍を除外するには和解に与するしかなく、異議を申し立てると除外ができないばかりか将来のデジタル化報酬を放棄することになる。デジタル出版台頭の潮流に抗えないと悟った米作家団体は、和解に持ち込むことでグーグルの潤沢な資金を利用して「版権レジストリ」を立ち上げ、デジタル版権管理の仕組みを構築することにしたと見られる。現にグーグルは、設立・運営費用として3450万ドル(約34億円)を負担する。
版権レジストリとは、書籍のデジタル版権管理団体のこと。音楽でいうJASRAC(日本音楽著作権協会)のような位置づけだ。デジタル版権管理の仕組みを世界に先駆けて作ることで、この分野をリードしようとしていると見られる。ネットでの検索や音楽・動画の市場に続き、デジタル書籍でも米国に牛耳られるのだろうか。
今回、デジタルの印税率63%という前例も作られてしまった。定価の10%前後という書籍印税率がベースになっている日本からすると「未曾有の数字」(出版社幹部)だ。
版権レジストリについては、米国内にも「国会図書館など官がやるべき仕事という批判もある」(国際大学GLOCOM客員教授・米国弁護士の城所岩生氏)というが、何ごとにもスピードが求められるネットビジネスの世界だけに、「大きな見返りが期待できる分野は、リーガルリスクを取ってでも、さっさとビジネス化して機先を制する」(城所氏)のがグーグルのやり方である。
グーグルが日本のブック検索に米国と同様の仕組みを持ち込むことは現時点では考えにくい。日本にはフェアユースの規定がないからだ。だが、政府の知的財産戦略本部がまとめた「知的財産推進計画2008」では、「フェアユース規定を導入することが適当」としている。既存の権利団体の抵抗が激しく、骨抜きになる可能性も否定できないが、一方で、著作者からするとグーグルがスキャンしてくれることは、基本的に歓迎なはず。ブック検索による露出増が期待でき、デジタル出版で印税が入る可能性もあるからだ。多寡はあるにせよ収入チャネルが既存流通からデジタルにシフトするだけだ。
グーグルの進出を嫌うのは古い体質の業界なのだ。グーグルに不満を漏らすだけでなく、米作家団体のようにネット企業のパワーを巧みに利用して対抗するスキームを創り出す意気込みはないのか。言葉と文化の壁に守られた出版界にも「黒船」が迫ろうとしている。



