原発30キロ圏「内部被曝」の実態
チェルノブイリと異なり急速に低下するセシウム検出率。試行錯誤の末、見えてきた「放射線と共生する方法」。
2013年8月号
DEEP [特別寄稿]
by 上 昌広(東京大学医科学研究所特任教授)

東日本大震災から2年4カ月が経過した。縁あって、筆者は福島県の医療支援を続けている。東京と福島を往復して感じるのは、被曝に対する温度差だ。
福島では、現在も地道な努力が続けられている。その中心は、相馬市、南相馬市などの地方自治体と、ひらた中央病院(平田村)、ときわ会常磐病院(いわき市)などの民間病院だ。彼らの活動により、「原発事故により福島は汚染されたが、やり方次第では、被曝を避け、従来通りの生活を続けられる」(南相馬市立総合病院・坪倉正治医師)ことが明らかとなった。
南相馬市立総合病院の「実証データ」
被曝は外部被曝と内部被曝に大別される。前者は、原発事故により環境中に放出された放射性物質からの放射線を浴びることだ。
福島第一原発事故でも、原発作業員や原発周囲の高汚染地域では、外部被曝が問題となり得る。
ただ、福島の場合、一部の地域を除いて、外部被曝は問題となっていない。避難や除染作業が進んでいることもあるが、雨や雪が大地に降り積もった放射性物質を、川や海へと洗い流している影響も大きい。
今年4月、政府は、年間被曝線量20ミリシーベルト以下の地域を、「避難指示解除準備区域」に指定し、住民が帰還するための環境整備を進める方針を示した。この政策は、外部被曝が着実に改善していることに基づいている。
では、住民は何を心配しているのだろうか。それは、内部被曝である。内部被曝とは、体内に放射性物質を吸収してしまうことだ。特に、子どもに対する長期的影響は不明であり、今でも「福島の子どもは、即刻県外に避難させるべき」と主張する医師もいる。
ところが、実態は、そう単純ではない。半減期が8日と短い放射性ヨウ素の影響は、今となっては検証不可能だが、放射性セシウムによる内部被曝については、多くの情報が蓄積しつつある。
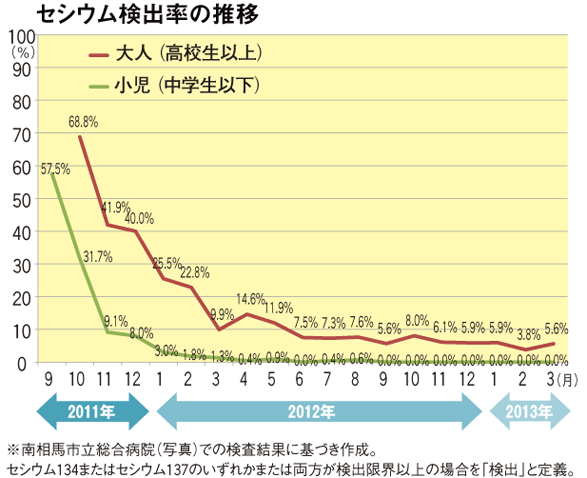
結論から言うと、福島県の各地でホールボディーカウンター(WBC)を用いた内部被曝検査が行われているが、殆どの住民では検出されないのだ。例えば、南相馬市立総合病院で、昨年10月から今年3月までに検査を受けた成人2865人のうち、放射性セシウムを検出したのは、75人(2・6%)だった。陽性者の殆どが高齢男性で、小児184人に限れば、全員が陰性である。
そもそも、自然な状態でも体内には体重1キロ当たり50ベクレル程度の放射性物質がある。放射性カリウムが主な原因である。この程度の内部被曝は生理現象ということも可能だ。
ホールボディーカウンターは、カリウムとセシウムの線量を区別することができる。専門家が要注意と見なすのは、カリウムに加え、体重1キロ当たり20ベクレル以上のセシウムによる内部被曝がある場合だ。このような住民は、わずかに3人(0・1%)に過ぎない。この傾向は、福島県内の他地域でも同じだ。最近の発表によると、体重1キロ当たり20ベクレル以上の放射性セシウムを検出したのは、相馬市では5082人中4人(0・1%)、平田村では8200人中4人(0・0%)である。
チェルノブイリと異なる「食糧事情」
放射性セシウムを吸収した場合、年齢や性別によって異なるが、数カ月から1年程度で体内から排出される。例えば、南相馬市立総合病院で内部被曝検査が始まった2011年10月には、69%の住民(大人)で内部被曝が確認された。原発事故後に、放射性物質で汚染された粉塵を吸入したためだ。その後、内部被曝の検出率は直線的に低下し、原発事故から1年後の12年3月には10%となった。この状況は、チェルノブイリとは対照的だ。彼の地では、原発事故から10年が経っても、住民の内部被曝は、平均して、体重1キロ当たり40ベクレルを超えていた。この事実は、チェルノブイリの住民が、慢性的に放射性物質を吸収していたことを意味する。つまり、汚染された食べ物や水を摂取していたことになる。
ただ、彼らが単に無知だったというわけではない。ウクライナの放射線専門家は、「当時はソ連崩壊の混乱期で、食糧難でした。放射性物質に汚染されていると分かっていても、食べざるを得ませんでした」と言う。チェルノブイリと比較した場合、福島の内部被曝対策は成功している。その理由について、前述の坪倉医師は「食事対策に尽きる」と明言する。
食品の放射線対策は地元住民の関心事だ。東京大学医学部の杉本亜美奈氏が行った、2865人の南相馬市民を対象とした調査によれば、肉・魚・果物・牛乳に関しては、地元のものを食べている人は殆どいない。米と野菜に関しても、地元で採れたものを食べているのは、全体の2割程度だ。
震災前、この地域は第1次産業が盛んで、「魚や米は買ったことがないという人は珍しくなかった」(地元住民)と言う。ところが、震災後は、もっぱら、スーパーで売っている他県産の食材を食べている。
実は、福島県の内部被曝対策の成功の原因は、ここにある。前述のウクライナの専門家は「こんなことが出来るのは、日本は食糧事情が良く、流通網が発達しているため」と言う。いかに大地や海が汚染されようとも、その地域の食材を避ければ、内部被曝することはない。
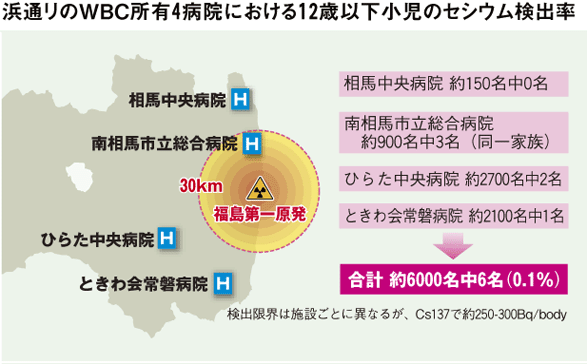
原発事故対応の不手際を批判されることが多い前・民主党政権だが、食品対策に関しては評価すべき点がある。特に、原発事故後、警戒区域の牛や豚などの家畜を殺処分したのは、内部被曝対策という観点からは合理的だった。これは、チェルノブイリ原発事故直後、汚染された牛乳を介して、多くの子どもたちが、放射性ヨウ素を吸収し、数年後に甲状腺癌を発症したこととは対照的だ。ただ、これもやむを得なかった。もし、チェルノブイリで厳密な食品規制をかければ、大量の餓死者を生みだした可能性が高い。
内部被曝対策を語る上で、住民と自治体、さらに専門家が一体となった努力を忘れるわけにはいかない。
例えば、地元の食材を食べる際には、あらかじめ自治体や専門家が実施している食品検査を受けることが多い。特に、土壌汚染が深刻な相馬市玉野地区には、東京農大の専門家が常駐し、検査を担当している。このような活動を通じ、汚染された食材を摂取するリスクを下げている。
福島の内部被曝対策は大成功
小児への対策は、さらに慎重だ。南相馬市の学校給食では、食材の事前チェックは勿論、1週間分の給食を貯めておいて、まとめて放射線を測定している。このダブルチェック体制は、早野龍五・東大大学院理学系研究科教授の提言を受けて始めたものだ。
飲用水に関しても神経を使っている。それは、この地域が、放射性物質が降り注いだ阿武隈山系の地下水を水源とするからである。幸いなことに、震災以降、地元自治体は頻回に検査しているが、水源、および水道水から放射性物質が検出されたことはない。南相馬市の住民の約6割が水道水を飲んでいるが、問題は起きていない。
相馬市や南相馬市の経験は、原発周辺地域にも伝わり、住民の帰還を後押ししている。例えば、原発事故後、全村避難を余儀なくされた川内村の場合、震災前の住民2900人のうち、約500人が既に帰村している。このうち、149人が内部被曝検査を受けたが、体重1キロ当たり20ベクレル以上の放射性セシウムを認めた人はいなかった。帰村者の中には、地元産の米や野菜を食べている人が多い。厳格な食品検査と、後述する汚染しやすい食物を特定し、それを避けることで内部被曝を減らすことができる。
福島の内部被曝対策は、現時点までは大成功と言っていい。チェルノブイリとは、比較にならない。ただ、全く問題がないわけではない。前述の坪倉医師は「ごく稀に、桁違いに内部被曝している人がいます」と言う。坪倉医師が経験した最高値は、70歳男性の体重1キロ当たり約400ベクレルだ。チェルノブイリの内部被曝の平均の約10倍で、野生のイノシシに近い。この老人の好物はキノコで、原発事故後も自生するキノコを食べていたという。そのキノコの放射線量を測定したところ、1キロ当たり14万ベクレルであった。むべなるかなだ。
実は、福島の食材が一律に汚染されているわけではない。特に高いのは、イノシシやキジなどの獣肉、アイナメなどの底魚、スダチなどの柑橘類である。一方、根菜類が汚染されることは珍しい。チェルノブイリの研究者が「95%の内部被曝は、特定の食品に由来する」と報告したが、この状況は福島でも変わらない。逆に言えば、食材に気をつければ、地元産の食材を食べても内部被曝は問題とならない可能性が高い。
前述の老人は、近所の人に誘われて、たまたま内部被曝検査を受診した。検査結果を聞いて、大いにショックを受けたという。数カ月後に再検査したところ、内部被曝は改善していた。福島の問題は、内部被曝に無関心な住民が一定の割合で存在し、彼らが検査を受けていないことだ。仮に人口の1%だとしても、県内では1万人以上に相当する。公衆衛生上、ゆゆしき問題である。
内部被曝対策の最大の敵は無関心である。問題は、このような老人だけではない。無関心は一般住民にも拡大しつつある。その証左に、震災から時が経つにつれ、内部被曝検査を受診する住民の数が急速に低下している。南相馬市立総合病院の場合、ピークの12年1月には1カ月で約1800人の住民が検査を受けたが、13年に入り、その数は200人程度に減った。
この状況はチェルノブイリと酷似する。チェルノブイリで内部被曝がピークに達したのは、原発事故から12年が経過した1998年である。現地の専門家は「原発事故から時間が経ち、油断したのです。一気に悪化しました」と言う。チェルノブイリでは、この経験を糧に、放射線対策を立法化し、厳密な放射線管理体制を継続している。
除染より教育や医療への投資を!
内部被曝対策は長期戦だ。関係者が一体となって努力するしかない。現地では試行錯誤が続いている。
例えば、南相馬市では5月から内部被曝検査を学校健診に組み込んだ。また、相馬市は、今夏より小中学校での授業に放射線教育を組み込む予定だ。
教育と並んで重要なのが、情報開示だ。内部被曝検査を行っている施設は、その結果を定期的にホームページで公開している。地元メディアが詳細を報じるため、多くの住民が現状を認識するようになっている。
さらに、南相馬市立総合病院やひらた中央病院などの施設では、東京大学の専門家と協力し、検査結果を英文学術誌に学術論文として発表している。米国のワシントンポストやサイエンスなども取り上げた。一連の情報発信を通じて、世界は「福島の内部被曝は軽度である」と認識するに至った。
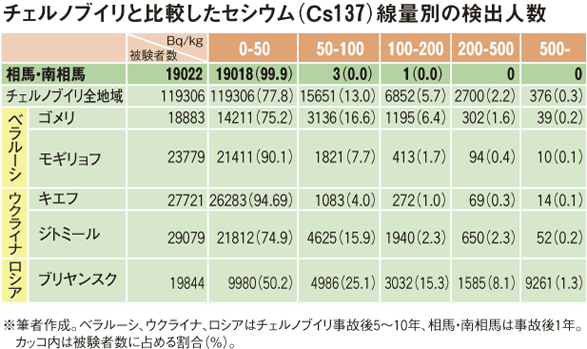
ちなみに、何百億円という予算が注ぎ込まれた福島県・福島県立医大から内部被曝に関する論文発表はない。
最近、福島県を訪問した上海の復旦大学の研究者は「中央政府は何をやっているんですか」と呆れ果てると同時に、「日本の地方の実力は、我々の想像を超えている」と賞賛した。
福島の内部被曝対策は、我が国の縮図だ。政治家や官僚は空理空論を弄ぶだけで、問題解決に寄与するところは少ない。
例えば、空間線量1ミリシーベルトを目標に、各地で除染作業が進められている。そのために、膨大な税金が費やされている。除染作業が本格化した12年度に関しては、政府予算として4513億円、南相馬市だけで、205億円が計上された。ところが、地元の評判は芳しくない。「大金を費やして、誰も住まないところを掘り返している」(現地住民)と揶揄される始末だ。「こんな金があれば、教育や医療に使って欲しい」という住民も珍しくない。
一方、福島の内部被曝を最小限に抑えてきたのは、当事者の地道な努力だ。試行錯誤を繰り返し、「放射線と共生する方法」を確立しつつある。
福島の人々は粘り強い。ゆっくりだが、着実に問題を解決している。やがて、原発事故を克服し、故郷を復興させるだろう。その日まで、筆者も福島の支援を続けたいと思う。




