本誌が見た「放射能の魔界」 福島原発は今、「水戦争」
敷地内に大小900を超える汚染水タンクがひしめく。原子力規制委員会と地元漁協の同意を得て海洋放出できるか。
2013年4月号
LIFE
by 現地ルポ/本誌 宮嶋巌

原発構内を埋め尽くす汚染水タンク(3月5日)

山側から見た4号機の原子炉建屋(3月1日)
Jiji Press
3月1日午前10時半。福島第一原発の免震重要棟内で白装束(防護服)に着替え、全面マスクを被る。綿手袋の上にゴム手袋を2枚重ねで着用し、異物が入らないように袖口をテープで封じる。靴下を2枚履き、不格好な防護靴に履き替えた。
免震重要棟前の空間線量は毎時23マイクロシーベルト(μSv)。取材陣を乗せたバスは、標高35メートルの高台からなだらかな坂道を走る(地図参照)。途端に携帯線量計の警戒音(100μSv超)が鳴り出す。どんよりとした空の下、灰色の海に面して並び立つ4つのタービン建屋の横をバスは南下。2年前の津波に押し流された発電設備やクルマの残骸が目に飛び込んできた。
「1080(μSv)です」と、案内役の東電社員の声が響く。測定地点は3号機タービン建屋の海側。これが、この日の最大値。3号機周囲は線量が高すぎて、全く手が出せないのだ。手に触れ、足が踏んだものすべてが汚染されている「放射能の魔界」と思い知る。
不安定な「4号機使用済み燃料」
4号機原子炉建屋の前でバスから降りる。震災時、4号機は定期検査中で全燃料が炉心から使用済み燃料プールに移されていたが、3号機から水素が流れ込み、建屋が吹き飛ぶ爆発を起こした。燃料プールの水が干上がり、むき出しになった1533体の核燃料が放射能をまき散らす悪夢に、世界中が震え上がった。政府・東電は4号機建屋の4階にある不安定なプールから使用済み燃料を取り出し、地上で貯蔵することを「廃炉」作業の最優先課題に据えた。
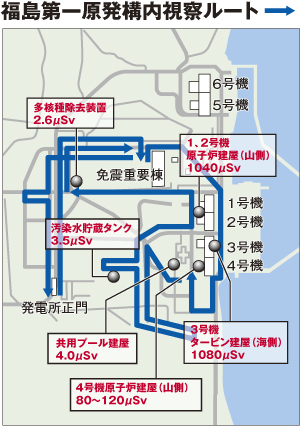
巨大なクレーンが上下し、工事車両が頻繁に出入りする作業現場は80~120μSv。巨大な鉄骨を組み上げた燃料搬出設備の土台が築かれていた。4号機の燃料搬出は、今年11月開始。移送先は、4号機の西隣りの建屋にある縦30m、横12m、深さ12mの共用プールだ。今回、初めて公開された青光りする共用プールの底には6377体の使用済み燃料が眠っていた。このプールには貯蔵余力がないため、水底の燃料をステンレス製の筒(乾式キャスク)に詰め替えて、陸上の仮保管場所に移動させなければならない。「玉突き」で確保したスペースに4号機の使用済み燃料を運び込む泥縄作業だが、ほかに手立てはなく、不安定なプールから核燃料を取り出し、地上で保管するまで約2年かかる。
バスは1号機原子炉建屋の山側を抜けた瞬間、空間線量は1040μSvにハネ上がる。約50m離れた1号機建屋の一角には、3号機と同レベルの10Sv(シーベルト) 前後(1Sv=100万μSv)の魔界が潜む。万一、その放射線を全身に浴びたら死を免れない。
田中規制委が「海洋放出」に理解
かつて「野鳥の森」と呼ばれた高台に向かうと、木々は1本残らず伐採され、汚染水を溜めるタンクがひしめき合っていた。原発構内の約16ヘクタールに、大小930ものタンクが立ち並び、総貯蔵量は約32万トン。すでに保管中の汚染水は26万トンに達しており、貯蔵余力は6万トンしかない。2011年夏の貯蔵量は約13万トンだったから、その増え方は尋常でなく、今も1日数百トンずつ増え続けている。
1~4号機建屋には、津波で海水が流れ込み、炉心溶融や水素爆発によって原子炉格納容器などが破壊された。事故直後、東電はポンプ車などを使って大量注水を行ったが、格納容器の底から水が漏れ、原子炉建屋やタービン建屋の地下へ広がった。その後、汚染水を浄化して原子炉に戻す「循環注水冷却システム」を導入したが、焼け石に水。山側から地下水が1日約400トンも流入し、約12万トンの汚染水が滞留する有り様だ。東電は山側に12本の井戸を掘り、1本で1日当たり約40トンの水を汲み上げる計画だが、抑制効果は未知数だ。

使用済み燃料が眠る共用プール(3月1日)
Jiji Press
結局、建屋地下に滞留する汚染水を汲み上げ、貯蔵するほかない。東電は貯蔵タンクの総容量を70万トンに増やす計画だが、敷地内には地盤の問題もあり、これ以上の増設はままならない。
バスは高台を走り、トリチウムを除く62核種を除去する「多核種除去設備(アルプス)」の前で止まった。アルプスは汚染水削減の「切り札」で、東電は放射性物質濃度基準をクリアした汚染水を、地元の同意を取り付け、海洋放出するチャンスを窺っている。そのアルプスは昨年中に稼働する予定だったが、高濃度廃棄物を入れる容器の安全性に問題があり、導入が遅れている。
アルプスの試運転許可申請に対して、原子力規制委員会は「汚染水の貯蔵が増えれば、水漏れなどリスクが高まる」として、条件付きで認可する考えだ。規制委の田中俊一委員長は「福島第一の現状は『水戦争』」と憂い、「アルプスから出てくる水というのは、通常であれば海洋放出できるようなレベルになる」として、海洋への「希釈排水」の可能性に理解を示した。
しかし、水素の同位体で水として存在するトリチウムの分離は難しく、アルプスでは除去できない。しかも、福島第一の滞留水のトリチウム濃度は、法規制の20倍~80倍もある。2月に福島第一の港湾内で捕られた魚(アイナメ)から、一般食品基準値の5100倍相当の放射性セシウム(1キロ当たり51万ベクレル)が検出され、風評被害を恐れる地元漁協らが受け入れるはずはない。福島第一は世界が注目する「海洋汚染型事故」であり、海に流せぬ莫大な汚染水との戦いが延々と続くのだろう。
政府と東電が定めた廃炉作業のロードマップによれば、2013年内に「4号機の使用済み燃料の取り出し開始」、21年内に「燃料デブリ(溶けた核燃料が金属と共に固化したもの)の取り出し開始」、そして51年までに「燃料デブリを回収し、原子炉建屋等を解体」し、作業を完了することになっている。今は入り口にすぎない。
「働く現場」の安全と安心が一番大切

吉田氏からバトンを受けた高橋毅所長(3月1日)
Jiji Press
免震重要棟内で会見に応じた高橋毅所長(東大修士・機械工学修了、55)は「米スリーマイル島原発事故では原子炉を冠水して燃料デブリを回収するまで十数年かかった。我々も放射線を遮蔽(しやへい)するため格納容器を水で満たさなければならないが、どこから水が漏れているのかわからない。1~3号機の建屋内には原子炉から漏れ出したデブリが格納容器や配管に散らばっており、ロボットでなければ近づけない場所がある。デブリの取り出しには特殊な遠隔除染技術や高性能ロボットが必要で、10年単位の作業になる」と、訥々(とつとつ)と語った。三つの原子炉がメルトダウンした例はなく、全てが手探りのうえ、デブリ取り出しという危険極まる高線量の大作業が待ち受けている。
高橋氏は柏崎刈羽原発の技術課長、福島第一の副所長(ユニット所長)、本店原子力運営管理部長を経て、癌に倒れた吉田昌郎前所長の後を継いだ。所長在任は通常2~3年。吉田氏からバトンを受けた高橋氏に続く15~20人の歴代所長に使命感と覚悟がなければ、廃炉作業は完遂しない。
現場のモチベーション確保を問われた高橋所長は「働く現場の安全と安心が一番大切です。とにかく、ここは線量が高い。年間積算線量が20m(ミリ)Svを超えると、作業員の皆さんは働けなくなってしまいます。建屋周辺の高線量のがれきを片付け、最近では月平均1mSvの被曝で収まるようになりました。毎日約3千人の作業員が入っていますが、協力会社の地元雇用率は約65%。地元の皆さんの思いに応えることが、現場の達成感につながっています」と答えた。
ここ数カ月、福島第一で働く作業員の登録は月平均約8千人、従業実績は6千人を上回っており、最も懸念された作業員確保で悩むことはなくなった。現場の線量を引き下げ、いかに安全を確保するか、歴代所長の手腕にかかっている(ちなみに約3時間の取材で筆者の被曝線量は92μSv)。
「廃炉」作業は、気の遠くなる苛酷な道のりだが、昨日から今日へ、今日から明日へ、一歩ずつ前に進んでいる印象を受けた。



