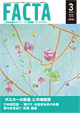「保育園不足」を見て見ぬふりの文科省
児童数が40%も減った小学校は空き教室だらけ。有効活用にも疑問符のつく校舎を「事業仕分け」せよ。
2010年3月号 DEEP

これまでの悪弊を変えられるか(川端達夫文部科学相)
Jiji Press
日本の高齢化率(65歳以上の人口比)が世界一の23%に達した。その主因は少子化にある。出生率が高ければ、高齢化のスピードは格段に緩やかだった。少子化問題は重要課題のはずだが、歴代の内閣はおざなりの対策に終始。慢性的な保育サービスの不足が、結婚や子育てへの心理的障害になっている。
新政権は、これまでより前向きな方針を打ち出した。子ども手当ではない。より実効性の高い保育サービスの拡充のことである。管轄である厚生労働省の官僚が保育に本腰を入れた同時期に、たまたま政権交代が重なった。1月末に閣議決定した少子化社会対策基本法の大綱、「子ども・子育てビジョン」の名称に新鮮味はないが、考え方は斬新だ。
保育サービスの必要度を初めて数値化したのである。需要予測にやっと踏み込み、今後5年間に0~2歳児の保育サービス利用者を現在の24%(75万人)から35%(102万人)へという目標を掲げた。これまでは、保育園に入園を希望していても満員で入れない待機児の数(毎年2万人前後)を発表し、その数を追いかけて保育園開設計画を作ってきたので、基本方針の転換ともいえる。
親が福祉事務所など自治体に保育希望を届け出ると、待機児と算定される。だが実態は、入園できないと判断した親の多くはわざわざ自治体に届けを出さない。そこで厚労省は待機児数を見限り、「潜在待機児数」を取り込んで需要を算定したのである。どんな公共事業でも事前の需要予測は当然のこと。やっとそのレベルに達した。
とはいうものの、ビジョンには「財源を論じない政策ではだめ」「これだけ多くの保育園の立地場所があるのか」という批判が出ている。待機児が多いのは、東京圏をはじめ近畿圏、仙台、福岡など限られた都市圏域であり、高価な土地の取得という問題を常に抱えているからだ。
少子化は校長にとって慶事
本当に安価で適格な場所がないのか。実はふんだんにある。少子化の結果、児童・生徒数が減った小中学校、つまり文部科学省管轄の教育機関だ。
校舎が現在のコンクリート造りになった1970年代以降で、全国の小学校児童数のピークは81年の1192万人、学級数は35万4千だった。それが、2009年には児童数が40%減の706万人、27万8千学級になった。東京都内では46万人、45%も減少。各学年1クラスしかない都心部の学校も多い。「運動会などの行事が成り立たない」との声もある。使われていない空き教室は公有地。もし保育園に転用すれば、待機児問題は一挙に解決するはずである。
かつて会計検査院は小中学校の空き教室の活用を指摘した。全国1056カ所の小中学校を調べた上、使っていない普通教室を老人福祉向けに活用するよう98年に当時の文部省に改善を促した。これを受け、同省は転用先として保育園も挙げながら地方自治体に伝えた。
だが、10年後の09年5月時点で用途変更した小学校教室は約4万に上っているものの、保育園に転用したのはわずか18校の39教室。都道府県別で最も待機児の多い東京都は2校、3教室だけだ。
横浜市のある小学校は、87年の開校時には1400人近い児童がいたが、今では7割以上減の360人となり、15の普通教室が他の用途に変わった。40人学級制度をはじめ知的・情緒障害児のための特別支援学級やパソコン授業で新たな教室が必要になったが、それでも教室には空きがあるはず。しかし、小中学校の所有・運営者である市区町村やその教育委員会の見解は違う。「教育に必要な有効な目的に転用し、空き教室は一つもない」と突っぱねる。
では、どのように「有効に」使われているのか。
ランチルームと名づけた教室は、異なる学年の児童が一緒に給食をとり「食育にぜひ必要」という。「雰囲気が大事」と普通の教室と違う色の壁紙で模様替えした学校も。利用頻度は「月に5、6回」にすぎない。
児童室は、学級の代表委員が学校行事などの話し合いをする教室。PTA活動のためのPTA会議室。「楽器練習の音が届かない」ための第二音楽室。算数の時間に、より少人数で授業を受けるために設けた学習室。
なかでも納得し難いのが郷土資料室。地域の農具や台所道具を集め、社会科の授業に役立てると言うが、ほとんど人の出入りがない。教材室も同様。地球儀や秤、丸めた地図などが教室の隅に並ぶだけ。職員室に移せるほどの量だ。机・椅子の保管庫は、倉庫代わりそのものだ。
図書室が三つある学校では、低学年向けの「絵本部屋」、辞書や地図をそろえた「調べ部屋」、それに「読み部屋」と命名。児童は4分の1に減って、120人余りしかいない。
さすがに「各学年1クラスしかないのにぜいたく」と首をかしげる校長もいるが、圧倒的少数だ。多くはいろいろな機能を持った教室が増えて喜んでいる。少子化は教育者にとって克服すべき難題ではなく、歓迎すべき慶事である。
転用先の優先順位はなく、転用方法は「学校長の判断が最優先される」(横浜市教育委員会)、「行政が決めてくる」(東京都内の小学校)と、まちまち。だが、共通しているのは教育現場に保育園への転用が全く念頭にないことだ。「学校はあくまで教育が目的。そのほかの用途は考えたこともない」と多くの教育委員会や校長たちは当然のように話す。校長は都道府県の任用職でもあり、学校と教育委員会が「空き教室はない」と公言すれば、市区町村の保育担当課が「保育園に使いたい」とは言い出せない。
品川区長の英断に学べ
こうした教育関係者の姿勢をリードしてきたのは文科省である。文科省は幼保一元化や放課後の学童保育でも、縄張り意識で親の希望を妨げてきた。年齢が近い小学校が保育園として好立地なのは明らかだが、「学校は自治体の財産なので文科省の要請にも限界がある。それでも、なぜ保育園への転用がほとんどないのか、これから調べたい」と呑気な言葉しか返ってこない。
ところが、小学校の活用を改めて考え直した自治体が出てきた。東京都品川区である。この4月から二つの区立小学校が、共に2教室を近くの区立保育園の園児向けに提供することになった。保育園の最年長児の5歳児向けに使うのが、これまでにない方式だ。
品川区は以前から小中一貫教育などに取り組んできており、今回の転用は昨秋、区長自ら決算特別委員会で発表した。従来の保育園への転用例では、待機児の多い0~2歳児が小学校の教室を使っており、調理室や洗面所、トイレの設備や登園の通路などの新設に多額の費用がかかったが、5歳児なら小学生と年齢が近いので給食や校庭を共用でき、メリットも多い。
この方式が各小学校で広まれば、その先に就学年齢の引き下げという制度変更の可能性もある。だが、肝心の文科省には思いもよらぬこと。事態を傍観するだけで、「文科省は少子化に手を貸している」との批判も免れない。
空き教室だらけの小中学校はムダの塊。「コンクリートから人へ」がスローガンの民主党は、ガラ空きのコンクリート校舎こそ、真っ先に「事業仕分け」の対象にすべきだ。