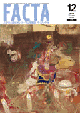一貫性欠く米国にアラブは「疑心暗鬼」
これでは欧州諸国やアラブの同盟国を「対イラン」で繋ぎ留められない。
2019年12月号
GLOBAL [特別寄稿]
by 田中浩一郎(慶應義塾大学教授)
2019年5月以降、ホルムズ海峡を間に挟むペルシア湾からオマーン海に至る海域で、船舶の安全航行に対する妨害行為が度々発生している。かつて、イラン・イラク戦争(1980~88)が激化する中、イラクとイランがそれぞれ相手国や第三国の原油を積載したタンカーを攻撃する、「タンカー戦争」がペルシア湾で起きたことがある。原油の中東依存が著しく高い日本はこの事態に大いに悩まされ、「シーレーン防衛」が議論される契機にもなった。結局、イ・イ戦争が1988年に終わりを告げると湾内の緊張は和らぎ、同海域は平時に戻った。その後、湾岸危機と湾岸戦争(1990~91)、さらにイラク戦争(2003)と、その都度、船舶の安全航行に対する懸念が取り沙汰されたが、幸いなことに商船への攻撃が再現されることはなかった。それが一転して、30余年前の悪夢が蘇る事態となったのだ。
フジャイラ沖に停泊中のタンカー4隻に対するサボタージュが5月上旬に発生し、続いて6月半ばにはオマーン海を航行中のタンカー2隻が襲われ、うち1隻が炎上する映像が世界中に配信された。サウジアラビアや米国は、即座にイランとその軍事組織であるイスラーム革命防衛隊を名指しで非難したが、イラン側はいっさいの関与を否定しており、米中央軍の発表と船員の目撃情報との間で整合性が取れないなど、犯人探しは迷走している。さらに、アラビア半島上ではサウジアラビアの石油パイプラインや油田、精油施設、軍事基地、空港がドローンや巡航ミサイルで攻撃された。毎回、イエメンの反政府武装組織ホウシー派が戦果を発表しているが、特に9月14日のアブカイク精油施設に対する攻撃については内容に矛盾が多く、欧州諸国などからも同派と友好関係にあるイランの関与を糾弾する声が出た。
衝撃の『英タンカー』拿捕
この間に、ホルムズ海峡とペルシア湾内では、イラン軍による外国籍タンカーの拿捕が相次いでいる。そのほとんどは、イランから安価な石油製品を密輸出するタンカーを領海内で取り締まる正当な行為であるため、対象も自ずと限定されており、船舶全般に対する安全航行上の脅威を構成するとは言えない。異例であり、衝撃が大きかったのが、英軍艦船の護衛を受けてホルムズ海峡を航行する英国籍のタンカーを、イラン軍が急襲して拿捕した事案だ。これは、一足先にジブラルタル海峡で英海兵隊によって自国タンカーが拿捕されたことへの報復と考えられ、同時に解放交渉を促すための「人質」の確保でもある。ほかにも、イランと米国が互いのドローンを撃墜しており、ペルシア湾近辺での軍事的な緊張が高まったことは明白だった。
この結果、周辺国や関係国にとって海事安全保障という課題が急務となった。米国は、反イラン「有志連合」の構築を同盟国や友好国に呼びかけ、各国はその対応に追われた。標的にされたイランは、米国主導の有志連合への反発と参加国への警告を露わにしつつ、「希望の連合」なる独自構想を提唱している。
共通しているのは、どちらも進捗が芳しくないことだ。イランを一連の攻撃の有責国とみなす風潮がある以上、ロウハーニ大統領が国連総会で掲げたイラン案が各国を惹きつけることに失敗したのは理解できる。一方、欧州諸国を筆頭に、ペルシア湾沿岸国の間でも、米国の有志連合構想とも距離を保とうとする傾向が強いことは否めない。これにはそれなりの背景がある。
対イラン強硬派『サウジ』も軟化
見落とせないのが、船舶の安全航行に対する一連の事案が始まった時期は、米国がイラン核合意(2015)から離脱して1年目を迎え、米国務省が革命防衛隊を外国テロ組織に指定してから1カ月後で、さらに、米国がイラン原油に対する全面禁輸措置の履行を宣言してからほどない頃に当たることだ。すなわち、「(イランから)謂れのない攻撃を受けた」と言う米国が、緊張が増進する舞台を用意したことに関して、実は一定の責任を負っているとみなされ、その意図を疑われている。
また、米国と同盟関係にあるペルシア湾岸のアラブ諸国の間でもイランと対峙することへの躊躇いがある。イエメン内戦にサウジアラビアとともに介入し、イランとつながるホウシー派と敵対してきたUAEも、自国が面する海域での緊迫感が高まるにつれ、件の有志連合への参加に踏み切りながらも、近年、激化していたイランとの対立姿勢から関係改善に向けて舵を切っている。自国のタンカーが被災したにもかかわらず、犯行主体の特定に関しては慎重な言動を見せる一方、イランとの海上警備活動での協力を再開し、首長家の枢要な人物を協議のためにイランに送り込んだ。相反する対応を見せるUAEに限らず、やはり有志連合に参画し、対イラン強硬論の最右翼であるサウジアラビアも、実質的な最高権力者であるムハンマド皇太子が最近では問題の外交的な解決への期待を語っており、イランとの直接対決を回避する道を模索している。
アラブ諸国の対応には、どこまで米国が信用できて、信頼に足る同盟相手であるのかという、米国に対する疑心暗鬼が決定的な影響を及ぼしている。先端兵器の購入や装備体系で米国に圧倒的に依存しているものの、彼らは安全保障のパートナーとしての米国の政策決定と行動には必ずしも満足していないのが実状だ。米国に対する猜疑心を深める契機となったのはアラブ各国がこぞって反対したイラク戦争である。その後、イラン核合意では蚊帳の外に置かれ、アサド政権による化学兵器使用疑惑に際しても米国が軍事攻撃を躊躇うなど、彼らの利益や立場が斟酌されない事例が続いた。
イランへの「最大限の圧力」を謳うトランプ大統領も、戦争回避を標榜し、イランとの首脳会談に期待を示すことから、アラブ側は、改めて梯子を外されることを危惧している。上述した一連の事案の発生に際して、米国は、明白な対イラン軍事行動は採らず、その後、IS相手にシリア北部で共闘したクルド人武装勢力をいとも容易く見捨てたことでも、アラブ側の懸念は増幅された。当初、米国をイランとの直接軍事対決に誘導することが米国のアラブ同盟国の狙いだったが、米国にその気がないと悟ったため、軌道修正を余儀なくされたのだ。
米国は、自らの一貫性に欠け、信頼を損なう行動によって、有志連合の構築と対イラン包囲網の強化に、欧州諸国やアラブ同盟国を誘い込むことに難儀している。